目次
【ビサヤ語とタガログ語の違い】フィリピン人はいつ英語を学ぶの?
〜セブ島で見えてくる、言語と教育のリアル〜
みなさん、こんにちは!今回はフィリピン・セブ島に留学や観光で訪れる人が意外と驚く「言葉の違い」について掘り下げてみたいと思います。
「フィリピンの公用語って英語とタガログ語でしょ?だったらタガログ語を少し覚えて行こうかな」
実はこれ、セブ島ではちょっとズレた感覚かもしれません。
セブ島をはじめとするビサヤ地域では、日常的に使われる言語が「ビサヤ語(セブアノ語)」なんです。
タガログ語は、実はマニラを中心としたルソン島エリアで主に話されていて、セブではほとんど使われません。
これ、日本人の感覚ではちょっと不思議に思えるかもしれませんよね。
「同じ国の中で、話す言葉が違って、しかも通じないこともあるなんて!?」
そうなんです。実際に僕もセブに来てみて、「公用語が英語とタガログ語」と聞いていたのに、現地で耳にする言葉はそれとは全然違う!という体験をしました。
これ、例えるなら――
関西弁で育った人が東京に行っても関西弁は通じるけれど、フィリピンのビサヤ語とタガログ語はもっと違う。
関西人がフランス語を話して、東京人がドイツ語を話してるくらいの違い、と言っても大げさじゃないくらいの「別言語」なんです(笑)
この不思議な言語事情に興味が湧いて、フィリピンの言語事情を少し深掘りしてみたら、文化・歴史・教育制度まで繋がっていてとても面白かったので、今回はそれをみなさんとシェアしてみたいと思います。
このページでは、
- セブの人はいつタガログ語を学ぶの?
- 貧困層と富裕層
- なぜ貧困層になる?
- フィリピン人の英語力
- 最後に
などを、体験ベースも交えながら紹介していきます。
日本では日本語ひとつで生活できるのが当たり前。
でもフィリピンでは、日常会話、学校教育、ニュース、ビジネスなど、シーンごとに「言語を使い分ける」というマルチリンガルな環境が当たり前なんです。
「言語=文化の窓口」とも言われるように、言葉の違いを知ることはその国の人の考え方や価値観を理解する第一歩になります。
それでは、言語の旅に出発してみましょう!

セブの人はいつタガログ語を学ぶの?

フィリピンでは、地域によって使われる言語が大きく異なります。たとえば首都マニラなどルソン島の人々は、日常的にタガログ語(現在のフィリピノ語)を話しますが、ここセブ島では「セブアノ語(ビサヤ語)」が圧倒的に主流です。
では、セブ出身の人たちはいつ、どのようにしてタガログ語を学ぶのでしょうか?
実際に3D ACADEMYの先生に聞いたところ、「簡単なタガログ語には、幼稚園の頃から少しずつ触れていく」とのことでした。具体的には、アルファベットや簡単な単語、日常表現などを先生が歌やゲームを交えて教える場面が多いそうです。ですがこの時点では、あくまで「聞いたことがある」程度で、実際に話す機会はあまりないようです。
本格的にタガログ語の勉強が始まるのは、小学校に上がってから。国語の授業では、基本的にタガログ語が使われ、読み書きの基礎をしっかり学ぶカリキュラムになっています。授業で使われる教科書の多くはタガログ語で書かれており、首都圏の子どもたちと同様に、セブの子どもたちもこの時期から徐々に「第2の言語」としてタガログ語を学び始めるのです。
ただし、ここで少し複雑になるのが、英語の存在です。
フィリピンでは英語も公用語のひとつとして広く使われており、数学や理科など、一部の教科書は英語で書かれています。そのため、子どもたちは学校で3つの言語に同時に触れる環境に置かれています。家庭ではビサヤ語、国語ではタガログ語、理数科目では英語…といった具合です。
このマルチリンガル環境は、日本人から見るとかなり特殊に思えるかもしれません。私たちが育つ環境では、日本語だけでほぼすべてが完結します。ところがセブの子どもたちは、5〜6歳のころから複数言語を聞き分け、使い分けるという脳のトレーニングを日常的に行っているのです。
また、語学習得を自然に促してくれるのが「テレビ」です。
多くの家庭では、日常的にテレビがついており、ニュースやドラマ、バラエティ番組などはほぼすべてタガログ語で放送されています。子どもたちはテレビを通してタガログ語のリズムや言い回し、イントネーションに自然と親しんでいきます。つまり、「習う」よりも「慣れる」ことで、実践的な語彙や会話表現が身についていくわけですね。
このような背景から、セブ出身の多くの人は、成長する過程で「セブアノ語(第一言語)」「タガログ語(第二言語)」「英語(第三言語)」の3つを習得することができます。しかもそれぞれが実際の生活の中で使われている言語なので、単に学問として覚えるのではなく、実用の中で定着していくという点も特徴です。
その結果、セブの若者たちは、進学や就職でマニラに出てもすぐに現地の言葉(タガログ語)に適応でき、さらに国際的な仕事でも英語を活用できる、非常に柔軟な言語スキルを持つようになるのです。
ちなみに余談ですが、フィリピンでは移動販売のコマーシャルやテレビのCM、さらには学校の校内放送なども、それぞれ地域によって言語が異なります。セブならセブアノ語、マニラならタガログ語。観光客にとっては、この言語の違いがとても面白く感じられるポイントの一つかもしれません。
貧困層と富裕層で異なる「英語との距離感」

「フィリピンでは英語が公用語」というイメージを持つ方は多いですが、実際にはフィリピン人全員がネイティブのように英語を話すわけではありません。英語の習得度や話す頻度には、実は社会的な背景、特に「家庭の経済状況」が大きく関係しているのです。
実は親世代が英語を話せないことも多い
3D ACADEMYで出会った先生たちから聞いた話で驚いたのが、「自分の両親は英語をほとんど話せない」という事実です。これは決して特別な話ではなく、実際に地方部や貧困層の家庭ではよく見られる光景です。英語教育を十分に受ける前に学校を中退してしまうケースも多いため、大人になっても英語が苦手という人が一定数存在します。
とはいえ、フィリピンの言語環境はとてもユニークで、セブアノ語(ビサヤ語)の中には日常的に英単語が取り入れられており、「英語がゼロ」という人は少ないようです。例えば「school」「office」「computer」「TV」などの単語は、セブアノ語の会話でもそのまま使われることが多く、日本語におけるカタカナ英語のような感覚で混ざっています。このため、「英語がまったく通じない」という場面は日本に比べるとかなり少ないのが実情です。
英語の“スタートライン”が違う
ただし、英語が混ざっているとはいえ、本格的に英語を学ぶタイミングには家庭の事情が大きく影響します。特に貧困層の子どもたちは、小学校に入る頃までに十分な教育機会を得られず、英語に触れるタイミングも遅くなりがちです。さらに、教育費や交通費の問題、親が学校教育の重要性を理解していないなどの理由から、小学校を中退するケースもあります。こうした環境では、英語の語彙力や文法理解を伸ばすことが難しく、結果的に社会人になっても英語力があまり身についていないことがあります。
一方で、富裕層の家庭はまったく逆のアプローチをとります。教育に対して非常に熱心で、幼児期から英語での絵本読み聞かせや、英語のテレビ番組、さらには英語塾やプライベートレッスンを受けさせる家庭も珍しくありません。中には、家庭内で親子の会話をすべて英語で行うような“英語イマージョン”教育を実践している家庭もあり、小学校に上がる頃にはすでに簡単な日常会話ができる子もいます。
テレビが英語・タガログ語の窓口に
また、家庭にテレビがあるかどうかも英語力に影響します。フィリピンでは全国放送のテレビ番組の多くがタガログ語、または英語で放送されています。そのため、テレビがある家庭の子どもは、自然と日常的にタガログ語や英語に触れる機会が増えます。特に英語のアニメや洋画、ニュースなどを通じて、耳が英語に慣れていくのです。
テレビがない家庭、または電気の供給が不安定な地域では、こうしたメディアによる言語習得の機会が乏しく、英語への接触頻度も限られてしまいます。この点でも、家庭環境の違いが子どもたちの英語能力の差を生んでいるのです。
格差は「話す機会」にも現れる
富裕層の子どもたちは、英語を使う環境にも恵まれています。例えば、私立の小学校では授業の多くが英語で行われ、先生との会話も英語中心です。友達との間でも“英語のスピーキング力を鍛える”ような環境が整っています。
一方で、公立学校では教師の英語力にばらつきがあり、授業もセブアノ語やタガログ語が多く混ざる傾向があります。つまり、英語に「触れる量」も「使う頻度」も、富裕層と貧困層では大きな開きがあるのです。
フィリピンにおいて貧困は非常に根深い社会問題ですが、その根本的な原因の一つに「教育格差」と「英語力の差」があります。特に英語力が人生の選択肢に直結するこの国では、「英語を話せるかどうか」が経済的階層を左右する決定的な要素となっています。
英語が話せないと「できる仕事」が限られる
現代のフィリピンでは、英語を使いこなせることが「社会的な武器」になります。観光業、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、教育、航空、ITなど、高収入の職業の多くは英語を前提とした業務です。
一方、英語力が乏しい場合、就ける仕事は非常に限られます。たとえば、建設現場の肉体労働者、屋台の販売員、バイクタクシー(ハバルハバル)の運転手、メイドなど、低賃金かつ体力勝負の仕事に偏ってしまいます。
その結果、十分な収入を得ることができず、子どもを学校に通わせる余裕がなくなり、次の世代も同じ貧困のサイクルに巻き込まれていくのです。
「教育を受けられるかどうか」が人生を分ける
フィリピンでは、小学校から高校までは義務教育とされていますが、経済的に苦しい家庭では、学費以外のコスト(制服代、通学費、教材代)を負担できないケースが少なくありません。これが原因で、小学校高学年や中学の途中で退学してしまう子どもが多く存在します。
特にセブのような都市部に住むスラム地区では、教育よりも「家計を助けるために働く」ことを選ばざるを得ない家庭もあります。親が教育の重要性を理解していても、現実的な生活の厳しさが子どもたちの未来を奪ってしまうのです。
英語が「富裕層の共通言語」になっている
一方、富裕層の子どもたちは幼少期から英語に囲まれた環境で育ちます。家庭では親が英語で話しかけ、インターナショナルスクールや私立の良質な学校に通い、英語を「当たり前の言語」として習得します。テレビ番組や読書の習慣も英語中心で、自然とスピーキングやライティングも上達していきます。
そのため、大学に進学するころにはネイティブに近いレベルで英語を操れるようになり、グローバル企業や政府機関、大手メディアなど、社会的に影響力のある職業への道が開かれます。
富裕層の間では、もはやタガログ語やビサヤ語は「家で使う言語」に留まり、実社会では英語が主役となるのです。
英語力が「格差の再生産装置」に
こうした状況を整理すると、英語を話せない → 低賃金の仕事 → 教育費不足 → 子どもも学校に行けない → また英語を話せない、という「貧困の再生産」が起きていることがわかります。
そして、その逆もまた然りで、英語を話せる → 良い仕事に就ける → 高い収入 → 子どもに良い教育を与えられる → 子どもも英語が話せる → 次世代も成功、という「富裕層の再生産」も並行して起きているのです。
これはフィリピンに限らず、英語が重要視される国々に共通する傾向ではありますが、特に公用語が英語でありながら実際には習得に格差があるフィリピンでは、この「英語格差」が社会階層を決定づける要因として非常に顕著です。
英語が話せれば貧困から抜け出せるのか?
では、英語が話せれば必ず貧困を脱出できるのか?もちろん答えは「イエス」であり「ノー」でもあります。
確かに英語力があれば、コールセンターやオンライン英会話講師など、比較的高収入な職に就ける可能性が広がります。しかし、そもそも英語を習得するには時間と努力、そして「学ぶ場」が必要です。
家庭で英語に触れられない、インターネット環境が整っていない、学校にまともな英語教師がいないという状況では、学習自体が困難です。また、教育を受けても途中でドロップアウトしてしまえば、せっかく身につけたスキルも中途半端なまま終わってしまいます。
大学まで進学できればチャンスはある
とはいえ、高校・大学まで進学できた場合、特に大学の授業は基本的に英語で行われるため、英語力は大きく伸びます。そして、その英語力を武器に、外資系企業、航空会社、観光業、IT分野、英語講師、公務員などへの道が開けます。
この「大学進学」こそが貧困のサイクルから抜け出す鍵であり、英語を実用レベルで習得する最後のチャンスでもあります。だからこそ、フィリピンでは「子どもには大学まで行かせたい」という親の願いが非常に強いのです。
フィリピン人の英語力

フィリピン人の英語力|話せる人・話せない人の分かれ目は?
私たち日本人や、他の外国の方にとって、フィリピン滞在で最も重要なのは「英語力」です。なぜなら、観光であれ留学であれ、現地の人とのコミュニケーションが英語でできなければ、どこかで不安を感じてしまうからです。レストランでの注文、道案内のやりとり、トラブル時の対応など、英語が通じるだけで安心感が大きく違います。
では、実際のところ、フィリピン人はどの程度英語が話せるのでしょうか?
一見すると、フィリピンでは「英語が公用語」とされているため、誰でも英語がペラペラな印象を持たれがちです。しかし、現実はそれほど単純ではありません。確かに、政府や教育機関では英語が多く使われていますが、日常生活では「英語を話す機会がほとんどない人」も存在します。
英語よりも母語での会話が基本
例えば、セブ島の一般家庭では、日常の会話はほとんどが「ビサヤ語(セブアノ語)」です。友達や家族との会話はもちろん、学校の休み時間、近所の人とのやりとり、日常の雑談なども全てビサヤ語で済んでしまいます。そのため、英語を話す場面は「授業」や「仕事」など、特定のシーンに限られることが多いのです。
つまり、たとえ英語教育を受けていたとしても、実際に英語を話す機会が少ない人は、英語のリスニングやスピーキングに自信がないという状況になります。
貧富の差が「英語力の差」に直結する
ここで大きな影響を与えているのが、家庭の経済状況です。アヤラモールやSMモールなどの大型ショッピングセンターで英語を話している親子連れを見かけたことがあるかもしれません。彼らは比較的裕福な家庭の出身で、子どもを「私立の学校」や「インターナショナルスクール」に通わせているケースが多いです。
こうした学校では、授業はほとんど英語で進められ、先生との会話も英語、友達同士のやりとりも英語、という環境が整っています。家庭でも親が英語を話せるため、自然と子どもも英語でのやりとりに慣れていきます。こうして、彼らはごく自然に「日常的に英語を使う生活」を送っているのです。
一方で、貧困層の家庭では、教育にかけられるお金も限られ、公立学校に通う子どもが多くなります。公立校でも一応は英語教育がありますが、先生の質や授業時間数、教材の整備、家庭での学習支援などにおいて、どうしても私立校に比べてハンディキャップがあります。
英語力は将来の職業選択を左右する
このようにして、英語が話せるかどうかは、そのまま将来の職業選択の幅に直結します。フィリピンでは「英語が話せない人=貧困層」と見なされることも多く、英語を使わない低賃金の肉体労働や単純作業に就くしか選択肢がなくなってしまうこともあります。
逆に、英語がある程度話せる人は、コールセンター、ホテルスタッフ、オンライン英会話講師、国際企業への就職、公務員など、より安定した職や高収入のチャンスを得やすくなります。実際、多くの若者が「英語を話せるようになって人生が変わった」と語っており、それがこの国における学歴と英語力の重要性を象徴しています。
フィリピン留学で英語を話せる人に会えるのか?
では、私たちがフィリピンに留学や旅行で訪れたときに、英語を話せる人と出会える確率はどのくらいでしょうか?
結論から言えば、都市部の若者や接客業の人たちは比較的英語が得意なケースが多いです。例えば、セブ市内の語学学校の先生たちはもちろん、モールの店員さんやホテルのスタッフ、カフェの店員なども、英語で接客ができるレベルには達しています。
ただし、少し郊外に行くと、英語が通じづらくなる場面もあります。トライシクルの運転手、ローカル市場のおばちゃん、田舎の屋台のスタッフなど、英語を使う機会が少ない人は、簡単な単語レベルの会話しかできない場合もあります。
このギャップを知っておくと、フィリピン滞在時のコミュニケーションのハードルが少し下がるかもしれません。
最後に
フィリピンの言語について調べたり実際に現地の人と話したりする中で、単に言葉の話だけではなく、フィリピンという国の社会背景や教育格差までが少しずつ見えてきました。
まず一つ、素直に「すごいな」と思ったのは、彼らが小さい頃から3つの言語に自然と触れながら育っていることです。家庭で使うセブアノ語(ビサヤ語)に加えて、学校教育で教わるタガログ語、そして英語。まるで「トリリンガルになることが当たり前」みたいな環境なんですね。
これを日本に例えるなら、大阪で生まれ育って関西弁を話しながら、学校では標準語と英語を学ぶ、というようなイメージです。僕自身大阪に住んでいますが、標準語で話すとちょっと照れくさいし、難しく感じることもあります。そう考えると、フィリピンの子供たちが日常的に3言語を使い分けているのは、本当にすごいことです。
次に感じたのは、「英語を話せるようになるまでの過程」が、決して簡単ではないということ。日本ではよく「フィリピン人は英語が得意」と思われがちですが、実際には家庭の経済状況によって教育格差があり、全員が流ちょうに英語を話せるわけではありません。
それでも、英語を話せることがフィリピンでは「人生の選択肢を広げる鍵」になっているため、多くの子供たちが一生懸命勉強しています。そういった努力を見ていると、貧しい家庭の子供たちが「英語が話せるようになって、将来はもっと良い暮らしをしたい!」と夢を見る気持ちがとてもよくわかります。
そして、フィリピンの社会を見ていると「まだまだ発展途上で、学歴や語学力がそのまま将来の生活レベルに直結している」ような、そんな雰囲気を強く感じました。今の日本は情報社会に突入し、学歴よりスキルや経験が重視される時代になりつつありますが、フィリピンでは今でも「いい大学を出る」「英語を話せる」というのが、安定した職や高収入への第一歩。
フィリピンに来て生活してみると、どこか昭和後期〜平成初期の日本を思い出すような空気があって、どこか懐かしさすら感じることもありました。
だからこそ、日本人としてただ観光や留学をするだけでなく、こうした背景にも少しだけ目を向けてみると、きっとフィリピンのことがもっと好きになると思います。

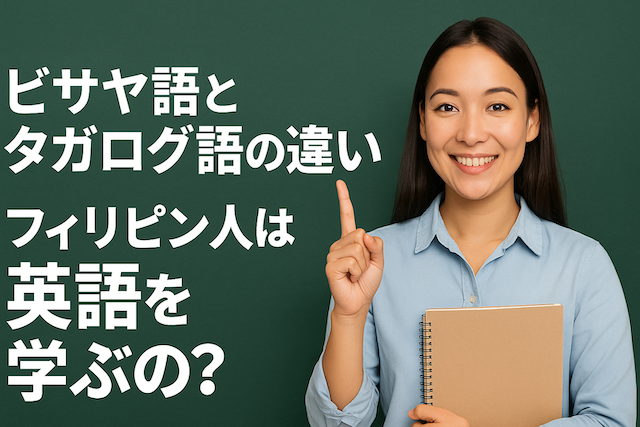




![[セブ島女子留学]フィリピン脱毛事情。激安ブラジリアンワックス!](https://3d-universal.com/wp-content/uploads/2016/08/IMG_3005-768x576.jpg)