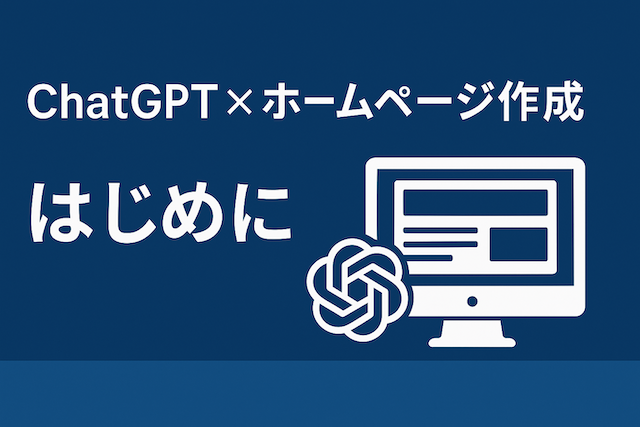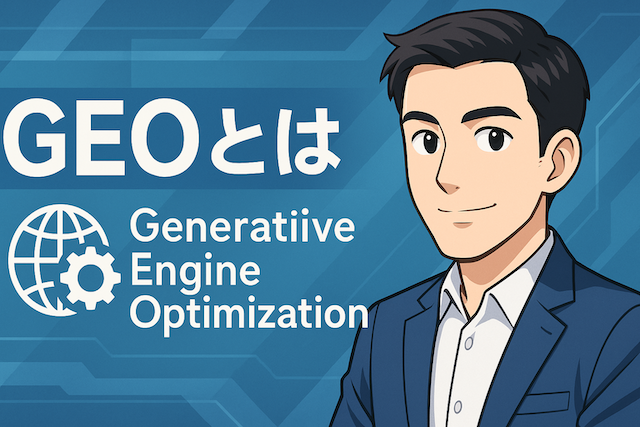目次
第6章:AI時代のEEAT戦略とChatGPTの限界
生成AI時代に、EEATがより重要になる理由
2024年以降、SEO界では**“AIファースト時代”におけるEEATの再定義**が急務となっています。
Googleが「AI生成コンテンツはガイドライン違反ではない」と明言した今、重要なのは「信頼されるAI活用コンテンツの設計」です。
その中核をなすのが、SEOの4本柱である「EEAT」:
-
Experience(経験)
-
Expertise(専門性)
-
Authoritativeness(権威性)
-
Trustworthiness(信頼性)
ChatGPTはこのうち、特に「専門性」「論理性」では大きな支援が可能ですが、
“体験”や“信頼”の領域には限界があります。
✅ 1. EEATとは何か?2025年版の定義と評価基準
EEATとは?
EEATとは、Googleの検索品質評価ガイドラインに基づいた「高品質コンテンツ」の4つの柱です:
-
E(Experience|経験)
筆者がその内容を“実際に体験したか” -
E(Expertise|専門性)
筆者がその分野について“十分な知識を持っているか” -
A(Authoritativeness|権威性)
筆者やサイト自体が“信頼される立場にあるか” -
T(Trustworthiness|信頼性)
内容が“正確・安全・誠実”であるか
かつては「E-A-T」でしたが、2022年末から「E」が追加され、「経験が重視されるように」なりました。
EEATは順位にどう関係する?
Googleは「ランキングの直接要因ではない」とは述べていますが、
実際には下記のような形でアルゴリズムに間接的に組み込まれていると見られています:
-
YMYLジャンル(医療・金融・法律など)ではEEATの有無が大きく順位を左右
-
AI生成コンテンツの信頼性評価にも用いられる傾向
-
スニペット表示やSGEへの引用にも影響
2025年以降の変化:EEAT重視の傾向が加速
2025年時点では、以下の動きがEEAT評価の強化を示唆しています:
-
Googleは著者プロフィールや体験情報の明記を高く評価するように
-
SGE(Search Generative Experience)やAIスニペットの生成において、信頼される情報源が引用されやすい
-
EEATは個人・法人を問わず全ジャンルで基本要素に
つまり、AIで誰でも情報発信できる時代だからこそ「誰が書いたか」「どんな経験に基づくか」が問われるようになっているのです。
✅ EEATを評価されるコンテンツの特徴(簡易チェック)
| 評価軸 | チェックポイント |
|---|---|
| 経験 | 体験談がある/筆者の声がある/一次情報が含まれる |
| 専門性 | 専門用語の適切な使い方/根拠ある説明 |
| 権威性 | 実績・資格・他サイトからの引用/被リンク |
| 信頼性 | 明確な著者表示/正確な情報源/更新日あり |
✅ 2. ChatGPTが得意なEEAT領域・苦手な領域
生成AIであるChatGPTは、SEOにおけるEEATの一部を大幅に効率化できます。
ただし、すべての要素をAIで担うことは不可能です。
ここでは、EEATの4要素それぞれについて、ChatGPTの「得意/不得意」を整理し、人間がどこを補完すべきかを解説します。
ChatGPTが得意な領域
| EEAT要素 | 得意な理由 |
|---|---|
| Expertise(専門性) | 豊富な知識データをもとに、用語や仕組みを正確に説明できる |
| Trustworthiness(信頼性) | 引用形式・論理構成・客観表現が得意で、正確な文体が書ける |
特に「用語解説」「仕組みの説明」「手順化」など、情報整理や説明系のコンテンツではChatGPTは非常に優秀です。
⚠️ ChatGPTが苦手な領域
| EEAT要素 | 不得意な理由 |
|---|---|
| Experience(経験) | 実体験を持たないため、エピソードや感情の再現が不自然になりやすい |
| Authoritativeness(権威性) | 実在の経歴・実績・所属を持たないため、著者の信頼性を補完できない |
つまり、ChatGPTは“情報整理のプロ”ではあるが、“体験の語り手”や“実績の証人”ではないということです。
人間が補完すべきポイント
ChatGPTでEEATを最大化するには、以下のような人間の編集・加筆が必要です:
-
実際に行った経験や感想を挿入する(例:「私は実際に使ってみてこう感じました」)
-
著者プロフィールに専門性や実績を明記する(例:「●●の認定資格を保有」)
-
サイトに信頼性のあるリンク(公式情報、他社引用など)を適切に配置する
-
画像・動画・証拠資料など一次情報を添付する
EEAT補完のベストバランスは“ハイブリッド型”
ChatGPT:
→ 構成案、本文のたたき台、FAQ、JSON-LD、SEO最適化部分を担当
人間(あなた):
→ 体験談・観点の挿入、著者開示、実績裏付け、感情表現の肉付けを担当
このように、AIと人間の分業体制を意識することで、EEATに強い高品質コンテンツが実現します。
✅ h2-3. EEATを補完するプロフィールと実績情報
生成AIによるコンテンツが溢れる中で、Googleが特に重視しているのが**「誰が書いたか?」という文脈情報**です。
ChatGPTがいくら説得力のある記事を書けたとしても、書き手の背景が不明なままではEEATの評価を得ることは難しいのです。
このセクションでは、SEOにおけるEEAT強化のために不可欠な著者情報・プロフィール・実績提示の方法を整理します。
なぜ“プロフィール”が重要なのか?
Googleの検索品質評価ガイドラインには、次のような記述があります:
“このページの制作者は、トピックに関して経験や専門性を持っているか?プロフィールページや外部情報で確認できるか?”
つまり、検索アルゴリズムは「本文」だけでなく、「著者・運営者に信頼性があるか」を裏側で評価しているのです。
EEATを補強する「プロフィールの要素」
| 要素 | 内容例 |
|---|---|
| 名前(できれば実名) | 例:Hideyuki Fujiki|SEOコンサルタント |
| 経歴・専門領域 | 例:大学卒業後、Web制作・SEO業界に15年従事 |
| 所属・実績 | 例:3D ACADEMY運営/月間30万PVのブログ運営者 |
| 資格・受賞歴 | 例:Google認定SEOスペシャリスト/ChatGPT講座登壇実績あり |
| SNS・外部リンク | X(旧Twitter)/note/LinkedIn/YouTube等へのリンク |
著者情報の掲載方法(テンプレート例)
よくあるNG例とその対策
| NGパターン | 対策方法 |
|---|---|
| ChatGPTに任せて著者名がない | 実名・ハンドルネームを記載し、外部SNSやプロフィールと接続する |
| 専門性が伝わらない | 「なぜこのテーマを書けるのか」を経歴・経験として明記する |
| 実績の証拠がない | 資格、数字(PV数、順位)、外部リンクで裏付ける |
✅ まとめ:AI時代の著者情報は“信頼の出発点”
AI生成コンテンツ全盛の今、「誰が書いたか」を明示することは信頼の最短ルートです。
ChatGPTで優れた本文が書けたとしても、それを支える“著者”という土台がなければ、Googleも読者も評価しません。
SEOのためにも、今こそプロフィール設計を見直すタイミングです。
✅ 4. AI文章に“人間らしさ”を注入するプロンプト技術
ChatGPTで生成される文章は、正確で整っている反面、どうしても「無機質で感情のない」印象を与えがちです。
Googleも読者も重視する「人間らしさ」や「体験のリアリティ」は、プロンプト次第で強化可能です。
このセクションでは、AI文章に「温度感」や「納得感」をもたらすプロンプト設計のテクニックを紹介します。
なぜ“人間らしさ”が必要なのか?
-
EEATのExperience(経験)を補完するため
-
AI検出回避のため(人間らしい言葉の選び方)
-
読者との共感や信頼形成のため
実際、体験談・例え・失敗談・感情などがあるだけで、
「読んでもらえる時間」と「シェア率」が大きく変わります。
✅ ChatGPT用 プロンプトテンプレート(人間味挿入ver)
ChatGPT × 人間らしさの融合がEEAT時代の鍵
いまや情報はAIで作れて当たり前。
その中で「読まれる文章」「信頼される情報」にするには、人間にしか出せない“温度”と“視点”が決め手です。
そして、その“人間性”すらもプロンプト設計で再現できる時代。
テンプレ化しておけば、誰でも再現可能です。
✅ h2-5. ChatGPT×EEATチェックリストの導入と運用
AIでコンテンツを量産する時代において、品質を保つ鍵となるのが「EEATチェック」です。
とくにChatGPTを活用してSEO記事を制作する際、仕上げに“人間の目で見るEEAT視点のチェック”を挿入することで、評価されやすいコンテンツに変わります。
このセクションでは、ChatGPTでも扱えるEEATチェックリストの設計方法と、その運用法を紹介します。
✅ EEATチェックは“構成”よりも“中身”の評価が重要
EEATは単なる形式ではなく、「中の人(著者)に信頼があるか?内容が経験や裏付けに基づいているか?」を問う概念です。
そのため、以下のような観点から記事を見直す必要があります:
| チェック項目 | 内容のポイント |
|---|---|
| 経験 | 筆者自身の体験談や実例が含まれているか |
| 専門性 | 専門的な用語・根拠・出典などが使われているか |
| 権威性 | 著者プロフィールや資格・所属が明示されているか |
| 信頼性 | 正確性/引用元/最新性が担保されているか |
ChatGPTで使えるEEATチェック用プロンプト
ChatGPT自身にEEAT的な視点での評価を依頼することで、抜け漏れや弱点を洗い出すことができます。
ChatGPT生成記事をEEAT視点でレビューするフロー例
-
ChatGPTで初稿を生成(構成や本文を自動化)
-
上記のプロンプトでEEAT観点のレビューを依頼
-
返ってきた指摘を元に、著者情報・体験談・出典を補強
-
必要に応じて自分の経験・主張を追記して完成へ
EEATチェックリストをNotion/スプレッドシートで共有
社内・チーム・外注先と共にSEOコンテンツを運用する場合、チェックリストの共有が非常に有効です。
| 項目 | 確認内容 | チェック |
|---|---|---|
| 経験 | 筆者の体験が入っているか? | ✅ |
| 専門性 | 専門知識や根拠の記載があるか? | ✅ |
| 著者情報 | プロフィールや外部リンクがあるか? | ✅ |
| 信頼性 | 引用・統計などがあるか? | ✅ |
このように「EEATテンプレート化」しておくことで、品質ブレのないSEO運用が可能になります。
✅ まとめ:AIに任せすぎない“人間の品質管理”が鍵
どんなに優れたプロンプトで記事を自動生成できたとしても、
最後に人間のEEAT視点でレビューを加えることで、Googleにも読者にも届く記事に仕上がります。
AI+EEATチェックこそ、これからのSEO運用のベースです。