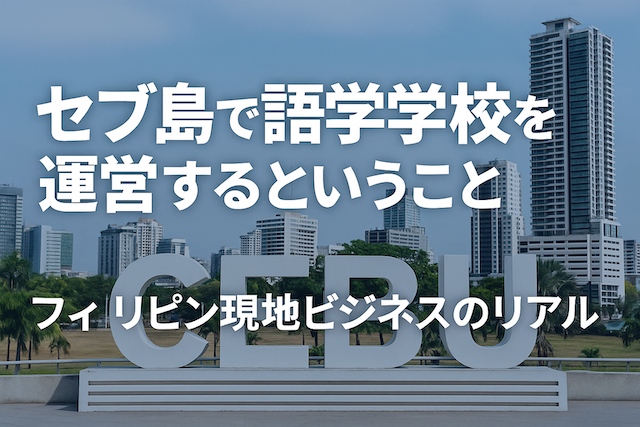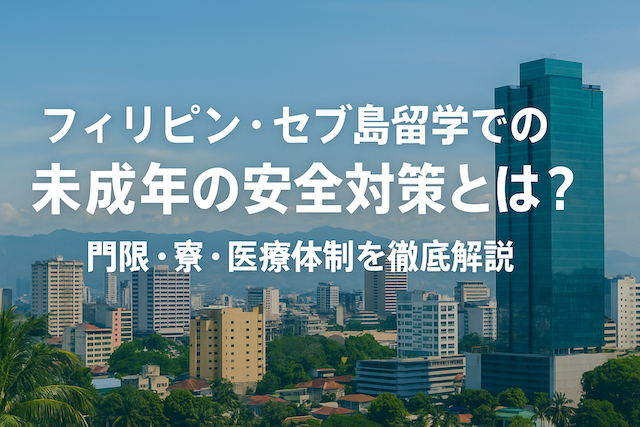目次
セブ島で語学学校を運営するということ|フィリピン現地ビジネスのリアル
はじめに:セブ島=語学留学のメッカになった理由
かつて「留学」といえば欧米が主流でした。しかし2000年代後半から、英語を第二言語とするフィリピン、とくにセブ島が「安くて、短期間でも成果が出る留学先」として注目を集めるようになります。日本・韓国・台湾といったアジア諸国の若者たちがこぞってセブを訪れ、今では年間数万人が英語を学びに訪れるまでになりました。
その背景には、マンツーマン授業を軸とした教育スタイル、費用対効果の高さ、そして親しみやすいフィリピン人講師の存在があります。
こうした留学需要の高まりに伴い、「自分で語学学校を立ち上げたい」「教育ビジネスを海外で展開したい」と考える人も増えてきました。しかし、実際にセブ島で語学学校を運営するというのは、理想や情熱だけでは続けられない、非常に“地に足のついた”ビジネスでもあります。
フィリピン現地で語学学校を運営するとはどういうことか?
日本国内で教育ビジネスを立ち上げるのと、フィリピン・セブ島で語学学校を運営するのとでは、同じ「学校経営」であってもまったく別の次元の話になります。違う国に根を張るということは、言葉や文化、法律、そして常識までもが異なる中で、一つひとつを自ら学び、現地に合わせて運営していく必要があるということです。
ここでは、実際にフィリピンで語学学校を運営する際に直面する、代表的な5つの側面について紹介していきます。
1. 法制度と認可手続きの複雑さ
フィリピンで合法的に語学学校を運営するには、複数の法的ステップを踏む必要があります。以下は主なものです:
-
SEC登録(法人設立)
-
TESDA認可(職業訓練校としての資格)
-
SSP発行機関としての登録(特別就学許可)
-
BIR登録・納税義務の確立(フィリピン税務局)
-
労働省(DOLE)との関係性(外国人雇用許可など)
これらの手続きは書類の不備や担当者の気まぐれによって遅延しやすく、1つの許認可に数か月を要することも珍しくありません。さらに、提出すべき書類も年々更新されるため、現地の行政手続きに精通した弁護士やコンサルタントとの連携が欠かせません。
また、外国人が経営者となる場合、「100%外資系」としてではなく、フィリピン人パートナーとの共同出資や特別な法人形態(例:PEZA登録、学術機関としての認可など)を模索することもあります。
2. 講師の採用・教育・マネジメント
フィリピン人講師は、英語を第二言語として習得しながら、日常的に高い英語力を使いこなしているため、ESL(English as a Second Language)教育の現場では非常に優秀な人材が揃います。
しかし、質の高い講師を採用・維持し続けるのは容易ではありません。
採用の課題:
-
TESOLや教育免許を持つ講師は給与相場が高い
-
競合校による引き抜きが頻発
-
履歴書だけでは判断できない「教える力」の見極めが必要
マネジメントの課題:
-
時間感覚や報連相の文化が日本と異なる
-
休暇・家族行事への配慮が不可欠
-
生徒からのフィードバックとのバランスを取る必要性
研修体制が甘いと、いくら英語力が高くても「教えるスキル」が育ちません。そのため、多くの学校では入社後2週間程度の集中トレーニングや、定期的な評価制度、模擬授業チェックなどを導入しています。
3. 生徒対応とカスタマーサポート
セブ島の語学学校に通う学生は、10代の中高生から、大学生、社会人、シニアまで実に多様です。さらに国籍も、日本・韓国・台湾・中国・中東・モンゴル・アフリカなどへと広がっています。
そのため、生徒一人ひとりに合わせた対応が求められます。たとえば:
-
病気や体調不良時の医療サポート(現地の病院手配、通訳同行など)
-
盗難・トラブルへの対応(警察対応、寮内の監視体制など)
-
宗教や食事の配慮(ハラル対応、ビーガンメニューなど)
-
進学・就職のサポート(TOEIC対策、推薦状の発行など)
これらに加えて、日本のように24時間整った行政・保険制度があるわけではないため、語学学校側の“生活サポート機能”は事業の一部として非常に大きな比重を占めています。
4. 現地スタッフと築く信頼関係
講師以外にも、運営を支える裏方スタッフ(清掃・受付・キッチン・ガードマンなど)の力は欠かせません。
ただし、日本のような「指示すれば動く」という感覚は通用しにくく、スタッフのモチベーションや文化的背景を尊重しながら運営する必要があります。
-
「家族が第一」という文化に基づいた休暇調整
-
フィリピン流の“言いにくいことをはっきり言わない”伝達スタイル
-
給与遅延や待遇への不満が“突然の退職”につながることも
学校経営者にとって、経済的な安定だけでなく「現地チームとの信頼」がなければ継続は難しい現実があります。
5. 予測不能なトラブルへの即応力
セブ島では、インフラ面の不安定さから、突発的なトラブルも珍しくありません。
-
停電・断水: 数時間〜丸1日、学校全体が機能停止
-
天候: 大雨や台風で空港閉鎖・授業中止
-
感染症: デング熱・食中毒・パンデミック対応
-
政治・行政: ビザ要件や税制度の急な変更
-
文化ギャップ: 生徒同士のトラブル、価値観の衝突
こうした事態に備えるには、マニュアル化と柔軟な意思決定が欠かせません。特にパンデミックを経た今、多くの学校が医療提携やオンライン対応の体制を強化しています。
経営者に求められる資質とは?
ここまで見てきた通り、フィリピンで語学学校を運営するには、教育業のスキルだけでなく、経営、法務、人事、危機管理、異文化理解など、複合的な能力が求められます。
加えて、次のような資質があれば理想的です:
-
「想定外」を楽しめる柔軟さ
-
現場に立ち続ける行動力
-
目先の利益よりも“信頼”を重視する長期視点
-
文化の違いをリスペクトする姿勢
セブ島の語学学校が直面してきた大きな波
この10年あまり、セブ島の語学学校業界は急成長と混乱、そして再構築という大きな波を経験してきました。語学留学というマーケットの中でも、これほど急激に変化し続けている地域は珍しいかもしれません。
それぞれのフェーズを振り返ることで、今、そしてこれから語学学校を運営することの意味が見えてきます。
● 2010年代:日本・韓国を中心とした“セブ留学バブル”の時代
2010年代前半、フィリピン留学は「コスパ最強の英語学習法」として急速に広まりました。韓国が先行し、日本が追随。1週間〜3か月という短期留学が一般化し、セブ島には次々と新しい語学学校が誕生しました。
とくに「マンツーマン授業」という強みは、欧米留学との差別化要素として圧倒的でした。小さな学校がビジネスチャンスをつかみ、校舎を拡大し、ピーク時には100校を超える語学学校がしのぎを削っていたといわれています。
しかしその裏では、以下のような問題も表面化していました:
-
講師の引き抜き合戦による人件費の高騰
-
価格競争によるサービス品質の低下
-
一部業者による強引なマーケティングや詐欺まがいの勧誘
-
政府の規制強化(TESDA登録義務化、SSPの厳格化など)
“拡大の時代”は、同時に“淘汰の予兆”も孕んでいたのです。
● 2020〜2022年:コロナによる突然のストップと“ゼロ化”
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大はセブ島の語学学校業界を直撃しました。国境が閉ざされ、留学生は帰国を余儀なくされ、予約は全キャンセル、授業も寮もすべてストップ。何百人もの講師やスタッフが職を失いました。
多くの学校が休校あるいは閉校し、再開の目処すら立たない状況が長く続きました。
-
オンライン授業への切り替えに乗り遅れる学校
-
校舎を売却・賃貸解消するケースも続出
-
フィリピン政府による出入国・隔離の頻繁なルール変更
-
講師・運営スタッフの流出(他業種への転職・海外就職など)
この時期、多くの学校経営者が一度「学校を畳む」という選択を考えたはずです。長年積み上げてきた運営ノウハウが空白となり、「0からの再出発」を迫られる転機でした。
● 2023年以降:再構築の時代と“多国籍化”という新しい流れ
2023年になると、フィリピン政府は入国制限を緩和し、語学学校業界も少しずつ再起動し始めます。しかし、コロナ以前と同じモデルでは立ち行かないことが明らかになりました。
市場は一度リセットされ、以下のような「新しい動き」が目立つようになります:
-
日本や韓国に加え、台湾・ベトナム・モンゴル・中東・アフリカからの学生が増加
-
大規模校よりも少人数・特化型の小規模校に人気が集まる傾向
-
ChatGPTやAI教材の活用など、教育テックを取り入れた学校も登場
-
社会人や30代以降のリスキリング層による「学び直し」需要の拡大
-
ビジネス英語やIELTS対策など、目的別にカリキュラムを絞る戦略
再開後のセブ島は、かつての“語学留学バブル”の焼き直しではなく、「必要な人に届く教育サービスを届ける」という本質的な価値に回帰しつつあるようにも見えます。
● 続けるには「柔軟性」と「信頼の積み重ね」が必要
このように、セブ島の語学学校業界はたった10年で3つの時代を経験しています。
-
急成長と混乱の“バブル期”
-
完全停止の“崩壊期”
-
再編と多様化の“再生期”
こうした環境で語学学校を運営し続けるには、「語学力」や「教えるスキル」以上に、経営者としての視点、柔軟な判断力、そして現地スタッフ・生徒との信頼関係が重要です。
市場が成熟した今、生き残っている学校の多くは、“数ではなく質”を追求する方針に舵を切っていることが共通点です。派手な宣伝ではなく、地道な教育改善、誠実なサポート体制、そして“誰のための学校か”という理念に立ち返った学校だけが、再び信頼を取り戻し始めています。
なぜそれでも続ける価値があるのか?
ここまでに紹介してきたように、セブ島で語学学校を運営するというのは、思っている以上に大変なことです。法制度、文化の違い、スタッフのマネジメント、予期せぬトラブル、そしてパンデミックのような外的要因──どれを取っても日本国内の教育事業とはまったく違う性質を持っています。
それでも、10年以上にわたって語学学校を運営し続けている経営者たちがいます。むしろ、この厳しい環境だからこそ続ける意味があると語る人も少なくありません。
このセクションでは、フィリピン・セブ島で語学学校を続けることの“価値”について、教育、経済、社会、そして個人の視点から掘り下げていきます。
1. 人の人生を変える力がある
語学学校は単なる「英語を教える場所」ではありません。
ときには、海外留学が初めてという学生が、緊張した面持ちで空港に降り立ち、慣れない環境の中で戸惑いながらも、少しずつ英語を話せるようになり、自信を取り戻していく。そんな姿を何度も見てきました。
語学の習得はもちろんですが、それ以上に「異文化の中で自分を試す」という経験が、人の人生観や将来を大きく変えていくのです。
-
留学後に英語を活かして外資系企業に転職した人
-
海外インターンからそのまま現地就職した人
-
英語を武器に起業した人
-
海外との関係が深い職業(国際協力、通訳、外務省など)に進んだ人
一つの語学学校が、そうした「人生の転機」に立ち会えること。これは数字では測れない、何よりも大きな価値です。
2. フィリピン人講師や現地スタッフの人生にも関われる
語学学校の主役は生徒だけではありません。講師やスタッフたちにとっても、安定した職場であり、成長の場でもあります。
フィリピンは学歴社会でありながら、就職口が限られているため、多くの優秀な人材が「英語講師」という職を通じて自立を目指しています。
語学学校がしっかりしたトレーニング制度や昇給制度を持ち、誠実な雇用環境を提供することで、彼ら・彼女らの人生の質も確実に変わっていきます。
-
教育学部出身の新卒講師が、数年でヘッドティーチャーに昇進
-
シングルマザーが英語講師として安定収入を得て子供を大学へ
-
長年の勤務経験を活かして、他国の教育機関でキャリアアップ
これは、フィリピンという国の経済や教育にも、微力ながら貢献している実感を得られる瞬間です。
3. 日本人の「学び方」を変えるきっかけになれる
日本人の英語コンプレックスは根深く、「読む・書く」はできても「話す・聞く」が苦手という人が依然として多くいます。そうした人たちにとって、セブ島のマンツーマン授業は、これまで経験したことのない「実践型英語学習」の入り口になります。
とくに近年では以下のような需要が顕著です:
-
社会人の短期集中留学(1〜2週間でブースト)
-
会社の研修としてのセブ留学導入(法人対応)
-
シニア層の「学び直し」や「海外生活体験」
-
親子留学や中高生の英語強化プログラム
日本の教育制度ではカバーしきれない部分を、セブ島の語学学校が補完する役割を担い始めているのです。
また、近年は**ChatGPTやAIを活用した“新しい学習スタイル”**にも注目が集まっており、こうした技術を現場に組み込んだ教育の最前線として、フィリピンの語学学校は新たな意義を持ち始めています。
4. 多国籍の中で育まれる“国際感覚”
セブ島の語学学校では、日本人だけでなく、韓国、台湾、モンゴル、ベトナム、サウジアラビア、UAE、ロシア、ナイジェリアなど、実にさまざまな国から学生が集まっています。
ひとつの教室に複数の国籍の生徒が集まる中で、「英語はツールであり、文化の違いは前提」という姿勢が自然と身につきます。
これは、どんなに英語ができても、日本の中だけではなかなか培えない感覚です。そして学校側もまた、国籍や宗教、言語背景の異なる生徒を受け入れることで、教育のあり方を常に問い直し、アップデートし続ける必要があります。
語学学校を運営するとは、単に英語を教えるのではなく、「異文化の交差点をつくる」営みでもあるのです。
5. 「本気で人と向き合いたい人」ほど向いているビジネス
セブ島で語学学校を運営する価値をひとことで言えば、「人の人生と本気で向き合えるビジネス」であるという点です。
-
迷っている生徒の背中を押す
-
挫折しそうな生徒を励まし支える
-
教える側の講師を育て、成長を喜ぶ
-
文化の壁を越えてスタッフと信頼を築く
効率や合理性だけでは語れない部分が、ここにはたくさんあります。ビジネスとしてのスケールは小さいかもしれませんが、密度の濃い“人生の現場”に立ち会える場所。それがセブ島の語学学校です。
今後のセブ島語学学校ビジネスに必要なこと
現在、セブの語学学校市場は次のフェーズに入っています。競争が成熟した今、求められるのは以下のような方向性です。
-
ターゲットの明確化(社会人特化、試験対策、ジュニアなど)
-
差別化されたカリキュラム(ChatGPT活用、ビジネス英語、実践重視など)
-
国際化と多言語対応(日本語+英語だけでは不十分)
-
安心・安全の体制(医療、門限、通訳サポートなど)
もう「ただ安いだけ」では選ばれない時代になりました。学校の“中身”と“体験価値”が求められています。
終わりに:セブ島で学校を運営するということは、人の人生と向き合うこと
セブ島で語学学校を経営することは、単なる“ビジネスの選択”ではありません。それは、日々変わる人と向き合い、現地に根を張りながら、教育という長期的な価値を届け続ける行為です。
これから語学学校を始めようと考えている方、あるいは教育事業に関心のある方にとって、本記事が少しでもヒントになれば幸いです。
今後のセブ島語学学校ビジネスに必要なこと
2023年以降、セブ島の語学学校業界は「再編と再構築」のフェーズに入りました。過去のような“量”の競争から、今は“質”と“特色”を磨き抜いた学校だけが選ばれる時代になりつつあります。
では、これからのセブ島語学学校ビジネスにおいて、どんな戦略・視点・体制が求められるのでしょうか?
ここでは、今後の運営に不可欠な5つのキーワードを中心に解説します。
1. 「ターゲットの明確化」──万人向けは、誰にも刺さらない
コロナ前までは「誰でもウェルカム」という総合型の語学学校が多く存在していました。しかし、市場の成熟とともに、“誰のための学校なのか”を明確にした学校ほど評価される傾向に変わっています。
たとえば以下のような特化パターンです:
-
社会人特化: ビジネス英語、プレゼン、英文メール、面接対策など
-
試験特化: IELTS/TOEICスコアアップ、目標点数保証など
-
親子留学対応: 保護者と子どもで生活・学習サポート
-
ミドル・シニア層: ゆるやかな生活と英語体験
-
アフリカ/中東向け: 英語圏ではない新興国の教育需要に応える
いまや「日本人向けの一般英語コース」だけでは、差別化が難しくなっています。自校が「誰に、何を、どの方法で」届けるのか──この軸が明確であればあるほど、ファンもリピーターもつきやすくなります。
2. 「カリキュラムの独自性と実用性」──内容で選ばれる時代へ
以前は「とにかくマンツーマン授業が多い」ことが売りになっていましたが、現在ではそれは“当たり前”。選ばれる理由になるには、以下のような工夫が不可欠です。
例:カリキュラム差別化の要素
-
ChatGPTやAIツールとの併用学習(事前学習やライティング添削)
-
ロールプレイやプレゼンテーションの実践型授業
-
英語×専門領域(医療、観光、ITなど)に踏み込んだ内容
-
自習時間のマネジメント・課題提出・コーチング支援
今や「学習そのもの」よりも、「どう学ぶか」「どこでアウトプットするか」の設計が問われています。
“教える”だけでなく、“使わせる”という視点が、語学学校のカリキュラムにも求められています。
3. 「安心・安全への徹底配慮」──治安・医療・生活面も評価対象に
2020年以降、安全性や医療対応への意識が飛躍的に高まりました。
とくに初めて海外に出る学生や、家族を預ける保護者にとって、「英語力が伸びるか」よりも「安全かどうか」のほうが重要視されるケースもあります。
語学学校が提供すべき安心体制の例:
-
校内・寮内の24時間ガードマン体制
-
定期的な訪問医療、緊急時の病院同行サポート
-
門限・外出ルールの明文化(とくに未成年対応)
-
寮内の掃除・洗濯・Wi-Fi整備とトラブル対応フロー
-
多言語対応の生活案内マニュアル(日本語・英語・母語)
日本人だけでなく、多国籍生徒に対応するためには、**“多文化の安心”**をデザインすることが求められます。
4. 「多国籍化への適応」──日本人だけを相手にしない発想
かつては日本・韓国が中心だったセブ留学も、近年はモンゴル・台湾・ベトナム・中東・アフリカ諸国と、国籍の幅が大きく広がっています。
これにより、以下のような変化が起きています:
-
日本人同士で固まりがちな環境が、英語を使わざるを得ない状況に変化
-
ハラル対応・食事制限・祈祷スペースなど、宗教的配慮の必要性
-
多様な英語レベル・学習背景を持つ学生への個別対応力
今後さらに成長が見込まれるのは、英語を第一言語としない新興国からの留学層です。競合が少ない中で信頼を築けば、安定したリピート・紹介も期待できます。
5. 「教育ビジネスとしての継続性と利益設計」
語学学校をビジネスとして成立させるには、教育の質と同じくらい、収益構造の明確化も不可欠です。
とくに、以下のようなポイントが見落とされがちです。
-
為替リスクの対策(ペソと円/ドルの変動)
-
現地費用の徴収方法(ペソ現金?日本円?カード?)
-
高インフレ・最低賃金上昇への対応(2025年現在も継続中)
-
ハイシーズンとローシーズンの需給調整(時期別料金など)
-
土日・短期対応、空港送迎などのオプション設計
価格競争に陥らず、適正価格×高満足度を実現するには、利益率ではなく「価値ベース」でサービス設計する必要があります。
まとめ:これからは「教育×人間力×テクノロジー」
セブ島の語学学校は、新たな時代に入りました。もはや、授業数や価格で勝負するだけの時代ではありません。
-
教育としての本質を見つめること
-
多様な人と本気で向き合うこと
-
テクノロジーを恐れず活かすこと
この3つの軸を持った学校こそが、次の10年を生き残るといえるでしょう。
終わりに:セブ島で学校を運営するということは、人の人生と向き合うこと
フィリピン・セブ島で語学学校を運営することは、単なるビジネスではありません。
それは「人と本気で向き合う営み」であり、同時に自分自身のあり方を常に問い直される日々でもあります。
学校は、建物でも、カリキュラムでも、料金表でもありません。
それらを動かし、支えているのは「人」であり、その一人ひとりの思い、成長、葛藤、挑戦が積み重なって、学校という“場”がつくられているのです。
留学生と向き合うということ
英語を学びにくる学生たちは、単に英語力を上げたいから来るわけではありません。
彼らは「変わりたい」と思って来るのです。
-
転職したい
-
海外で働きたい
-
留学経験を将来に活かしたい
-
自分に自信を持ちたい
-
人生の停滞感を打破したい
そのような想いを持った学生と向き合うとき、語学学校の役割は「英語を教える」だけでは足りません。彼らの背景を知り、不安に耳を傾け、時には一歩踏み込んだアドバイスをする。そうした人間的な関わりが、何よりも記憶に残るのです。
講師やスタッフと向き合うということ
学校の裏側を支えている講師やスタッフも、また人生の転機を迎えています。
貧しい家庭から大学を出て、初めて安定収入を得た若者。家族を支えながら働くシングルマザー。将来は海外で働きたいという夢を持つ講師。
そうした彼ら・彼女らに対して、適切な給与と労働環境を提供することはもちろん、**教育機関として“育てる責任”**も求められます。
定期的な研修、成果に応じた昇給、信頼に基づいたマネジメント――
彼らの人生の一部として、この学校が意味を持てるように。
そんな気持ちで接している学校経営者は、実はとても多いのです。
自分自身と向き合うということ
海外で語学学校を運営するというのは、自分自身が常に問われ続ける仕事でもあります。
文化の違い、法律の壁、予期せぬトラブル、経営上の葛藤──その一つひとつにどう向き合うかは、他人のせいにはできません。
-
日本式の常識は通じない
-
正解のない決断を毎日迫られる
-
言葉では伝えきれない感情が飛び交う
その中で、「自分はなぜこの仕事をやっているのか?」という原点に何度も立ち返ることになります。
それでも続けたいと思えるのは、目の前にいる“誰か”の変化を目撃できるからです。
今日も一人の生徒が、「昨日よりも話せるようになった」と笑う姿を見るたびに、
昨日より少し自信をつけた講師が、堂々と授業をする姿を見るたびに、
「やっぱり、やっていてよかった」と思えるのです。
セブ島という“挑戦の地”で
セブ島は、ビジネスにとって決してイージーな場所ではありません。
インフラは不安定で、文化的ギャップは深く、商習慣も読めない。
だからこそ、ここには“試される場”としての価値があるのだと思います。
教室があり、生徒が集い、講師が教え、スタッフが支える。
その日常の積み重ねが、「学校」という形をとって、
人の人生に働きかけるエネルギーとなっている。
セブ島で語学学校を運営するということは、
教育ビジネスという枠を超えて、
“人と人の出会いと成長をつなぐ場所”をつくり続けることなのです。
最後に
これからセブ島で語学学校を始めようと思っている方へ。
続けるのは簡単ではありません。想像以上に“地味な仕事”です。
でも、本気で人と向き合える人にとって、これ以上やりがいのある仕事もなかなかないと思います。
あなたの想いや覚悟が、いつか誰かの人生を変えるかもしれません。
そして、その誰かは、あなた自身でもあるのです。