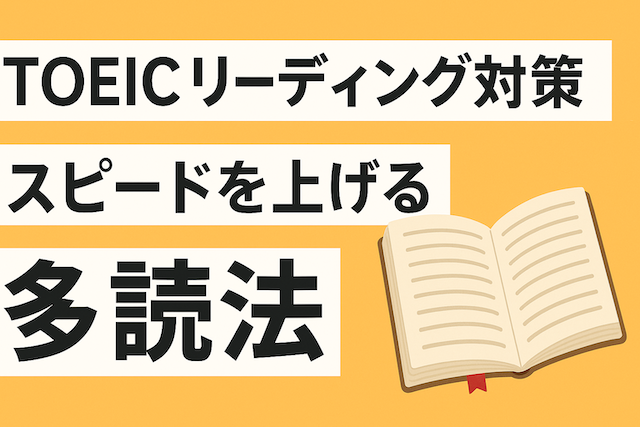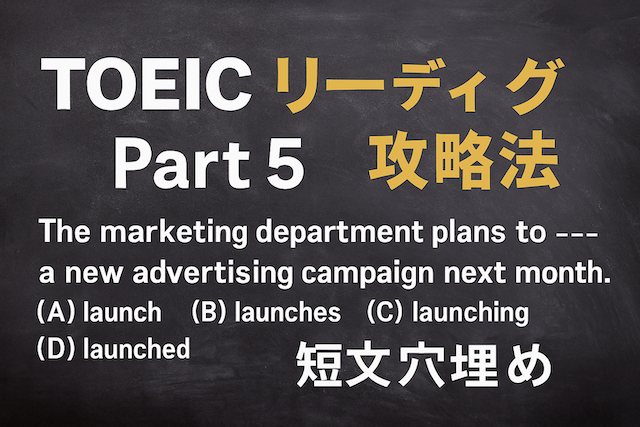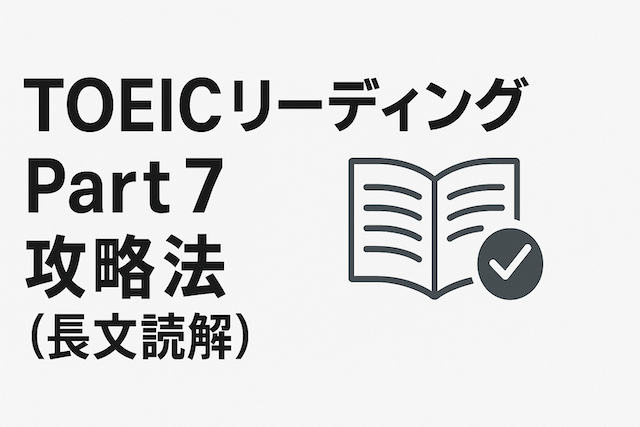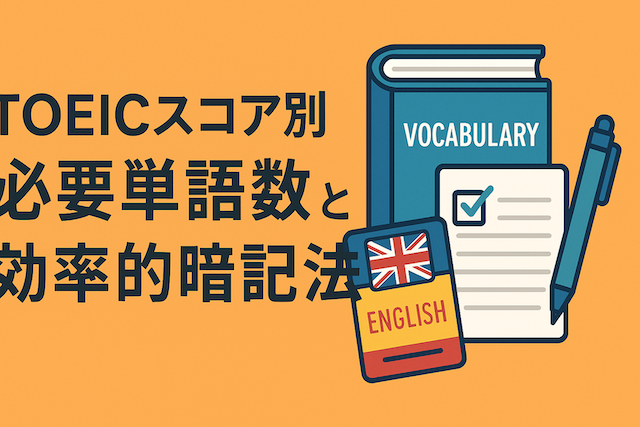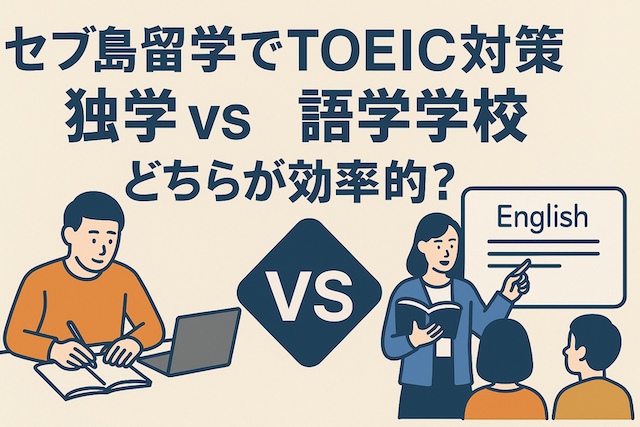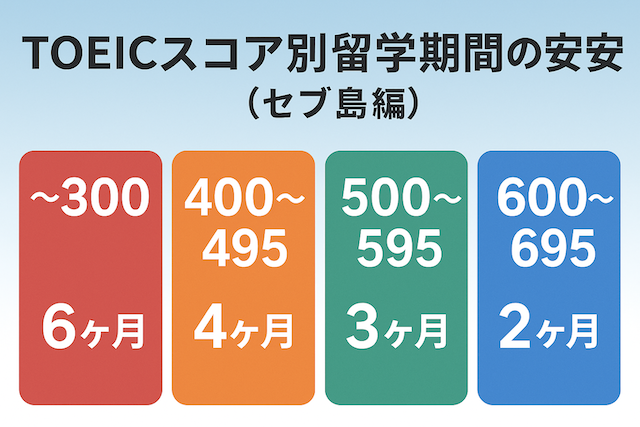目次
- TOEICリーディング対策 スピードを上げる多読法
- はじめに
- TOEICリーディングでスピードが求められる理由
- 多読の基本ルール
- 多読で使う素材の選び方
- 多読の効果を高める実践ステップ
- TOEICリーディングと多読の関係
- 多読を続けるコツ
- まとめ
- FAQ:TOEICリーディング対策 スピードを上げる多読法
- 多読は1日にどれくらい読めばいい?
- 多読中に辞書は使っていい?
- 教材レベルはどう選ぶ?
- おすすめのジャンルは?
- 多読と精読の比率は?
- Part 7の時間不足にどう効く?
- わからない単語に出会ったら?
- 音読はやったほうがいい?
- 進捗はどう記録する?
- 目標WPM(1分間当たり語数)の目安は?
- 効果が出るまでどれくらい?
- 多読だけで十分? 模試は必要?
- 返り読み(逆戻り)を減らすコツは?
- 忙しくて読めない日が続いたら?
- 英英辞典は使うべき?
- スマホでも効果は出る?
- 1日の目標が達成できないときの代替案は?
- 多読素材はどのくらいでレベルを上げる?
- 多読の成果をPart 5/6にも生かすには?
TOEICリーディング対策 スピードを上げる多読法
はじめに
TOEICリーディングで「時間が足りない…」と感じたことはありませんか?
特にPart 7の長文読解では、多くの受験者が最後まで解き切れずに終わってしまうことがあります。実際、リーディングセクションでは75分で100問を解かなければならず、単純計算すると1問に使える時間はわずか45秒ほどしかありません。語彙力や文法知識があっても、読むスピードが足りなければ正解を導く前に時間切れになってしまうのです。
そこで有効なトレーニングが「多読」です。多読とは、辞書を引かずに大量の英文を読み、英語を「頭からそのまま理解する」力を鍛える方法です。大量に読み進めることで自然と読解スピードが上がり、TOEIC本番でも焦らずに問題を処理できるようになります。
この記事では、TOEICリーディングでスピードを上げるための多読法を具体的に解説します。基本的なルールから、教材の選び方、実践的なステップまで紹介するので、「速く正確に読む力」を身につけたい方はぜひ参考にしてください。
TOEICリーディングでスピードが求められる理由
TOEICのリーディングセクションは、75分で100問を解く構成になっています。つまり、1問にかけられる時間は平均で約45秒しかありません。さらにPart 7では1問ごとに短文を読むのではなく、長文メールや記事、複数文書を読み比べる設問が出題されるため、実際には1問に30秒前後しか割けないケースも少なくありません。
また、リーディング問題は「情報処理スピード」が合否を分ける大きなポイントになります。文法や語彙の知識があっても、英文を頭から順に理解できなければ解答時間が足りなくなるのです。特に次のような課題を抱える受験者が多いです。
-
精読に時間をかけすぎる:一文一文を細かく訳してしまい、全体の理解に時間がかかる。
-
単語の意味が分からず止まる:知らない単語に出会うと手が止まり、リズムを失う。
-
読むスピードが安定しない:内容が難しいと極端にペースが落ちる。
TOEICでハイスコアを狙うには、正確さだけでなく「時間内に解き切る」力が欠かせません。そのために有効なのが、辞書を使わずに大量の英文を読み進める「多読トレーニング」です。多読を通じて、英文を日本語に訳さずに理解できる力が育ち、読解スピードを飛躍的に高めることができます。
多読の基本ルール
多読は「速く読む力」を身につけるのに効果的ですが、正しいルールを守って実践しないと効果が半減してしまいます。以下の3つが、多読を続けるうえでの基本ルールです。
1. 辞書を引かずに読む
多読の最大のポイントは「分からない単語があっても止まらない」ことです。逐一辞書を引いてしまうと、読むスピードが落ち、かえって日本語訳に頼るクセがついてしまいます。意味が分からなくても、前後の文脈から推測しながら読み進めましょう。
2. 完璧に理解しようとしない
多読の目的は「内容を大まかに把握するスピードを上げること」です。理解度は70%〜80%で十分です。細かい文法や単語の意味を深掘りするのは精読で行い、多読では「分からない部分を気にせず前に進む」意識を持ちましょう。
3. 毎日少しずつでも継続する
多読は一度に大量に読むよりも、毎日少しずつ続ける方が効果的です。1日15分でも良いので習慣化し、英文に触れる量を積み重ねていくことがリーディングスピード向上の近道になります。
この3つを守ることで「英文を頭からスムーズに処理する力」が育ち、TOEICのリーディングでも時間に余裕を持って解答できるようになります。
多読で使う素材の選び方
効果的な多読を実践するためには、教材選びがとても重要です。難しすぎる素材では途中で挫折してしまい、逆に簡単すぎる素材では成長が止まってしまいます。TOEICリーディング対策に多読を取り入れる場合、以下のポイントを意識して教材を選ぶと効果的です。
1. レベルは「少し易しい」ものから
最初からTOEIC公式問題集やビジネス記事に挑戦すると、理解できない単語や表現が多くて読み進められないことがあります。多読の目的は「止まらずに読むこと」なので、まずは自分のレベルより少し簡単な英文を選びましょう。Graded Readers(レベル別リーダー)や中級者向けニュース記事などがおすすめです。
2. TOEICに近いジャンルを選ぶ
TOEICのリーディングで出題される英文は、ビジネスメール・お知らせ・広告・ニュース記事などが中心です。そのため、多読の素材もこれらに近いジャンルを選ぶと効果的です。英字新聞のビジネス欄や企業のプレスリリース、ニュースアプリの英語版などはTOEIC対策と直結します。
3. 量を意識する
多読は「質より量」が基本です。最初は1日1,000語程度から始め、慣れてきたら2,000語以上を目標にするとスピードが鍛えられます。読む量を記録して「今日はここまで読んだ」と可視化すると、モチベーション維持にもつながります。
正しい教材選びをすることで、多読が「楽しく続けられる習慣」になり、結果的にTOEIC本番のリーディング力強化にも直結します。
多読の効果を高める実践ステップ
多読はただ英文を読むだけでも効果がありますが、工夫を加えることでさらにリーディングスピードを効率よく伸ばせます。以下のステップを意識すると、TOEIC対策としての成果が出やすくなります。
1. 短時間でも毎日読む
1日15分〜20分程度の「短時間リーディング」を習慣にしましょう。長時間まとめて読むよりも、毎日少しずつ続ける方が脳が英語のリズムに慣れ、スピードが安定します。
2. 精読と組み合わせる
多読だけでは理解の浅い部分が残ることもあります。そこで、別の時間に「精読」を取り入れて、文法や語彙を正確に押さえると効果的です。精読で学んだ知識を多読に活かすことで、速さと正確さの両方を鍛えられます。
3. 音読・黙読を使い分ける
黙読だけでなく、時々音読を取り入れるのもおすすめです。音読することで英文のリズムやフレーズの感覚が身につき、結果的に黙読スピードも速くなります。特にニュース記事や会話文を音読すると効果的です。
4. 読んだ量と時間を記録する
「今日は何語読んだ」「何分で読み終えた」と記録しておくと、自分の成長が見える化されます。週ごとに振り返るとモチベーションが維持でき、学習習慣が定着しやすくなります。
これらのステップを取り入れることで、多読の効果を最大限に引き出し、TOEIC本番でのリーディングスピード向上につなげることができます。
TOEICリーディングと多読の関係
TOEICリーディングは大きく Part 5(短文穴埋め)・Part 6(長文穴埋め)・Part 7(長文読解) に分かれています。それぞれのパートで求められる力は異なりますが、多読は特にPart 7対策に直結します。
Part 5・6では精読が中心
Part 5や6は文法や語彙の正確な知識が問われるため、基本的には「精読」で細かい理解力を鍛える必要があります。ただし、多読を続けて英文に慣れておくことで、文の流れを早くつかめるようになり、解答スピードが安定します。
Part 7で多読の効果が最大化
Part 7はTOEICリーディングで最も時間を要するパートです。Eメール、記事、広告、チャットログなど多彩な英文が出題されます。多読で「大量の英文を素早く処理する力」を鍛えておくと、本番で文章量に圧倒されずに取り組めます。特に「辞書を引かずに読み進める訓練」が、限られた時間内で内容を理解するスキルに直結します。
本番での相乗効果
精読で得た文法知識と、多読で培った速読力は相互に補完し合います。文法・語彙力をベースにしつつ、多読で英語を頭から理解する習慣を身につければ、TOEIC本番でも 「速さと正確さの両立」 が可能になります。
多読はTOEICリーディングの全体的な読解力を底上げするだけでなく、特にスコアを左右するPart 7で大きな武器になります。
多読を続けるコツ
多読は効果的なトレーニングですが、継続できなければ力は身につきません。英語学習は短期間で劇的に成果が出るものではないため、いかに「続けやすい環境」を作るかがポイントになります。以下のコツを取り入れて、習慣化を目指しましょう。
1. 興味のある分野を読む
自分が関心のあるテーマなら、難しい英文でも「もっと知りたい」という気持ちがモチベーションにつながります。旅行、テクノロジー、スポーツ、ビジネスなど、興味のあるジャンルを中心に選ぶと継続しやすいです。
2. 読んだ量を「見える化」する
アプリやノートを使って、読んだ語数や時間を記録しましょう。「1週間で1万語読んだ」など、成果が数字で見えると達成感が生まれ、続ける原動力になります。
3. 難しすぎる素材を避ける
レベルが高すぎる教材を選ぶと、理解できない部分が多くなり、挫折の原因になります。理解度70〜80%を目安に「ちょっと簡単かも?」と感じる素材を選ぶ方が、多読の効果を最大限に引き出せます。
4. 生活習慣に組み込む
「朝の通勤時間にニュース記事を2本読む」「寝る前に15分だけリーディングする」など、毎日の生活にルーティンとして取り入れると習慣化しやすくなります。
このように工夫しながら多読を継続すれば、TOEICリーディングで求められる速読力が自然と身についていきます。
まとめ
TOEICリーディングは「時間との勝負」と言われるほど、スピードがスコアに直結します。特にPart 7では、英文量の多さに圧倒されて最後まで解き切れない受験者が少なくありません。その弱点を克服するために最適な学習法が「多読」です。
多読の基本は、辞書を使わずに大量の英文を読み進めること。理解度70%でも構わないので、とにかく前に進む習慣を身につけることが大切です。さらに、精読との組み合わせ、音読の活用、読書量の記録などを取り入れれば、効果は一層高まります。
多読を継続することで、英文を頭から理解するスピードが上がり、TOEIC本番でも時間に追われず安定して解答できるようになります。スコアアップを目指すなら、今日から「多読」を学習ルーティンに組み込み、英語を読むスピードと量を積み重ねていきましょう。
FAQ:TOEICリーディング対策 スピードを上げる多読法
多読は1日にどれくらい読めばいい?
初心者〜中級は1,000語から、慣れてきたら2,000語以上を目安に。時間基準なら15〜20分/日でもOK。大切なのは“毎日継続”。
多読中に辞書は使っていい?
基本は使わないのがルール。止まらずに読むことが目的だからです。どうしても気になる語は読了後に3語までなど上限を決めて確認を。
教材レベルはどう選ぶ?
理解度70〜80%を目安に、少し易しい素材から。難しすぎると挫折、簡単すぎると伸びにくいです。
おすすめのジャンルは?
TOEICに近い「ビジネスメール・告知・広告・記事」形式。Graded Readers、英字ニュースのビジネス欄、企業プレスなどが実戦的。
多読と精読の比率は?
目安は多読:精読=7:3。スコアが伸び悩む場合は一時的に精読比率を上げ、基礎を補強。
Part 7の時間不足にどう効く?
多読で「返り読みしない頭からの処理」が習慣化し、段落要点把握と設問スキャンが速くなります。結果的に1問あたりの処理時間が短縮。
わからない単語に出会ったら?
前後の文脈で推測してスルー。固有名詞なら“何者か”程度の理解で十分。頻出して気になる語だけ後で確認。
音読はやったほうがいい?
週数回の音読は有効。チャンク(意味のかたまり)で区切り、リズムと語順処理を鍛えると黙読も速くなります。
進捗はどう記録する?
読了語数と時間をセットで記録。例:1,600語 / 18分 / 記事3本。週単位で合計を可視化すると習慣化しやすいです。
目標WPM(1分間当たり語数)の目安は?
初中級:120–150 WPM、実戦目標:180–220 WPM。まずは安定150 WPM、その後200 WPMを狙いましょう。
効果が出るまでどれくらい?
個人差はありますが、毎日15分×4週間で体感的な読速アップを感じる人が多いです。2〜3か月で安定化。
多読だけで十分? 模試は必要?
多読は土台づくり。実戦力は公式問題集や模試で時間配分を含めて検証しましょう(週1回が目安)。
返り読み(逆戻り)を減らすコツは?
指やカーソルで視線ガイド、チャンクごとに区切って読む、段落ごとに1行要約を頭で作る——で前進読みを固定化。
忙しくて読めない日が続いたら?
「最低5分」や「見出しだけ3本」など超ミニマム目標を設定。ゼロをなくすことが再開の最短ルートです。
英英辞典は使うべき?
多読中は不要。読了後の復習で簡潔な定義を確認する用途なら有効です。意味の“回路”を日本語に戻しすぎないのがポイント。
スマホでも効果は出る?
出ます。通知をオフにし、リーダーモードやオフライン保存を活用。フォントをやや大きめにして視線移動を滑らかに。
1日の目標が達成できないときの代替案は?
語数→時間基準(15分)に切り替える、短文記事を複数本に分割、通勤中に見出しとリードのみを読む等で負荷を調整。
多読素材はどのくらいでレベルを上げる?
理解度が80%超&WPMが安定してきたら、一段階だけ上げる。急激なレベルアップは非推奨。
多読の成果をPart 5/6にも生かすには?
多読で見慣れたコロケーションを精読ノートに取り出し、品詞・文型とセットで整理。処理スピードと正確性が両立します。