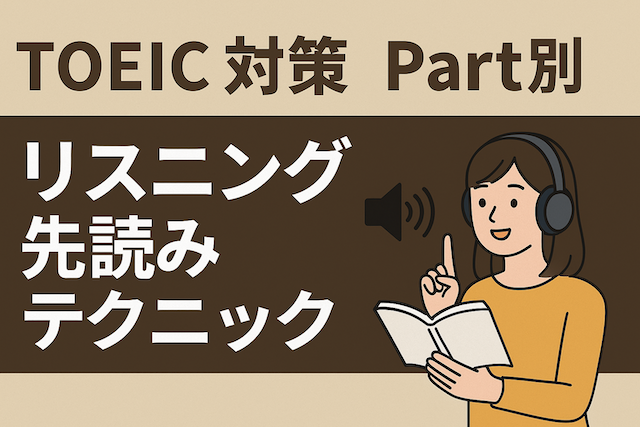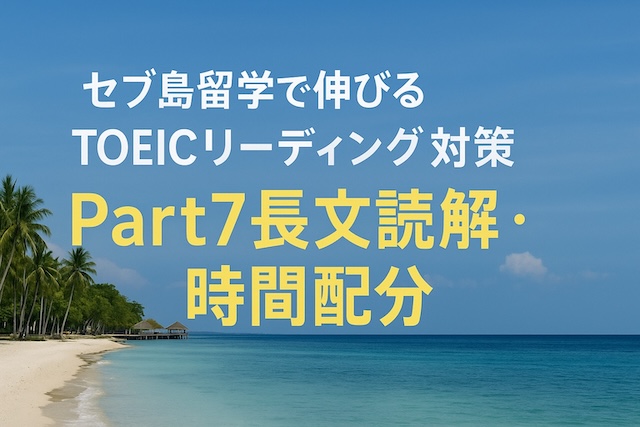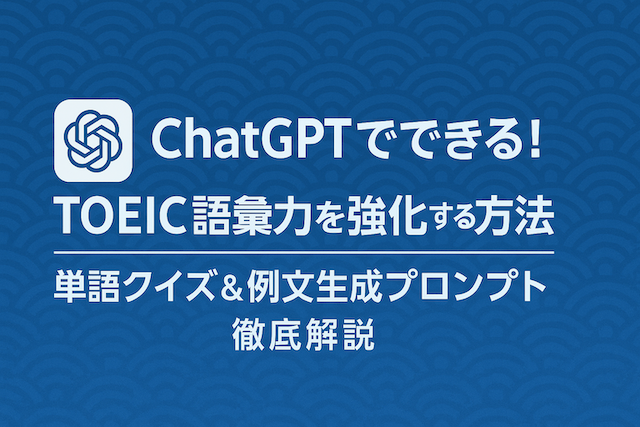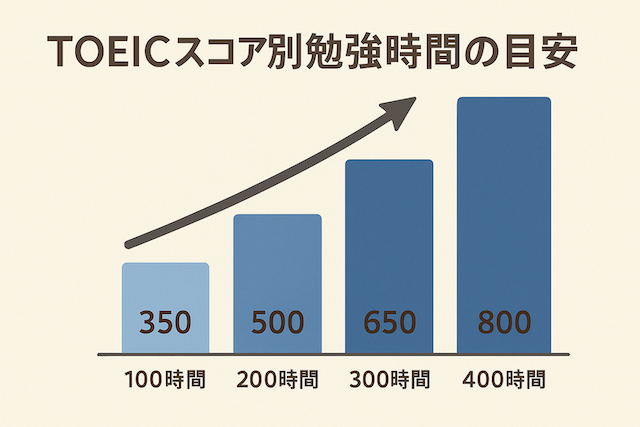目次
- TOEIC対策 Part別リスニング先読みテクニック
- はじめに
- Part 1 写真描写問題:先読みテクニック
- Part 2 応答問題:先読みテクニック
- Part 3 会話問題:先読みテクニック
- Part 4 説明文問題:先読みテクニック
- 先読み時間の配分と実践トレーニング法
- まとめ
- FAQ:TOEIC対策 Part別リスニング先読みテクニック
- 先読みは本当に効果がありますか?初心者にも有効?
- Part別の先読みの基本を一言でまとめると?
- 先読みの最適な時間配分は?
- 設問は選択肢まで細かく読むべき?
- 先読み中に音声が始まって焦れます。どう対処?
- よくある先読みの失敗は?
- 数字・日付問題に弱いです。先読みで強くなれますか?
- Part 2は先読みできないのに、どう準備する?
- 「設問順=音声の流れ」はいつも当てはまる?
- 先読みしながらメモは取るべき?
- 設問が難しくて時間内に3問読めません
- ひっかけ(言い換え)への対策は?
- 先読み練習の具体的メニューは?
- 試験本番、迷ったらどうする?
- 先読みで集中が切れます。持久力の鍛え方は?
- 教材は何を使うと先読み力が伸びますか?
- 先読みと精読のバランスは?
- スコアが伸びないとき、先読み以外で見直す点は?
TOEIC対策 Part別リスニング先読みテクニック
はじめに
TOEICのリスニングセクションは45分間・100問というスピード勝負です。音声は一度しか流れず、聞き逃しがそのまま失点につながるため、多くの受験者が「集中して聞いていたのに答えを選べなかった」という経験をします。
そこで効果を発揮するのが 「先読みテクニック」 です。設問や選択肢を音声が流れる前に確認しておくことで、リスニング中に意識すべきキーワードを絞り込み、正答に直結する情報を効率よくキャッチできます。
ただし、先読みの方法はPartごとに異なります。Part 1・2では写真や出題パターンから動詞や答え方を予測することが中心、Part 3・4では印刷された設問を素早く読み取り会話や説明の流れを先に掴むことがポイントです。
このガイドでは、Part別に最適な先読みのコツ を整理し、スコアアップにつながる具体的な実践方法を紹介していきます。
Part 1 写真描写問題:先読みテクニック
TOEICリスニングの冒頭に出題されるPart 1は、写真を見てその状況を説明する文を選ぶ問題です。短文リスニングで比較的得点源にしやすいセクションですが、油断するとトリックに引っかかることもあります。先読みを活用して正答率を安定させましょう。
先読みのポイント
-
音声が流れる前に 写真をしっかり観察 する。
-
「人物・動作・物・位置関係」の4点を確認しておく。
チェックすべき視点
-
人物
-
男性か女性か、人数は何人か
-
制服や作業着を着ているか → 職業が関係する可能性
-
-
動作
-
座る、立つ、歩く、話す、指す、持つ、使う など動詞を予測
-
静止している動作(looking at, standing, sitting)にも注意
-
-
物・環境
-
写真内の大きな物体(机、パソコン、本、車など)
-
公園、オフィス、街中などシーンの特徴
-
-
位置関係
-
前に、隣に、後ろに、壁のそばに、机の上に など前置詞表現を想定
-
よく出るひっかけパターン
-
存在しないものを述べる
例:写真に花はないのに “Some flowers are on the table.” と言う。 -
似て非なる動作
例:実際は「持っている」なのに「使っている」と言う。 -
状態と動作の取り違え
例:立っているのに “He is walking.” と表現される。
実践テクニック
-
写真を見ながら、頭の中で 3つ以上の英文を作る
(例:The man is sitting at a desk. The woman is holding a pen. Some papers are on the table.) -
動詞を2〜3個予測しておくと、音声が流れたときに照合しやすくなる。
Part 2 応答問題:先読みテクニック
Part 2は短い質問や発言に対して、最も自然な応答を選ぶ形式です。設問が問題冊子に印刷されていないため、Part 1と違って「文字としての先読み」はできません。その代わりに 質問パターンをあらかじめ意識しておくこと が先読みテクニックとなります。
先読みのポイント
-
質問文が流れる前に「どんなタイプの問いが出やすいか」を想定しておく。
-
疑問詞やYes/No質問の答え方をあらかじめシミュレーションする。
よく出る質問パターン
-
疑問詞で始まる質問
-
Who:人名や役職で答える
-
Where:場所(office, station, at homeなど)で答える
-
When:時間・日付で答える
-
Why:理由(because, due to, sinceなど)で答える
-
How:方法・手段・程度で答える
-
-
Yes/No質問
-
Do you〜?, Is it〜?, Can you〜?
-
→ Yes / No で始まらない自然な応答が正解になる場合も多い
-
-
依頼・提案・勧誘表現
-
“Could you open the window?” → “Sure.” や “No problem.”
-
“Why don’t we meet tomorrow?” → “That sounds good.”
-
-
あいまい返答が正解になるケース
-
“I’m not sure.” “Let me check.” “It depends.”
-
ひっかけパターン
-
質問の単語と似た音の単語でミスリードする
(例:trainとdrain、mailとmale) -
Yes/No質問に対して、Yes/Noで始まる不自然な答えを提示
-
質問の意図と関係ない返答を含ませて混乱させる
実践テクニック
-
リスニング直前に「Who, Where, When, Why, How, Yes/No」の6種類を常に頭に置いておく。
-
疑問詞を聞いた瞬間に「答えの方向性」を即座に決める。
例: “Where〜?” → 場所だけ集中。 -
“Would you〜?” “Could you〜?” など依頼表現を聞いたら → 承諾フレーズ を想定。
Part 3 会話問題:先読みテクニック
Part 3は、2人または3人による会話を聞き、その内容に関する設問(1セット3問)に答える形式です。問題冊子に設問が印刷されているため、先読みの効果が最大限に発揮できるパート です。
先読みのポイント
-
音声が始まる前に 3問すべてを一気に読む
-
「何が問われているか」だけを素早く把握する
-
選択肢まで細かく読む必要はなく、設問の方向性を掴むのが目的
チェックすべき設問の種類
-
基本情報系
-
“Where does the conversation take place?”(場所)
-
“Who is the man?”(人物の役割)
-
-
詳細確認系
-
“What will the woman do next?”(次の行動)
-
“What problem are they discussing?”(課題や問題点)
-
-
数字・日付系
-
値段、時刻、日程などは一度聞き逃すと取り戻せない
-
-
意図推測系
-
“What does the man mean when he says…?”
-
直接言っていない意図や気持ちを推測させる問題
-
実践テクニック
-
設問を読む時間は 5〜7秒程度 に抑える
-
3問の順番に沿って会話が進むため、設問の流れ=会話の展開 と意識する
-
1問目で「場所・人物」を押さえると、その後の会話が理解しやすくなる
-
会話中に答えが出たらすぐマークし、余った時間を 次セットの先読み に回す
ひっかけパターン
-
数字の入れ替え(15と50、13と30など)
-
選択肢の言い換え(cheap ⇔ inexpensive, delay ⇔ behind schedule)
-
会話中で複数の選択肢が一見当てはまりそうに聞こえるが、文脈で正解が1つに絞られる
Part 4 説明文問題:先読みテクニック
Part 4は、1人によるアナウンスやスピーチ、広告、留守電メッセージなどを聞き取る形式です。こちらも問題冊子に設問が印刷されているため、先読みで効率的に聞き取る準備をすることが不可欠 です。
先読みのポイント
-
音声が流れる前に 3問すべての設問をざっと読む
-
「話のテーマ」「聞くべき情報(数字・日付・予定など)」を把握しておく
-
会話ではなく一方的な説明なので、情報量が多い点に注意
チェックすべき設問の種類
-
テーマ確認系
-
“What is the talk mainly about?”(主題・ジャンル)
-
“What is the purpose of the announcement?”(目的)
-
-
詳細確認系
-
“What problem is mentioned?”(問題点)
-
“What service is being offered?”(サービス内容)
-
-
数字・時刻・日付系
-
出発時間、締め切り、料金など
-
→ 一度聞き逃すと選択肢から消去できないため要注意
-
-
次の行動系
-
“What are listeners asked to do?”(次の行動や指示)
-
実践テクニック
-
設問先読みは 約7秒以内 を目安に、流れをつかむ程度でOK
-
設問の順番に沿って説明が進むことが多いので、1問目が話のイントロ、2問目が詳細、3問目が結論 という流れを意識する
-
正解の根拠が聞こえたら即マークし、余った時間は次のセットの設問を読む
-
特に 数値・日付 は集中して聞き取り、選択肢と照合する
ひっかけパターン
-
数字の言い換え(twenty-five → a quarter of a hundred)
-
同じ意味の別表現(cancelled ⇔ called off、free ⇔ at no cost)
-
不要な追加情報で注意をそらす(宣伝文句や前置き)
先読み時間の配分と実践トレーニング法
Part別 先読み時間の配分
-
Part 1(写真描写)
→ 写真を 5秒以内 に観察し、「人物・動作・位置」を予測。 -
Part 2(応答問題)
→ 設問が印刷されないため、出題パターンの予測 を常に頭に置く。先読みというより「質問タイプの即時分類」に集中。 -
Part 3(会話問題)
→ 各セットの3問を 5〜7秒で一気に読む。
会話中に答えが出たら即マークし、余った時間を次の設問先読み に回す。 -
Part 4(説明文問題)
→ 設問3問を 7秒程度で読む。数字・日付・場所など「聞き逃せない情報」に印をつける意識。
先読みを効果的に行うための練習法
-
タイマーを使った訓練
-
問題集を解くとき、先読み時間をストップウォッチで計測。
-
5〜7秒以内に3問を読む練習を繰り返す。
-
-
設問の分類トレーニング
-
設問を読んだら即座に「場所/人物/理由/数字/意図」のどれかに分類する。
-
脳内でカテゴリー化すると、音声中で集中すべきポイントが明確になる。
-
-
ディクテーション+先読み練習
-
音声を聞きながらスクリプトを見てディクテーション。
-
その後、設問を先読みして「どの部分が答えの根拠か」を確認。
-
-
シャドーイング+設問意識
-
会話や説明文をシャドーイングしつつ、設問がどこに対応しているか意識。
-
「このフレーズが問われやすい」という感覚をつかむ。
-
試験本番での意識ポイント
-
解答は 迷ったら即マーク → 先読みの時間を確保するため。
-
音声中に「これが答えだ」と思った瞬間に塗る → 記憶に頼らない。
-
設問の順番=音声の流れ という原則を常に頭に置く。
まとめ
TOEICリスニングで安定して高得点を狙うには、先読みで聞き取る準備を整え、音声中は集中して答えを拾う ことが必須です。Partごとに異なる戦略を身につけ、練習で時間配分を体に染み込ませれば、リスニングセクション全体の得点力が大きく向上します。
FAQ:TOEIC対策 Part別リスニング先読みテクニック
先読みは本当に効果がありますか?初心者にも有効?
有効です。音声前に「何が問われるか」を把握できるため、注意の向けどころが明確になります。英語力が高くない段階でも、設問の種類を先に知るだけで聞き取りの負荷が減ります。
Part別の先読みの基本を一言でまとめると?
- Part 1:写真から人物・動作・位置を瞬時に予測
- Part 2:設問本文がないため質問タイプ(Who/Where/When…/依頼)を即分類
- Part 3:各セット3問を5〜7秒でざっと読む(流れ=会話展開)
- Part 4:テーマ+数字・日付・指示を先に意識して聞く
先読みの最適な時間配分は?
目安はセットあたり5〜7秒(Part 3)、7秒前後(Part 4)。写真問題(Part 1)は開始前の数秒で観察、Part 2は「パターン想定」を常時オンにしておきます。
設問は選択肢まで細かく読むべき?
最初の先読みでは設問文のみで方向性を掴み、選択肢はざっと視野に入る程度でOK。音声中に根拠が出たら選択肢を素早く照合します。
先読み中に音声が始まって焦れます。どう対処?
「3問一気読み→音声開始と同時にリスニングへ切り替え」の型を練習で固定化します。読み切れなくても、1問目の方向性だけ掴めていれば十分機能します。
よくある先読みの失敗は?
- 読み込み過ぎ:選択肢の言い換え罠にはまる
- 設問の種類を意識しない:場所か理由か数字か不明のまま聴く
- マークを後回し:根拠を聞いたのに塗らず忘れる
数字・日付問題に弱いです。先読みで強くなれますか?
設問で「数字系だ」と先にタグ付けしておくと、音声中で数字アンテナが立ち、取りこぼしが減ります。時刻(a.m./p.m.)、料金、部屋番号、日付の語彙を事前に固めておくとさらに安定します。
Part 2は先読みできないのに、どう準備する?
質問タイプの即時分類が先読みの代替です。Who/Where/When/Why/How、Yes/No、依頼・提案(Would/Could/Why don’t we…)を聞いた瞬間に答えの方向を固定します。
「設問順=音声の流れ」はいつも当てはまる?
原則として当てはまります(Part 3/4)。例外もありますが、まずはこの原則を活用し、ズレを感じたら柔軟に切り替えましょう。
先読みしながらメモは取るべき?
基本は最小限でOK。数字や固有名詞など記憶保持が難しい情報のみ短くメモ。書き過ぎると音声を逃します。
設問が難しくて時間内に3問読めません
設問のラベリング(場所/人物/理由/数字/意図)だけでも先に決める練習を。全文精読より、方向づけが優先です。
ひっかけ(言い換え)への対策は?
先読みでキーワードの同義語候補を1〜2個想定しておくと耐性が上がります(cheap ⇔ inexpensive、delay ⇔ behind schedule など)。
先読み練習の具体的メニューは?
- タイムトライアル:3問を5〜7秒で読む→音声→即マーク
- 設問分類ドリル:設問を見て1秒でカテゴリ付与
- ディクテ+根拠特定:聞いた後に解答根拠の位置を特定
- シャドーイング:設問との対応箇所を意識しながら音読
試験本番、迷ったらどうする?
即マーク→次セット先読みが鉄則。長考で先読み時間を失うと連鎖的に崩れます。消去法で最有力にチェックを入れ、先へ進みましょう。
先読みで集中が切れます。持久力の鍛え方は?
模試を通しで運用し、先読み→聴解→即マークのルーチンを45分間維持する練習を重ねます。セット間の数秒で姿勢と視線を整えるミクロ休憩も有効です。
教材は何を使うと先読み力が伸びますか?
公式問題集や模試で、設問だけ先読み→音声の手順を繰り返すと実戦感覚が最速で身につきます。数字・図表系に強くなりたい場合は、ニュース聞き取りで日時・金額を抜き出す練習も効果的です。
先読みと精読のバランスは?
先読みは方向づけ、精読は確認。最初は設問のみ→慣れたら必要な選択肢だけ精読、の順で負荷を調整します。
スコアが伸びないとき、先読み以外で見直す点は?
音声そのものの聞き取り力(短文の瞬間処理、弱読、連結音)と、語彙・コロケーション不足がボトルネックのことがあります。先読みと並行して頻出表現の暗記と音の変化の訓練を行いましょう。