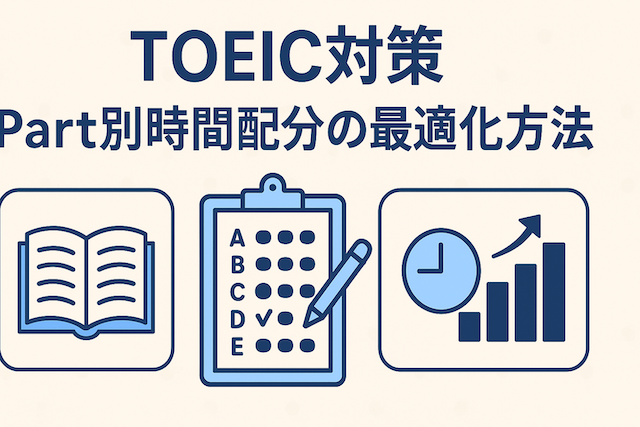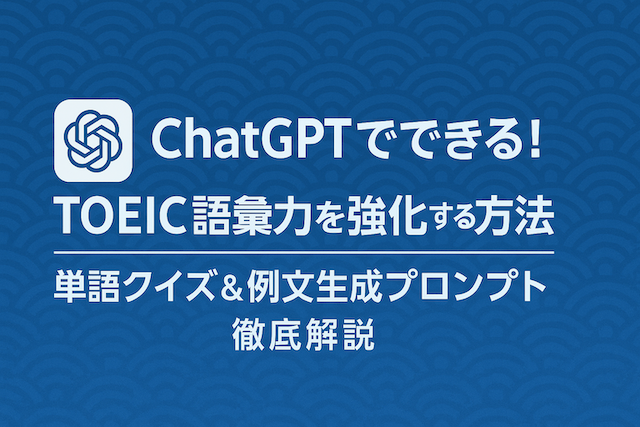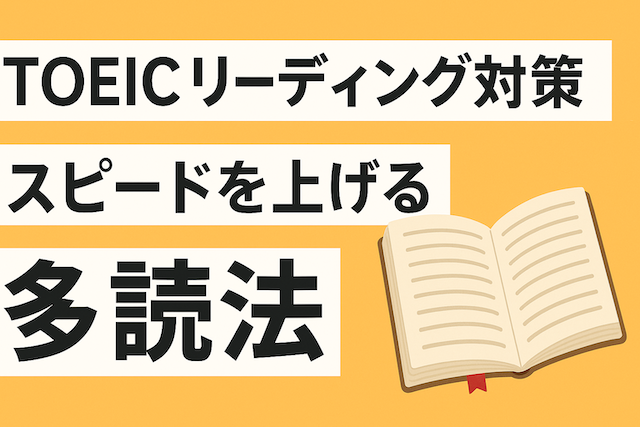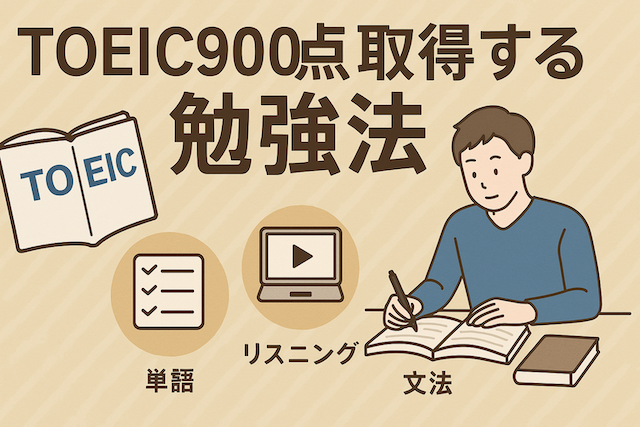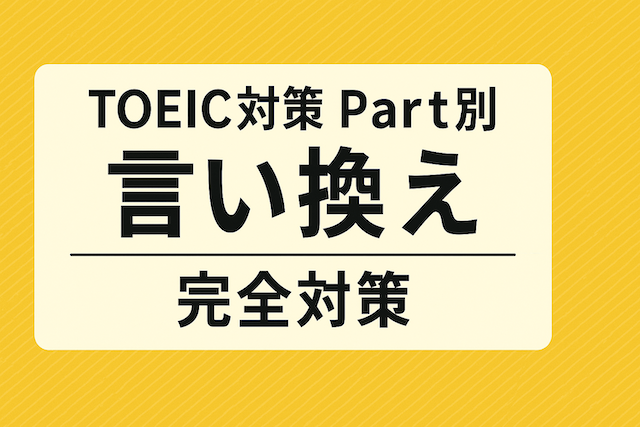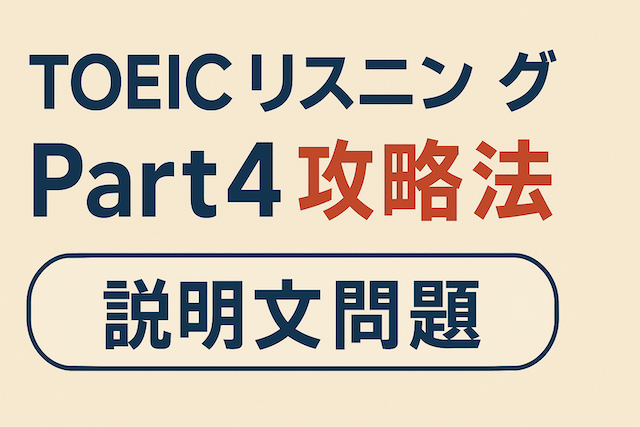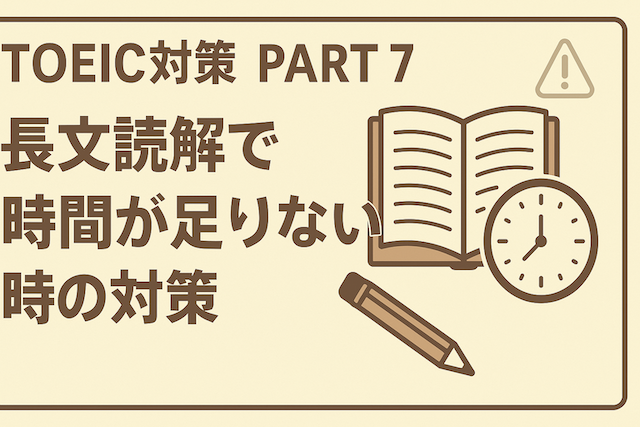目次
- TOEIC対策 Part別時間配分の最適化方法
- はじめに
- TOEIC全体の時間概要
- リスニングセクションの時間感覚
- リーディングセクションの時間配分戦略
- 実践的な時間管理トレーニング
- まとめ
- FAQ:TOEIC対策 Part別時間配分の最適化方法
- TOEICの各Partの最適な時間配分は?
- 時間が押した場合の立て直し方は?
- Part 5を早く正確に解くコツは?
- Part 6で時間がかかる原因と対処は?
- Part 7は全文読むべき?先読みは?
- 先読みはどこまでやる?リスニングの具体例は?
- 見直し時間は確保すべき?どれくらい?
- 難問に粘るべきラインは?
- 語彙が足りないと感じたときの応急対応は?
- リーディングはPartの順番を変えてもいい?
- 練習時のタイマー設定はどうすべき?
- 塗り間違いを防ぐマーク運用は?
- 先読みとメモは試験規定上大丈夫?
- リーディング速度を上げる即効性のある練習は?
- 模試はどれくらいの頻度でやる?
- 本番で緊張して時間感覚が狂うのを防ぐには?
- スコア帯別の時間配分は変えるべき?
- 当日の持ち物や時計は?
TOEIC対策 Part別時間配分の最適化方法
はじめに
TOEICテストは「英語力」だけでなく「時間管理力」も試される試験です。特にリーディングセクションは75分で100問を解かなければならず、多くの受験者が時間不足に陥り、最後のPart 7を解ききれずに悔しい思いをします。
実際、正解できる実力があっても「どのPartにどれくらい時間を使うか」を意識しないと、得点を最大化できません。逆に言えば、効率的な時間配分を習得することで、現状の英語力でも大幅なスコアアップが可能です。
この記事では、TOEIC全体の時間構成を踏まえたうえで、Partごとの最適な時間配分とその実践方法を解説します。模試演習や本番での実用的な戦略として活用できる内容になっていますので、試験直前の調整にも役立ててください。
TOEIC全体の時間概要
TOEICは 合計2時間・200問 のテストです。時間の流れを理解しておくことで、どこに集中すべきかが見えてきます。
リスニングセクション(45分・100問)
-
音声に合わせて進行するため、自分で時間を調整する余地はありません。
-
Part 1からPart 4まで合計45分。途中で止まることはなく、聞き逃しても戻ることはできません。
-
必要なのは「瞬時に理解して選択肢をマークする力」と「集中力の持続」です。
リーディングセクション(75分・100問)
-
自分のペースで解答できる唯一のセクション。
-
文法・語彙の短文穴埋め(Part 5)、長文穴埋め(Part 6)、読解問題(Part 7)の3種類。
-
時間配分の工夫次第でスコアが大きく変わるポイント。
-
特にPart 7は分量が多く、後半に時間切れになる受験者が多い。
まとめると、リスニングでは「先読みと集中力」、リーディングでは「戦略的な時間配分」が鍵となります。
リスニングセクションの時間感覚
リスニングは全100問・約45分。音声に完全に合わせて進むため、受験者自身が「時間を調整する」ことはできません。したがって、Partごとの特徴を理解し、集中力を切らさずに取り組むことが最大の攻略法です。
Part 1(写真描写問題・6問/約3分)
-
問題数は少なく、難易度も比較的低め。
-
ここで確実に正解を重ねることが大切。
-
写真を見て「動作・位置・人物の状況」を素早く把握する練習が有効。
Part 2(応答問題・25問/約8分)
-
質問文に対する自然な返答を選ぶ形式。
-
音声が短く、即答が求められるため集中力を保つことが難しい。
-
「疑問詞 → 答え方」「Yes/Noでは答えられない質問」など、典型パターンを覚えておくと有利。
Part 3(会話問題・39問/約17分)
-
2〜3人の会話を聞き取り、設問に答える形式。
-
設問を先読みしておくことで、必要な情報を聞き逃さずに済む。
-
メモを取らなくても「キーワードの把握」「選択肢の消去法」で十分対応可能。
Part 4(説明文問題・30問/約17分)
-
アナウンスやスピーチなど1人の話を聞く形式。
-
Part 3と同様に先読みが必須。
-
「数字・日付・場所」といった情報は正答に直結しやすいため特に注意。
リスニングでは「配分の調整」よりも、先読み・集中・切り替えが最大のカギ。聞き逃しても立ち止まらず、次の問題へ気持ちを切り替えることが高得点につながります。
リーディングセクションの時間配分戦略
リーディングは 75分で100問 を解く必要があり、多くの受験者が「最後まで解ききれない」という課題を抱えています。Partごとに時間の目安を持ち、計画的に進めることが高得点のカギです。
Part 5(短文穴埋め・30問)
-
目安時間:10分(1問20秒)
-
特徴:文法・語彙の基礎力を問う短問形式。
-
ポイント:
-
短い文章なので長考は不要。
-
知識で即答できる問題が多いため、迷ったら印をつけて後回しにする。
-
最低でも25問以上を素早く正確に解答する意識を持つ。
-
Part 6(長文穴埋め・16問)
-
目安時間:8分(1問30秒)
-
特徴:長文の流れを理解しながら空所を埋める問題。
-
ポイント:
-
文全体の意味を意識して読む。
-
文法だけでなく「接続詞」「文脈上の一貫性」に注目。
-
文章の前後を軽く確認してから解答すると精度が上がる。
-
Part 7(読解問題・54問)
-
目安時間:57分
-
シングルパッセージ(29問):約20分
-
ダブルパッセージ(10問):約12分
-
トリプルパッセージ(15問):約25分
-
-
特徴:量が多く、時間不足の最大の原因になるパート。
-
ポイント:
-
設問を先に読む → 必要な箇所を効率よく探す。
-
全文を丁寧に読むのではなく、「答えがある部分」をピンポイントで確認。
-
難しい問題に固執せず、まずは解ける問題を優先。
-
リーディングでは「Part 5・6を短時間で突破 → Part 7に時間を残す」の流れを徹底することが最適解です。
実践的な時間管理トレーニング
時間配分を「頭で理解する」だけでは不十分です。実際の試験環境を想定し、身体に時間感覚を染み込ませる練習が必要です。以下のトレーニングを取り入れることで、本番でも安定したパフォーマンスを発揮できます。
1. 模試を使ったシミュレーション
-
公式問題集や模試を使い、必ずストップウォッチをセットして解く。
-
本番と同じ 2時間通し練習 を定期的に行うと、集中力の持続力も鍛えられる。
2. 「1問にかける秒数」を意識
-
Part 5:1問20秒以内
-
Part 6:1問30秒以内
-
Part 7:設問1つにつき60〜70秒以内
秒単位での「感覚」を持つと、試験中に焦らずリズムを保てる。
3. 優先順位をつける習慣
-
難問にこだわらず、解ける問題から確実に得点。
-
迷った問題はマークだけして飛ばし、後半に時間が残れば戻る。
4. マーク時間を確保する
-
最後に 最低1〜2分 を見直し用に残す。
-
マークシートのずれや記入漏れは「努力ゼロ点」につながるため、必ず確認する。
5. 部分練習も取り入れる
-
「今日はPart 5だけ10分で解き切る」など、セクションごとに時間制限をつけて訓練。
-
部分練習で時間管理を磨き、模試で総合調整するのが効率的。
時間配分は「計画」だけでなく「実戦感覚」が重要。日頃から制限時間を意識した練習を繰り返すことで、本番で自然にリズムを保ちながら解答できるようになります。
まとめ
TOEICは単なる英語力の試験ではなく、時間をいかにコントロールできるかがスコアを左右する試験です。
-
リスニング:時間配分は調整できないため、重要なのは「先読み」「集中力の維持」「切り替え」。
-
リーディング:75分の中で、Part 5を約10分・Part 6を約8分に抑え、Part 7に十分な時間を残すことが鍵。
-
時間管理トレーニング:模試を使ったシミュレーションや秒単位の意識、マーク時間の確保がスコア安定につながる。
効率的な時間配分を身につけることで、今の英語力を最大限に発揮でき、安定してスコアを伸ばすことが可能です。試験直前に戦略を変えるのではなく、日々の練習から時間感覚を磨くことを意識しましょう。
「時間を制する者がTOEICを制する」。
次回の模試から、ぜひこの記事で紹介した時間配分を試してみてください。
FAQ:TOEIC対策 Part別時間配分の最適化方法
TOEICの各Partの最適な時間配分は?
リーディング75分の目安は以下です。
- Part 5(30問):約10分(1問20秒)
- Part 6(16問):約8分(1問30秒)
- Part 7(54問):約57分(シングル約20分/ダブル約12分/トリプル約25分)
リスニングは音声進行(約45分)のため、時間配分の調整はできません。先読みと集中維持が鍵です。
時間が押した場合の立て直し方は?
- そのPartで取り返さない:残りのPartで巻き返す前提に切り替える。
- 飛ばす基準を決める:固有名詞・推論が重い設問を一時スキップ。
- マークだけ先に:戻る印を付け、最後の見直しで再挑戦。
Part 5を早く正確に解くコツは?
- 設問タイプごとに即断ルール(品詞・時制・前置詞・語彙)を決める。
- 読まずに解ける問題は全文読解を省く。
- 20秒超過で一旦保留→後回し。
Part 6で時間がかかる原因と対処は?
- 原因:文脈確認の過読、挿入文選択で迷走。
- 対処:段落の目的(依頼・通知・案内)を先に把握→空所前後2文を主に確認。
- 挿入文は「接続・指示語・一致(時制・数)」の3点で迅速に照合。
Part 7は全文読むべき?先読みは?
全文精読は不要です。設問先読み→該当箇所探索→必要部分のみ精読が基本。推論問題は根拠の文を2か所以上で裏取りします。
先読みはどこまでやる?リスニングの具体例は?
- Part 3/4:設問を3問分先読みし、キーワード(数字・日付・場所・目的)に下線。
- 選択肢はすべて読まず、紛らわしい語を1つだけメモ。
見直し時間は確保すべき?どれくらい?
最低1〜2分。マーク漏れ・番号ずれの確認を最優先。内容の再検討は「飛ばし印」がある問題から。
難問に粘るべきラインは?
Part 5/6は30秒(上限90秒)を越えたら一度離脱。Part 7は1設問70秒を目安に、根拠が見つからなければ仮マーク→戻る。
語彙が足りないと感じたときの応急対応は?
- 文法・論理手掛かり(接続詞、代名詞の照応、同義言い換え)で消去。
- 図表・件名・日時など非文章情報から当たりを付ける。
- 未知語は前後の肯否関係(however, therefore 等)で意味域を推測。
リーディングはPartの順番を変えてもいい?
原則は5→6→7でOK。読む体力に不安がある場合は、7(シングル)→5→6→7(ダブル・トリプル)など、自分の得点源を先に処理する戦略も有効です。
練習時のタイマー設定はどうすべき?
- 通し練習:2時間固定(本番再現)。
- 部分練習:Part 5は10分、Part 6は8分、Part 7はセット単位(シングル20分等)。
- 「残り時間アラート」を2回(中間・終了5分前)に設定。
塗り間違いを防ぐマーク運用は?
- 1問ごとにマークする方式を基本にし、セットまたぎでは絶対に溜めない。
- ページ切替時に番号を声に出さず視線で確認する「二重チェック」を習慣化。
先読みとメモは試験規定上大丈夫?
問題冊子へのメモは一般的に許容されますが、持ち込み物・筆記具・時計などの規定は会場・実施団体で異なる場合があります。必ず受験票・公式案内の最新ルールを事前確認してください。
リーディング速度を上げる即効性のある練習は?
- チャンク読み:語単位でなく語句塊で目を運ぶ。
- スキャニング訓練:数字・固有名詞・日時だけを素早く拾う練習。
- 言い換えペア暗記:設問と本文で頻出の同義表現をセットで覚える。
模試はどれくらいの頻度でやる?
直前期は週2〜3回の通し+日次で部分練習が目安。復習は誤答原因(語彙/文法/推論/時間)をタグ付けし、翌練習で同カテゴリを重点補強します。
本番で緊張して時間感覚が狂うのを防ぐには?
- 開始直後にチェックポイント時刻(Part 5終了、Part 6終了)を問題冊子の余白にメモ。
- 各Partの最初の2問は「肩慣らし」— 難化していても深追いしない。
- ミス後は3呼吸リセットで次問に切り替える。
スコア帯別の時間配分は変えるべき?
- 〜600点:Part 5/6で取りこぼし削減(配分は目安通り)。
- 700〜800点:Part 7のシングル精度を優先し、難問は潔くパス。
- 900点目標:Part 5を8〜9分に短縮し、トリプルに時間を投資。
当日の持ち物や時計は?
持ち込み可否(腕時計・予備鉛筆・消しゴム等)は実施団体の最新案内に従ってください。スマート機能付きデバイスは不可の場合が一般的です。必ず事前確認を。