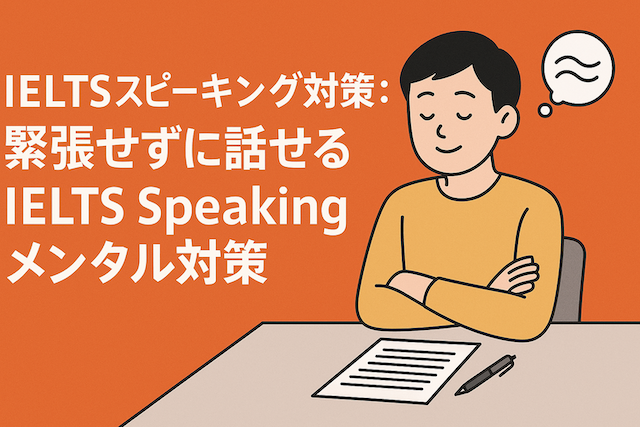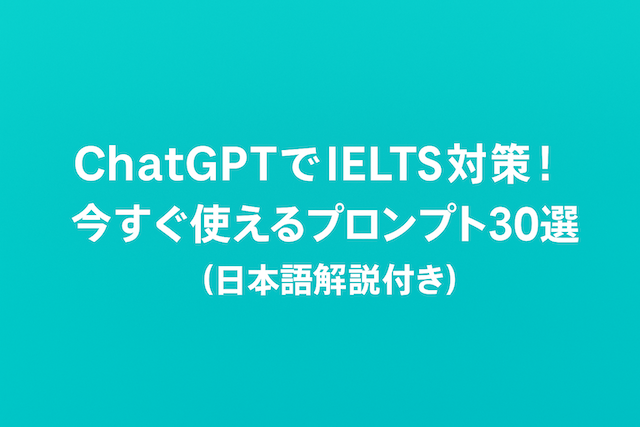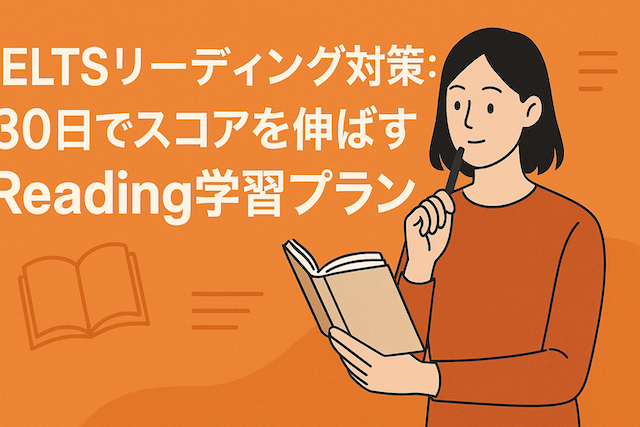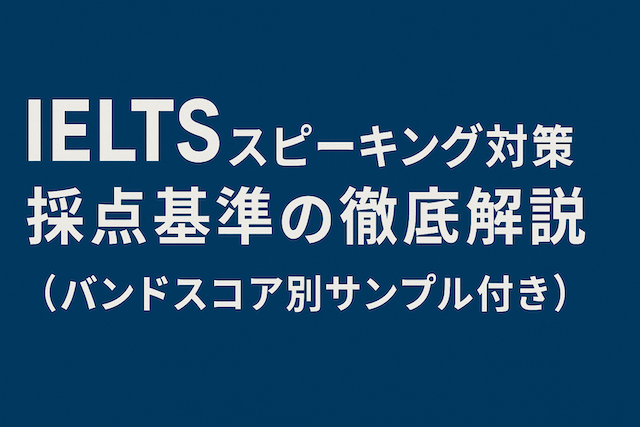目次
- IELTS受験総合ガイド: 試験形式と各セクション概要
- はじめに
- IELTSの試験形式
- Listening(リスニング)
- Reading(リーディング)
- Writing(ライティング)
- Speaking(スピーキング)
- まとめ
- IELTSとは何のための試験ですか?
- AcademicとGeneral Trainingの違いは何ですか?
- 試験全体の所要時間と受験の流れは?
- 紙ベースとコンピュータ試験の違いは?
- Listeningセクションの構成は?
- Readingセクションの違い(Academic/General)は?
- Writingは何を求められますか?
- Speakingの進み方は?
- スコアはどのように決まりますか?
- どのモジュールを選べば良いですか?
- 持ち物や身分証は何が必要ですか?
- 時間配分のコツは?
- よくあるミスは?
- 効果的な学習法は?
- 結果はいつわかりますか?
- 再受験やスコア有効期間は?
IELTS受験総合ガイド: 試験形式と各セクション概要
はじめに
IELTS(アイエルツ、International English Language Testing System)は、英語圏の大学進学や移住、就職などに広く利用される国際的な英語能力試験です。特に英語を母語としない人々が、自身の英語力を証明するために世界140か国以上で受験しています。
この試験の特徴は、Listening・Reading・Writing・Speakingの4技能すべてを評価する点にあります。そのため、単に文法や語彙の知識だけでなく、実際の生活や学術の場でどれだけ英語を使いこなせるかが試されます。
本記事では、IELTSの試験形式全体と各セクションの概要をわかりやすく解説し、初めて受験する方でも全体像をイメージできるように整理しました。
IELTSの試験形式
IELTSは大きく Academic(アカデミック) と General Training(ジェネラル・トレーニング) の2種類に分かれています。どちらを受験するかは目的によって異なります。
-
Academic: 海外大学や大学院への進学、専門資格取得を目指す人向け。
-
General Training: 海外移住や就労、日常生活に必要な英語力を証明したい人向け。
Listening(リスニング)とSpeaking(スピーキング)は両モジュール共通ですが、Reading(リーディング)とWriting(ライティング)は出題内容が異なります。
試験時間と流れ
-
全体所要時間: 約2時間45分
-
順番: Listening → Reading → Writing → Speaking
-
受験形式:
-
紙ベース試験(Paper-based)
-
コンピュータ試験(Computer-delivered)
-
特にコンピュータ試験では、結果が早く出る(5〜7日程度)というメリットがあります。
Listening(リスニング)
-
試験時間: 約30分(紙ベース試験の場合は解答転記のために追加で10分間あり)
-
問題数: 40問(4つのパートで構成)
-
形式: 会話や講義の音声を聞き取り、穴埋め・選択問題・マッチングなどで回答する
パート構成
-
Part 1: 日常的な会話(例:ホテル予約、電話での問い合わせ)
-
Part 2: 独りでの説明(例:観光案内、施設の説明)
-
Part 3: 複数人による議論(例:学生同士や教授との会話)
-
Part 4: 学術的な講義やプレゼンテーション
特徴と対策ポイント
-
問題は順番通りに進むため、設問を先読みする習慣が重要。
-
同義表現(paraphrase)が頻出するため、語彙力と理解力が試される。
-
1回しか音声が流れないため、集中力とメモ取りスキルが鍵になる。
Reading(リーディング)
-
試験時間: 60分(解答転記の時間は含まれない)
-
問題数: 40問
-
形式: 長文を読んで設問に答える(選択問題、見出し付け、True/False/Not Given など多様)
Academicモジュール
-
出題される文章は 学術的・専門的な内容 が中心。
-
論文、研究記事、新聞や雑誌の特集記事などから出題される。
-
大学レベルの読解力や論理的思考力が問われる。
General Trainingモジュール
-
出題される文章は 日常生活や職場で使う実用的な内容 が中心。
-
広告、会社マニュアル、職場の案内文、新聞記事など。
-
生活に直結する実用的な英語を理解できるかが試される。
特徴と対策ポイント
-
問題は文章内の順番に沿って出題される傾向がある。
-
時間配分が非常に重要(各パッセージに約20分を目安に)。
-
キーワードを見つけるスキミング(概要読み)とスキャニング(情報探し)が必須。
Writing(ライティング)
-
試験時間: 60分
-
問題数: 2つの課題(Task 1とTask 2)
-
形式: 文章作成(手書きまたはPC入力)
Academicモジュール
-
Task 1(約150語以上 / 20分目安)
グラフ、表、チャート、図などの視覚資料をもとに情報を要約・比較・説明する。
→ データの正確な読み取りと客観的な表現が求められる。 -
Task 2(約250語以上 / 40分目安)
社会問題や一般的なテーマについて自分の意見を論理的に展開するエッセイ。
→ 主張、理由、例、反論への対応など、構成力が重要。
General Trainingモジュール
-
Task 1(約150語以上 / 20分目安)
日常的な手紙を書く。依頼、苦情、感謝、情報提供など。
→ フォーマル(公式)、セミフォーマル、インフォーマルの文体を使い分ける必要がある。 -
Task 2(約250語以上 / 40分目安)
一般的なテーマについてのエッセイ。Academicに比べやや平易だが、論理的な構成は同様に重視される。
特徴と対策ポイント
-
Task 2の配点が大きいため、必ず十分な時間を確保すること。
-
文法の正確さ、語彙の幅、論理的な構成(序論・本論・結論)が評価の鍵。
-
Academicは「客観的・分析的」、Generalは「実用的・日常的」な表現を意識する。
Speaking(スピーキング)
-
試験時間: 11〜14分
-
形式: 試験官との1対1の面接形式
-
評価基準: 流暢さと一貫性、語彙の幅、文法の正確さ、発音
パート構成
-
Part 1(イントロダクション・日常的な質問 / 約4〜5分)
自己紹介、出身地、趣味、仕事・勉強など身近なトピックについて答える。 -
Part 2(個人スピーチ / 約3〜4分)
試験官から渡されるカード(Cue Card)に書かれたトピックについて、1分間準備し、1〜2分間スピーチを行う。その後、試験官から1〜2問追加質問がある。 -
Part 3(ディスカッション / 約4〜5分)
Part 2のテーマを発展させた抽象的な議論。社会問題や意見交換が中心となり、論理的な思考力が試される。
特徴と対策ポイント
-
自然な会話を意識し、暗記した文章をそのまま話すのは避ける。
-
長く話すことよりも、一貫性のある論理的な回答が評価される。
-
Part 2ではメモを活用し、序論・本論・結論の簡単な流れを準備すると話しやすい。
-
発音やイントネーションも評価対象のため、聞き手に伝わる英語を意識する。
まとめ
IELTSは、Listening・Reading・Writing・Speakingの4技能を総合的に測定する国際的な英語試験です。AcademicとGeneral Trainingの2種類があり、進学や移住といった目的に応じて選択する必要があります。
各セクションには独自の特徴があり、Listeningでは正確な聞き取り、Readingでは効率的な読解力、Writingでは論理的な文章構成、Speakingでは自然で一貫した会話力が問われます。
試験の形式を理解しておくことで、効率的な学習計画を立てやすくなり、スコアアップに直結します。これから受験を考えている方は、自分の目的に合ったモジュールを選び、弱点を補強しながらバランスよく準備を進めましょう。
IELTSとは何のための試験ですか?
英語を母語としない人の英語運用力を測定する国際試験で、大学・大学院進学、就職、移住申請などに広く利用されます。4技能(Listening/Reading/Writing/Speaking)を総合評価します。
AcademicとGeneral Trainingの違いは何ですか?
ListeningとSpeakingは共通ですが、ReadingとWritingの内容が異なります。
Academicは学術的文脈(進学・専門資格向け)、General Trainingは実生活・職場文脈(移住・就労向け)です。
試験全体の所要時間と受験の流れは?
約2時間45分です。通常はListening → Reading → Writing → Speakingの順で実施されます(Speakingのみ別時間に行われる場合があります)。
紙ベースとコンピュータ試験の違いは?
問題内容・配点は同じです。コンピュータ試験はタイピングで回答し、結果通知が比較的早い傾向があります。手書きが得意なら紙、タイピングが得意ならコンピュータを選ぶと良いでしょう。
Listeningセクションの構成は?
4パート計40問。日常会話、説明、ディスカッション、講義などが出題され、音声は原則1回のみ再生されます。紙試験では解答転記のための時間が追加されます。
Readingセクションの違い(Academic/General)は?
Academicは学術的な長文(論文・記事など)、Generalは実用文(広告・案内・マニュアルなど)が中心です。いずれも40問・60分で、設問形式は多様です。
Writingは何を求められますか?
60分で2課題。
Academic: Task 1はグラフ等の要約、Task 2は意見エッセイ。
General: Task 1は手紙(目的や文体の適切さ)、Task 2は一般テーマのエッセイ。
Speakingの進み方は?
試験官との1対1で11〜14分。Part 1(身近な質問)→Part 2(1分準備後のスピーチ)→Part 3(抽象的議論)の3部構成です。
スコアはどのように決まりますか?
各セクションが0.5刻みのバンドスコア(0〜9)で評価され、平均してOverall Band Scoreが算出されます。四捨五入の規則に従って最終スコアが決まります。
どのモジュールを選べば良いですか?
進学・専門資格が目的ならAcademic、移住・就労や実生活向けならGeneral Trainingが一般的です。志望校・申請先の要件を必ず確認しましょう。
持ち物や身分証は何が必要ですか?
受験登録時に使用した有効な身分証(多くの会場でパスポート)が必要です。会場からの受験確認メールの指示に従ってください。
時間配分のコツは?
Readingは各パッセージ約20分、WritingはTask 1約20分/Task 2約40分を目安に。Listeningは設問先読み、Speakingは簡潔かつ一貫性のある回答を意識しましょう。
よくあるミスは?
- 指示語数を超える(Writingの語数不足も減点要因)
- スペリング・文法ミスの放置
- Listeningでの単位・複数形の誤り
- Readingで設問のタイプを取り違える
- Speakingで暗記丸暗記の不自然な応答
効果的な学習法は?
- 模試で現状把握 → セクション別の弱点分析
- Listeningはディクテーションとパラフレーズ対策
- Readingはスキミング・スキャニングの反復訓練
- Writingは良答案の構成テンプレート化と添削
- Speakingは録音・客観評価とトピック別語彙の拡充
結果はいつわかりますか?
会場や方式によりますが、コンピュータ試験は比較的早め、紙試験はやや時間がかかる傾向があります。正式な目安は受験申込時の案内を確認してください。
再受験やスコア有効期間は?
受験回数に制限はありません。スコアの有効期間は通常2年とされますが、提出先の方針を必ず確認してください。