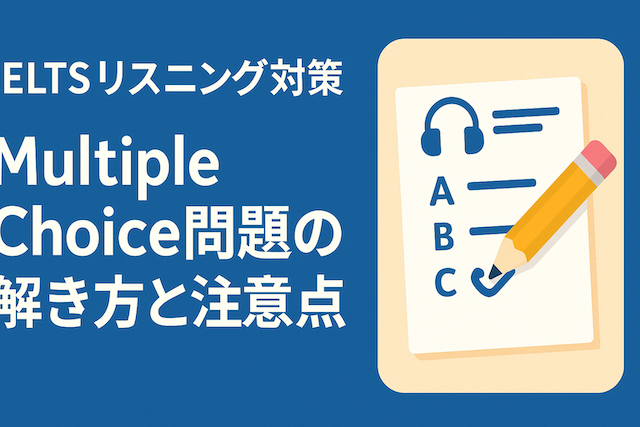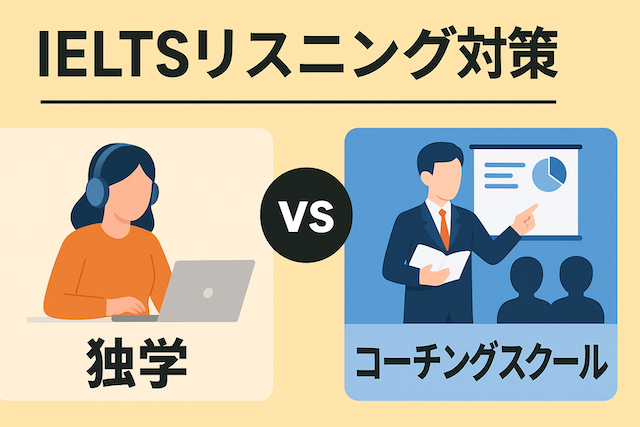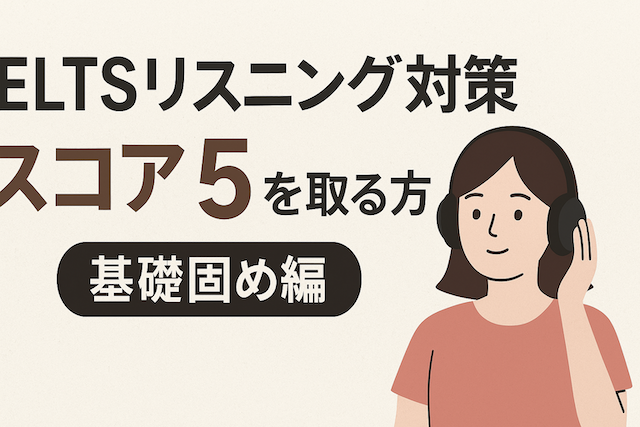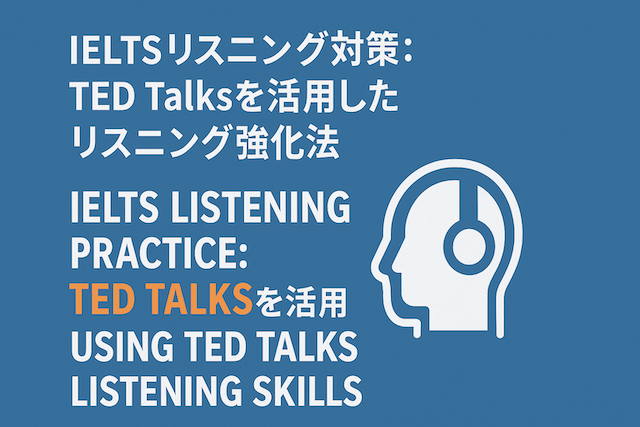目次
- IELTSリスニング対策: Multiple Choice問題の解き方と注意点
- はじめに
- Multiple Choice問題の特徴
- 解き方ステップ
- 注意点とよくあるミス
- 効率的な練習方法
- まとめ
- FAQ:Multiple Choice問題の解き方と注意点
- Multiple Choiceはどのセクションに出ますか?
- 単一解答と複数解答の違いは?
- 先読みのコツは?
- 言い換え(シノニム)にどう対応する?
- ひっかけ(ディストラクター)の見抜き方は?
- メモは取ったほうがいい?
- 迷ったときの消去法は?
- 複数解答の順序は音声の順と一致する?
- 時間が足りません。管理方法は?
- スペリングや大文字小文字は採点に影響する?
- 数値・日付・固有名詞が絡む選択肢の注意点は?
- アクセント(英・米・豪)で聞き取りが落ちます
- 正解率が上がらない原因は何?
- 効果的な復習方法は?
- コンピューター受験と紙受験で戦略は変わる?
- 「全部正しそう」に見えるときは?
- 1問落とすと連鎖的に崩れます
- 練習で伸ばす優先順位は?
- ディスカッション型(Section 3)のコツは?
- 講義型(Section 4)のコツは?
- 具体的な家庭学習メニューは?
IELTSリスニング対策: Multiple Choice問題の解き方と注意点
はじめに
IELTSリスニングにおいて、多くの受験者がつまずく問題形式のひとつが Multiple Choice(選択問題) です。見た目はシンプルで「選択肢から正しいものを選ぶだけ」と思われがちですが、実際は 言い換え表現の多用 や ひっかけの配置 によって非常に難易度が高くなっています。特に、選択肢がどれも「正しそう」に聞こえるため、最後まで聞き切らずに誤答してしまうケースが少なくありません。
しかし、正しいアプローチを理解すれば、この問題形式は安定した得点源にできます。ポイントは 先読みの習慣化、シノニムへの対応力、そして 冷静な消去法 です。
この記事では、Multiple Choice問題の特徴を整理し、実際にどのように解けば良いのか、また注意すべき点をわかりやすく解説します。IELTSでリスニングスコアを伸ばしたい方は、ぜひ参考にしてください。
Multiple Choice問題の特徴
IELTSリスニングにおけるMultiple Choiceは、一見するとシンプルですが、実際には細かい工夫が施されており、受験者を混乱させやすい形式です。以下にその主な特徴をまとめます。
1. 選択肢の数と形式
-
基本は3〜4択が多いですが、場合によっては5つ以上出ることもあります。
-
解答形式は大きく分けて2種類:
-
単一解答(正しい答えを1つ選ぶ)
-
複数解答(2つ以上選ぶよう指示される場合あり)
-
2. 試されるスキル
-
単語や文の聞き取り力だけでなく、
-
要点を素早く把握する力
-
情報の取捨選択能力
-
言い換え表現を見抜く力
が総合的に試されます。
-
3. 選択肢のトリック
-
多くの場合、似た内容が繰り返されるように構成されています。
-
例: 「I thought about taking the economics course, but in the end I decided on psychology.」
→ 選択肢に economics と psychology が両方あると、前半に引っかかって誤答する人が多い。
4. 情報の量とスピード
-
会話や説明の中で答えが一度しか言及されないこともあります。
-
音声のスピードは速くないものの、情報量が多く、最後まで集中することが必要です。
解き方ステップ
Multiple Choice問題は「受け身で聞く」のではなく、戦略的に聞き取る姿勢が大切です。以下のステップで取り組むと正答率が上がります。
1. 問題文と選択肢を先読みする
-
音声が流れる前に キーワード をチェックする。
-
誰が?何を?なぜ?といったポイントを意識。
-
例: Why did the student choose that course?
→ 「理由」に関する表現(because, due to, reason, prefer など)を想定しておく。
2. シノニム(言い換え)を意識する
-
IELTSでは選択肢の単語がそのまま出るとは限らない。
-
例:
-
expensive → costs a lot
-
cheap → affordable
-
job → occupation, career
-
3. 消去法を活用する
-
確実に違うと分かる選択肢はすぐ除外。
-
残り2つで迷ったら「音声でより強く裏付けられている方」を選ぶ。
4. 複数解答の戦略
-
「Choose TWO letters」と指定された場合、答えが連続して出るとは限らない。
-
前半と後半に分かれて出るケースもあるので、焦らずにメモを取りながら進める。
5. 最後まで集中する
-
会話の後半で「最初の意見を撤回」するパターンが多い。
-
「最初に出てきた選択肢に飛びつかない」ことが重要。
注意点とよくあるミス
Multiple Choice問題は、テクニックを知っていれば得点源になりますが、典型的なミスにはまると失点しやすい形式です。以下によくある注意点を整理します。
1. 最初に出た内容に飛びつかない
-
試験では「Aが良さそうだが、やっぱりBにする」といった言い直しが頻出。
-
最初に出てきた言葉だけで判断すると不正解になる可能性が高い。
2. 「どれも正しそう」に見える罠
-
選択肢はどれも plausible(もっともらしい)ように作られている。
-
正解は「音声でしっかり裏付けられたもの」だけと心得ること。
3. 指定数以上の選択は即失点
-
「Choose TWO」の場合、3つ選んだら即不正解。
-
正答数の確認を必ず最後に行う習慣をつける。
4. 曖昧な記憶に頼らない
-
「たしかそんなことを言っていた気がする…」という曖昧な記憶で選ぶのは危険。
-
本番ではメモを取り、確実に聞き取れた内容に基づいて解答する。
5. 試験時間のプレッシャーに負けない
-
Multiple Choiceは情報量が多く、集中力を奪われやすい。
-
普段から「制限時間内で先読み→聞き取り→選択」を繰り返し練習しておくことが大切。
効率的な練習方法
Multiple Choice問題は、ただ数をこなすだけでは伸びにくい形式です。戦略を意識したトレーニングを積むことで、短期間で正答率を上げられます。
1. 公式問題集で集中的に演習する
-
Cambridge IELTSシリーズなどの公式教材を使い、Multiple Choiceだけを抜き出して演習する。
-
実際の試験に近い言い回しやトリックに慣れることができる。
2. ディクテーションで細部を確認
-
特に迷った問題は音声を止めながら書き起こす。
-
言い換え表現や細かなニュアンスを聞き取る練習になる。
3. 言い換え表現リストを作る
-
「expensive → costs a lot」「opinion → point of view」など、自分用のシノニム集を作成。
-
選択肢に出てきそうな言葉をまとめておくと、試験中に即対応できる。
4. 時間制限を設けて練習
-
本番同様に「30秒で選択肢を先読みする」練習を繰り返す。
-
先読みのスピードと集中力を鍛えることができる。
5. 音声を二度聞いて確認する
-
本番では一度しか聞けないが、練習段階では二度聞きを有効活用。
-
一度目は全体の流れ、二度目はディテールに集中して復習する。
まとめ
IELTSリスニングのMultiple Choice問題は、
一見シンプルに見えても 言い換え表現 や ひっかけ によって難易度が高く、多くの受験者が苦手とする形式です。
しかし、次のポイントを意識すれば得点源にできます。
-
先読み でキーワードを把握する
-
シノニム を意識して音声を聞く
-
消去法 を使って不正解を減らす
-
最後まで集中 して聞き切る
さらに、公式問題集で集中的に練習し、自分だけの「言い換えリスト」を蓄積していけば、本番での対応力は大きく向上します。
Multiple Choiceを攻略できれば、リスニング全体の安定感が増し、スコアアップに直結します。ぜひ日々の学習に取り入れて、確実に得点できる分野にしていきましょう。
FAQ:Multiple Choice問題の解き方と注意点
Multiple Choiceはどのセクションに出ますか?
全てのセクションで出題されます。特にSection 3・4では学術的な話題で情報量が多く、言い換え表現が増えるため難度が上がります。
単一解答と複数解答の違いは?
単一解答は正解を1つ、複数解答は指示どおりに2〜3つ選びます。複数解答で指示数を外す(例:2つのところを3つ選ぶ)と自動的に不正解になります。
先読みのコツは?
設問の 主語・動詞・キーワード を15〜30秒でマーキングし、理由・目的・対比・数量などの出題トリガー語(because, reason, however, instead, the number of など)を想定します。
言い換え(シノニム)にどう対応する?
選択肢の重要語を言い換えセットで覚えます。例:expensive → costs a lot / pricey、opinion → point of view、benefit → advantage。音声は選択肢の語をそのままは言いません。
ひっかけ(ディストラクター)の見抜き方は?
前言撤回・対比・例外・弱め表現に注意。例:「I used to think A, but now I prefer B.」→ Aは囮、答えはB。might, probably, not necessarily などのモダリティも判断材料です。
メモは取ったほうがいい?
Yes。設問番号の横にキーワード短語だけを書き、長文は避けます。who/what/why/when を1語でメモ(例:why→“reason: schedule conflict”)。聞きながら即消去法に使います。
迷ったときの消去法は?
「音声で明確に否定・除外された選択肢」から消します。残り2択なら、より具体的・限定的に音声と一致する方(数値・固有名・因果関係が合う方)を選びます。
複数解答の順序は音声の順と一致する?
一致しないことが多いです。2つの答えが会話の前半・後半に離れて出ることもあるため、1つ目を確定しても油断せず最後まで聞き切りましょう。
時間が足りません。管理方法は?
各セットごとに「先読み→聞く→即マーク→見直し」のサイクルを固定します。先読みは欲張らず、設問の次の2〜3問分に集中。難問は10秒以上悩まず、仮マークして前へ進みます。
スペリングや大文字小文字は採点に影響する?
Multiple Choiceは通常、選択肢の記号(A/B/C など) をマークする形式なのでスペリングの採点は基本不要です。指示に従い記号ミスを防ぐことに集中しましょう。
数値・日付・固有名詞が絡む選択肢の注意点は?
音声は「概数・比較・例外」を混ぜます(just under 50, no later than May など)。選択肢の数詞・比較語(more/less than, at least, within)を事前にマーキングして照合します。
アクセント(英・米・豪)で聞き取りが落ちます
各アクセントの弱形・連結に慣れるため、短い講義・大学相談の音源で反復。特に豪アクセントの /eɪ/→/aɪ/ など癖に慣れると、言い換え検出が安定します。
正解率が上がらない原因は何?
①先読み不足 ②言い換え耐性不足 ③最初の発話に飛びつく ④設問ごとの聞き取りポイントが曖昧 ⑤見直し時に指示数や記号の整合を確認していない、のいずれかが多いです。
効果的な復習方法は?
不正解の選択肢を「音声のどこに対応していたか」を特定し、誤答の原因タグ(語彙/言い換え/推論/スピード/先読み)を付与。次回は同タグの問題だけ束ねて再演習します。
コンピューター受験と紙受験で戦略は変わる?
基本戦略は同じ。コンピューター受験では画面スクロール中に設問見落としが起きやすいので、表示倍率とスクロール位置を固定化する練習をしておくと安定します。
「全部正しそう」に見えるときは?
音声の限定語(only, mainly, especially, in particular, rather than)や転換語(however, instead, whereas)に一致する一択を探します。曖昧語(some, kind of)は消去対象になりがちです。
1問落とすと連鎖的に崩れます
各設問を独立タスクと捉え直し、次の問題に影響させないマインドセットを徹底。仮マーク→次へ→最後に10〜20秒で指示数・記号の最終整合を確認します。
練習で伸ばす優先順位は?
①先読みの速さ ②言い換え対策(自作シノニム表) ③ディストラクターの型(前言撤回・対比・例外) ④数値/比較/期間表現の聞き分け、の順に鍛えると効率的です。
ディスカッション型(Section 3)のコツは?
話者ごとに主張が揺れやすいので、発話者の「立場ラベル」をメモ(Tutor: 要件, Student A: 賛成, Student B: 代替案 など)。誰の意見に対する設問かを先に把握します。
講義型(Section 4)のコツは?
段落の見出し(定義→原因→影響→対策→結論)の流れを意識。設問が「原因」なら because/due to、「影響」なら lead to/result in を待ち構える形で聞きます。
具体的な家庭学習メニューは?
- Cambridge過去問のMultiple Choiceだけを抜き出し、1日15問×2セット
- 誤答は音声スクリプトで原因タグ付け → 同タグを翌日リトライ
- 自作シノニム表を毎日10語更新(週70語)
- 週1回は本番同様の通し演習(先読み→一発勝負)