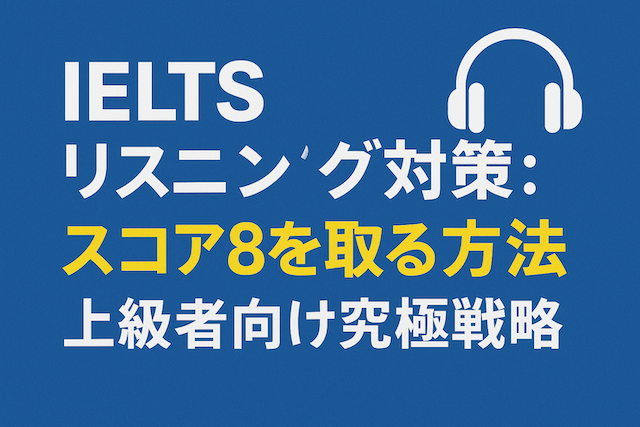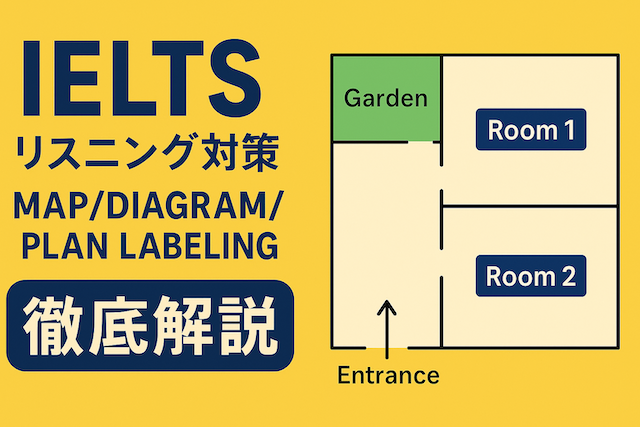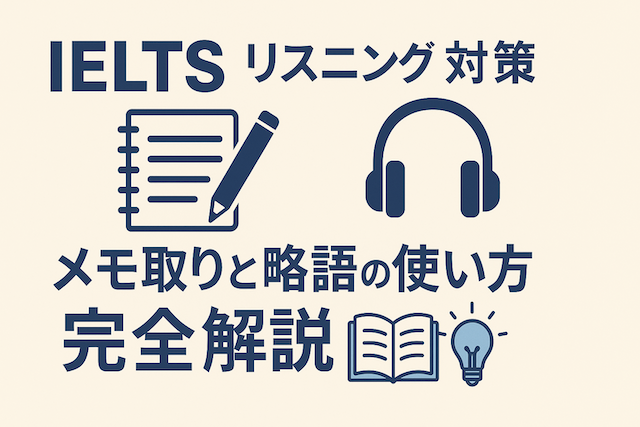目次
- IELTSリスニング対策: 環境・サイエンス系パッセージの傾向と対策
- はじめに
- 環境・サイエンス系パッセージの出題傾向
- よく出る設問タイプ
- 対策のポイント
- 学習法
- まとめ
- よくある質問(FAQ)
- Q1. 環境・サイエンス系のトピックはどのセクションで出やすい?
- Q2. どんなテーマが頻出ですか?
- Q3. 専門用語はどの程度覚えるべき?
- Q4. スコアに直結する聞き取りポイントは?
- Q5. 苦手なパラフレーズ対策は?
- Q6. よく出る設問形式は?
- Q7. Section 4(講義形式)に強くなる練習法は?
- Q8. 数字の聞き間違いを減らすには?
- Q9. 図表・マップ問題はどう対策する?
- Q10. 背景知識はどの程度必要?
- Q11. 推奨する素材やメディアは?
- Q12. リスニング中にメモはどう取る?
- Q13. 学習スケジュールの作り方は?
- Q14. 本番で聞き逃したらどうする?
- Q15. 独学でもスコアは伸ばせる?
IELTSリスニング対策: 環境・サイエンス系パッセージの傾向と対策
はじめに
IELTSリスニングでは、旅行や日常生活の会話に加えて、学術的なテーマを扱うパッセージも数多く登場します。その中でも特に受験者を悩ませやすいのが、環境問題やサイエンス系のトピックです。
「気候変動」「再生可能エネルギー」「動物保護」「新しい科学技術の研究」など、現代社会で注目されるテーマが取り上げられるため、背景知識が少ないと難しく感じるかもしれません。また、専門的な用語や数字・統計が多く出てくることから、内容を追いながら正確に答えを拾う力が求められます。
しかし、心配はいりません。IELTSでは高度な専門知識までは必要なく、あくまで一般的なアカデミック英語を理解できるかどうかが試されています。つまり、パラフレーズを正しく聞き取り、要点を押さえるトレーニングを積めば十分に対応できます。
本記事では、環境・サイエンス系パッセージの出題傾向や頻出テーマ、そして効果的なリスニング対策を解説します。特にSection 3・4での攻略に役立つ実践的なヒントをまとめていますので、ぜひ学習に役立ててください。
環境・サイエンス系パッセージの出題傾向
IELTSリスニングにおける環境・サイエンス系のパッセージは、主に**Section 3(学生同士や教授とのディスカッション)とSection 4(講義形式のモノローグ)**で登場します。難易度は比較的高めで、アカデミックな内容や専門用語が含まれるのが特徴です。
1. 頻出テーマ
-
気候変動・環境問題
-
global warming(地球温暖化)、climate change(気候変動)、carbon emissions(二酸化炭素排出)
-
-
自然保護・動物関連
-
endangered species(絶滅危惧種)、wildlife conservation(野生動物保護)
-
-
再生可能エネルギー・資源問題
-
renewable energy(再生可能エネルギー)、wind/solar power(風力・太陽光発電)
-
-
科学技術・研究
-
genetic research(遺伝子研究)、space exploration(宇宙探査)、artificial intelligence(人工知能)
-
2. 話し方のスタイル
-
説明・講義型(Section 4)
大学の講義のように、一人の話者が長く説明します。専門用語が出やすく、要点を聞き逃さない集中力が必要です。 -
ディスカッション型(Section 3)
学生同士、または教授との会話形式。意見の交換や研究計画の説明があり、話者ごとの立場を把握する必要があります。
3. 設問の傾向
-
ノート/表の穴埋め
講義ノートや研究概要を埋める形式が多く、キーワードを的確に聞き取る必要があります。 -
選択問題(Multiple Choice)
複数の要素を比較させる設問が出題されやすく、細かいニュアンスの違いを理解する力が問われます。 -
地図・図表問題
実験施設の配置や研究エリアの説明で、位置や構造を把握する力が試されます。
4. 難しさのポイント
-
専門的な語彙が多く登場し、意味を知らない単語に出会いやすい。
-
数字・割合・年代が解答のカギになることが多い。
-
パラフレーズ(言い換え)が多用され、設問と音声の表現が一致しない。
よく出る設問タイプ
環境・サイエンス系パッセージでは、アカデミックな内容を整理しながら聞き取れるかどうかを測るために、特定の設問形式がよく出題されます。以下では、特に注意して対策すべき問題タイプを紹介します。
1. ノート/表の穴埋め(Note/Table Completion)
-
特徴
大学の講義ノートや研究概要のような形式で、空欄を埋める問題。 -
例
「Solar energy is ______ compared to fossil fuels.」 -
ポイント
空欄前後の文脈を先に把握し、どんな品詞(名詞・形容詞・数字)が入るのか予測してから音声を聞くと効率的。
2. 選択問題(Multiple Choice Questions)
-
特徴
研究結果の解釈や意見の違いなどを問う形式。3〜4つの選択肢から1つ、あるいは複数を選ぶ場合もある。 -
例
「What is the main cause of the decline in species population?」
A. Climate change
B. Pollution
C. Overhunting
D. Natural disasters -
ポイント
選択肢の言葉は音声中でそのまま出てこないことが多い。パラフレーズに敏感になることが必要。
3. マップ/図表問題(Map/Diagram Labeling)
-
特徴
実験施設の説明や環境保護区の紹介で、位置関係を把握しながら答える形式。 -
例
「The laboratory is located to the ______ of the main hall.」 -
ポイント
方向(north, south, left, right, adjacent to)や空間的な表現を聞き逃さないことが大事。
4. 要約完成問題(Summary Completion)
-
特徴
長めの説明文を要約したテキストの空欄を埋める形式。 -
例
「The research suggests that renewable energy sources are ______ and more environmentally friendly.」 -
ポイント
音声の中で繰り返し出るキーワードが答えになりやすい。
対策のポイント
環境・サイエンス系のリスニングは内容がアカデミックで、難易度が高めに感じられることが多いですが、出題のパターンはある程度決まっています。以下のポイントを意識すれば、正答率を大きく上げることができます。
1. 専門用語よりもパラフレーズに注目する
-
IELTSでは、設問のキーワードがそのまま音声で使われることは少なく、**言い換え(paraphrasing)**で登場することが多い。
-
例:
-
global warming → rise in average temperatures
-
renewable energy → energy from natural resources
-
endangered animals → species at risk of extinction
-
2. 数字・データを正確に聞き取る
-
環境や科学のテーマでは、統計・割合・年代がよく答えになる。
-
注意点:
-
fifteen と fifty のように紛らわしい数字に要注意。
-
年代表現(eighteen ninety → 1890、twenty twenty-five → 2025)を聞き逃さない。
-
3. 因果関係を意識する
-
講義や研究説明では、原因と結果を示す表現が頻出する。
-
接続表現の例:
-
原因 → because, due to, as a result of
-
結果 → therefore, consequently, lead to
-
-
答えはこうしたフレーズ直後に登場することが多い。
4. 強調表現を聞き逃さない
-
話者は重要な情報を強調して述べることがある。
-
例:
-
The most significant factor is…
-
What I’d like to highlight is…
-
-
強調部分が設問の答えになる確率は高い。
5. 音声の流れを先読みする
-
問題冊子を素早く確認し、空欄前後を読んで「答えの種類」を予測しておく。
-
名詞が入りそうか、形容詞か、数字か。
-
-
あらかじめ心の準備をしておくことで、音声の中から正しい情報をキャッチしやすくなる。
学習法
環境・サイエンス系パッセージの攻略には、リスニングの技術練習と背景知識のインプットの両方が必要です。以下の学習法を取り入れることで、内容理解力と集中力を同時に鍛えることができます。
1. 科学系コンテンツで耳を慣らす
-
BBC Earth, National Geographic, TED Talks など、科学や環境問題を扱う動画を日常的に視聴する。
-
IELTS本番に近いスピードとアカデミックな語彙に触れられる。
-
特に「ドキュメンタリー形式の解説」や「大学教授の講演」に近いものが効果的。
2. 過去問で Section 4 を重点的に練習
-
Cambridge IELTS シリーズを活用し、環境・科学系が多く登場する Section 4(講義形式) を繰り返し解く。
-
解答後は必ずスクリプトを確認し、
-
聞き取れなかった単語
-
言い換え表現
-
答えに直結するシグナルワード
を整理する。
-
3. シャドーイングでスピードに慣れる
-
音声を止めずにそのまま声に出して追いかける「シャドーイング」を行う。
-
特に数字・データや専門用語を含む部分を繰り返し練習すると、実際の試験で混乱しにくくなる。
4. 頻出トピックの語彙をまとめて学習
-
難しい専門語を暗記する必要はないが、頻出する基本的な語彙には慣れておくと安心。
-
例:
-
pollution(汚染)
-
conservation(保護)
-
habitat(生息地)
-
sustainable(持続可能な)
-
-
単語帳としてではなく、リスニングでどう使われているかに注目する。
5. ディクテーションで弱点を発見
-
短い音声を一時停止しながら書き取る「ディクテーション」を実践。
-
自分が聞き取れない部分の傾向(数字?接続詞?専門語?)を把握でき、効率的な弱点補強につながる。
まとめ
IELTSリスニングにおける環境・サイエンス系のパッセージは、専門的な語彙や数字、データが多く登場するため、受験者にとって難所になりやすい分野です。しかし、出題傾向を理解し、正しい対策を取れば安定して得点できるようになります。
ポイントを振り返ると:
-
出題テーマは限られている(気候変動・再生可能エネルギー・環境保護・科学研究など)。
-
設問形式はパターン化しており、特にノート穴埋め・選択問題・図表問題が多い。
-
パラフレーズに敏感になることが正答率向上のカギ。
-
数字や因果関係の聞き取りを重視する。
-
学習は過去問+科学系コンテンツ+シャドーイングの組み合わせが効果的。
最終的に大切なのは、難解な内容を丸暗記することではなく、**「聞き取れた情報を整理し、設問と結びつける力」**を養うことです。環境や科学の話題はIELTSだけでなく、海外大学や職場でも必ず出てくるテーマなので、学習を通じて「実用的なアカデミック英語力」を身につけられるはずです。
よくある質問(FAQ)
本記事「IELTSリスニング対策: 環境・サイエンス系パッセージの傾向と対策」に関するFAQです。試験対策の要点を短くまとめています。
Q1. 環境・サイエンス系のトピックはどのセクションで出やすい?
主にSection 3(ディスカッション)とSection 4(講義形式)で出題されます。特にSection 4は一人の話者が長く説明するため、難易度が高めです。
Q2. どんなテーマが頻出ですか?
気候変動、再生可能エネルギー、野生動物保護、資源問題、遺伝子研究、宇宙探査、AIなどの現代科学と環境問題がよく扱われます。
Q3. 専門用語はどの程度覚えるべき?
全て暗記する必要はありません。パラフレーズ(言い換え)に対応できる基本語彙と、頻出のシグナルワードに絞って学ぶのが効率的です。
Q4. スコアに直結する聞き取りポイントは?
数字(割合・年号・数量)、固有名詞、因果関係を示す表現(because, due to, therefore など)の直後に答えが出ることが多いです。
Q5. 苦手なパラフレーズ対策は?
過去問の設問キーワードとスクリプト上の言い換えを対応表にして復習しましょう。例:global warming → rise in average temperatures。
Q6. よく出る設問形式は?
ノート/表の穴埋め、選択問題、図表・マップのラベリング、要約完成などです。空欄前後から品詞や語の種類(名詞・形容詞・数字)を予測してから聴くと正答率が上がります。
Q7. Section 4(講義形式)に強くなる練習法は?
過去問のSection 4を繰り返し解き、スクリプトで言い換え表現とシグナルワードを確認。難所はシャドーイングで音の流れごと定着させましょう。
Q8. 数字の聞き間違いを減らすには?
fifteen と fifty のような紛らわしい発音を集中的に練習。年号(eighteen ninety → 1890)の言い方にも慣れておくと失点を防げます。
Q9. 図表・マップ問題はどう対策する?
方位・位置関係(north, south, left, right, adjacent to など)を素早く把握。音声前のプレビューで図の構造と選択肢の候補を先読みしておくのがコツです。
Q10. 背景知識はどの程度必要?
高度な専門知識は不要ですが、テーマ別の基本語彙(pollution, conservation, habitat, sustainable など)に耳を慣らしておくと理解がスムーズです。
Q11. 推奨する素材やメディアは?
BBC Earth、National Geographic、TED Talksなどの科学系コンテンツが有効。本番に近い語彙・スピード・論理展開に触れられます。
Q12. リスニング中にメモはどう取る?
全文は書かず、数字・固有名詞・キーワードのみを箇条書き。因果や対比は矢印(→, ⇄)や記号で素早く表現すると良いです。
Q13. 学習スケジュールの作り方は?
週3回はSection 4の過去問、毎日10~15分のシャドーイング、週1回ディクテーションで弱点発見。最後にパラフレーズ表を更新して知識を再利用します。
Q14. 本番で聞き逃したらどうする?
引きずらずに次へ進むのが最善。設問の並びは音声の進行に一致するため、次の空欄のタイプを即座に予測してリカバリーを狙いましょう。
Q15. 独学でもスコアは伸ばせる?
十分可能です。過去問の反復(精聴→スクリプト確認→再聴)、パラフレーズ対応表の更新、数字・因果の重点練習を軸に継続すれば、安定して得点力が上がります。