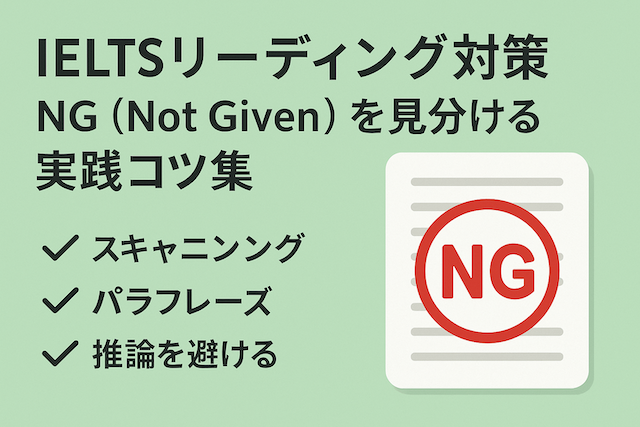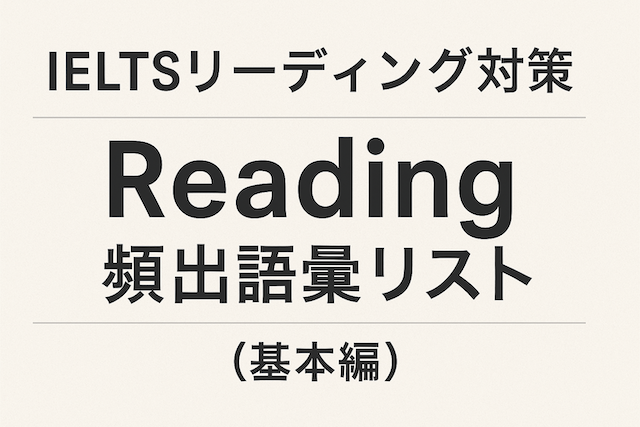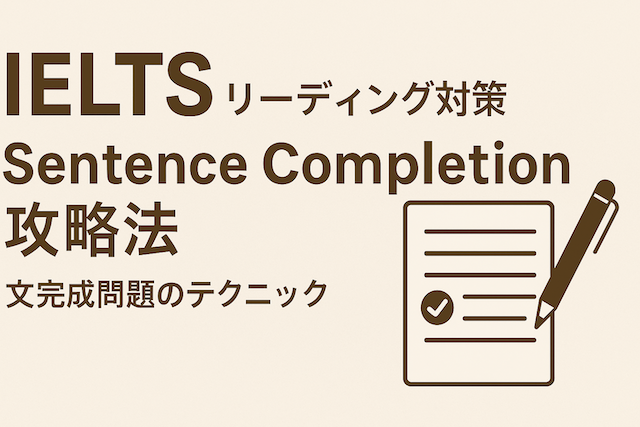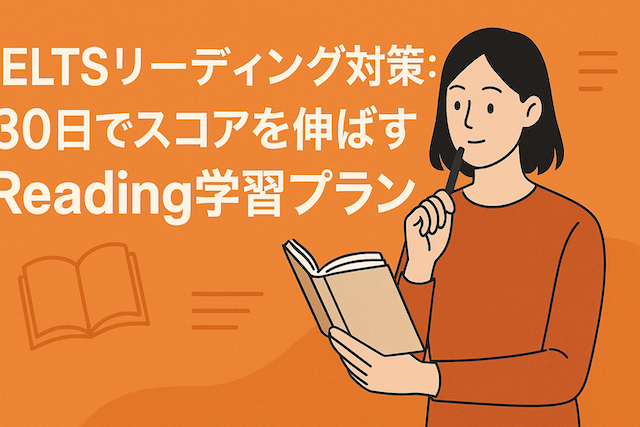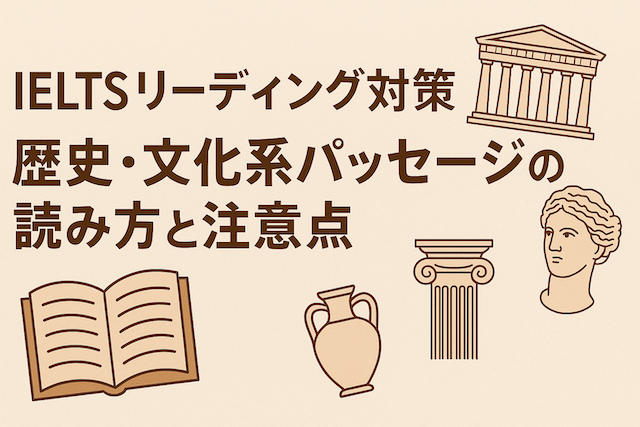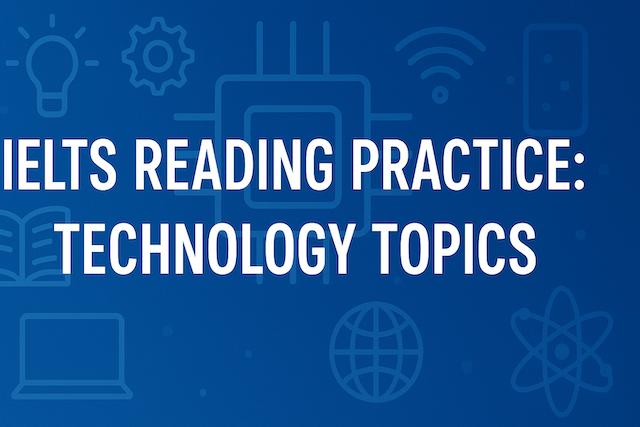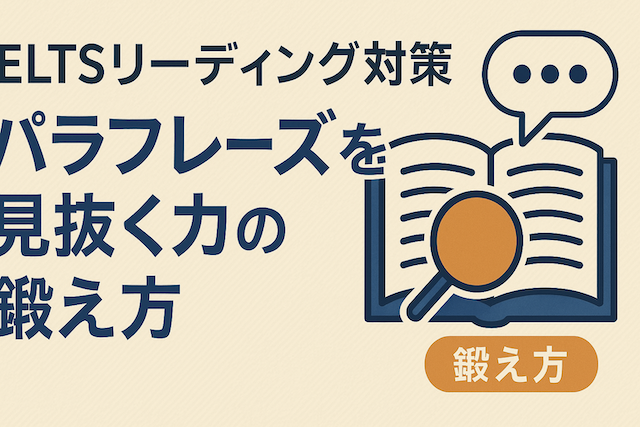目次
- IELTSリーディング対策: NG(Not Given)を見分ける実践コツ集
- はじめに
- NG(Not Given)の基本理解
- NGを見分けるための実践コツ集
- 練習方法
- まとめ
- FAQ:NG(Not Given)を見分ける実践コツ集
- Not Given(NG)とFalseの違いは?
- NGを最速で見分けるチェックリストは?
- 設問に断定表現(all/always/never)がある時のコツは?
- 本文に関連語はあるが結論が書かれていない場合は?
- パラフレーズ(言い換え)で見落とさないためには?
- 背景知識が頭に浮かんで迷う時の対処は?
- FalseとNGをよく取り違えます。復習方法は?
- 設問の語順は本文の情報順と連動しますか?
- 時間が足りない時、NGはどう処理する?
- 「一部」「多くの」「ほとんど」など数量語の扱いは?
- 例外句(except/unless/however)に気づけない時の対策は?
- 図表や注釈がある場合、NGの判定は?
- 本文に一般論はあるが特定条件がない場合は?
- 練習でNG判定力を鍛える具体メニューは?
IELTSリーディング対策: NG(Not Given)を見分ける実践コツ集
はじめに
IELTSリーディングの問題形式の中でも、特に受験者を混乱させやすいのが True / False / Not Given の設問です。この中で「Not Given(NG)」は、情報が本文に「書かれていない」ことを示しますが、多くの人が「False」との違いを見極められず、失点しやすいポイントになっています。
なぜNGが難しいのかというと、私たちは無意識に 常識や背景知識で空白を埋めてしまう からです。設問を読むと「きっと本文もそう言っているはず」と考えてしまい、根拠が本文に存在しないのに答えを選んでしまうのです。
しかし、IELTSリーディングではあくまで 本文に明記されている情報だけ を根拠に判断する必要があります。つまり、答えの選択基準は「本文に根拠があるかないか」という一点に絞られるのです。
この記事では、NGを確実に見分けるための実践的なコツをまとめ、Falseとの違いをクリアに理解できるよう解説します。NGの判断力を高めることで、True / False / Not Given 問題全体での得点力も大きく向上します。
NG(Not Given)の基本理解
まずは、True / False / Not Given 問題の基本ルールを整理しておきましょう。
-
True(T)
設問の内容が、本文に書かれている情報と 一致している。 -
False(F)
設問の内容が、本文に書かれている情報と 反対または矛盾している。 -
Not Given(NG)
設問の内容に関する情報が、本文に まったく触れられていない。
ここで重要なのは、「False」と「Not Given」の違いです。
-
False は「本文に答えはあるが、逆のことが書かれている」場合。
-
Not Given は「本文にそもそも答えが書かれていない」場合。
例えば、設問が「全ての学生は試験を受ける必要がある」と書いてあったとします。
-
本文に「全ての学生が試験を受けなければならない」と書いてあれば → True
-
本文に「一部の学生だけが試験を受ける」と書いてあれば → False
-
本文が「試験について全く触れていない」となれば → Not Given
つまり、NGを見抜くカギは 「本文に情報が存在するかどうか」 であり、推測や常識ではなく、テキストに書かれている事実だけで判断することが求められます。
NGを見分けるための実践コツ集
1. キーワードの有無を確認する
設問に登場するキーワードやテーマが本文にまったく現れない場合、それはNGの可能性が高いです。
ただし、本文では同じ言葉ではなく パラフレーズ(言い換え) で書かれていることもあるため、「似た意味の表現があるかどうか」を慎重に確認しましょう。
2. 本文が部分的な情報しか示していない場合はNG
設問が「すべての観光客が無料の地図を受け取る」と述べていて、本文には「一部の観光客が無料の地図を受け取る」としか書かれていない場合、これはFalseではなくNGです。
なぜなら本文には「すべて」という断定を裏づける情報が 欠けている からです。
3. 断定表現に注目する
設問に all, always, never, only, must などの強い表現が含まれている場合、本文がそこまで明確に断定していなければNGの可能性が高まります。
IELTSでは「断定」か「限定」の差が答えを左右することが多いので、特に注意しましょう。
4. 背景知識で補わない
受験者が自分の常識や知識で「きっとそうに違いない」と判断してしまうのがNGで一番多いミスです。
たとえば、設問が「アメリカは世界で最も英語話者が多い国である」と述べていても、本文がその点に触れていなければNGになります。
「常識的に正しいかどうか」は無関係であり、判断基準はあくまで本文の情報です。
5. Falseとの違いを意識的に整理する
-
False → 本文に「逆のこと」が明確に書かれている
-
Not Given → 本文に「その情報が存在しない」
FalseとNGを取り違えると大きな失点につながるので、常に「本文に逆の情報があるかどうか」で線引きする習慣を持ちましょう。
練習方法
1. 必ず根拠を探す習慣をつける
True / False / Not Given の問題を解くときは、必ず本文のどこに根拠があるかを確認しましょう。
-
根拠が明確に見つかる → True または False
-
根拠がどうしても見つからない → Not Given の可能性大
「根拠の線引き」を習慣化すると、FalseとNGの区別が格段にしやすくなります。
2. FalseとNGを間違えたときの復習法
練習中にFalseとNGを取り違えた場合は、次の2点を必ず確認してください。
-
本文に「逆の情報」が書かれていたか?
-
それとも情報がそもそも「欠けていた」のか?
この振り返りを繰り返すことで、「本文にある vs ない」の意識が自然に定着します。
3. 設問を断定表現に着目してチェックする
練習の際に「always」「never」「all」「must」などをハイライトしておくと、NGを見抜きやすくなります。本文がそこまで言い切っていない場合、答えはNGの可能性が高いと気づけるようになります。
4. NGだけを集中的に練習する
市販の問題集や過去問から「NGが含まれる問題」だけを抜き出して解くと、判断基準が鍛えられます。最初は難しく感じますが、数をこなすうちにFalseとNGの感覚がクリアになります。
5. 時間を区切って実戦形式で解く
試験本番では迷いすぎて時間を浪費することが一番のリスクです。練習段階から「1問にかける時間」を意識し、分からなければ根拠がない=NGと決める癖をつけておくと安心です。
まとめ
IELTSリーディングのTrue / False / Not Given 問題の中でも、特にNG(Not Given)は多くの受験者にとって難関です。しかし、判断のポイントはシンプルで、本文に情報があるかどうか だけに注目すれば迷いが減ります。
-
True: 本文と一致している
-
False: 本文に逆の情報がある
-
Not Given: 本文に情報が存在しない
特にFalseとNGの違いを意識して整理することが、得点力アップのカギです。
また、推測や背景知識ではなく「本文の根拠」をベースに判断する姿勢を徹底すれば、確実に正答率が上がります。
NG問題を得意にすれば、True / False / Not Given 全体での安定感が増し、リーディングスコア全体の底上げにつながります。日々の練習で「根拠があるかどうか」を常に確認する習慣をつけ、本番で自信を持ってNGを選べるようになりましょう。
FAQ:NG(Not Given)を見分ける実践コツ集
Not Given(NG)とFalseの違いは?
Falseは本文に「逆の情報」や「明確な矛盾」がある場合。NGは本文がその内容にまったく触れていない場合です。根拠の所在で判断しましょう。
NGを最速で見分けるチェックリストは?
- 設問キーワード(または言い換え)が本文に見当たらない
- 本文は話題に触れているが、設問の範囲・数量・条件を満たす情報が欠けている
- 断定語(all/always/never/only/must など)に対応する断定が本文にない
- 自分の常識や前提で補わないと判断できない
設問に断定表現(all/always/never)がある時のコツは?
本文が同じレベルで断定していないならNGの可能性が高いです。本文が一部事例や傾向しか述べていない場合は、範囲過剰ゆえにNGになり得ます。
本文に関連語はあるが結論が書かれていない場合は?
関連トピックに触れていても、設問の結論(因果・比較・数量・条件)が欠けていればNGです。部分情報のみ=NGの合図です。
パラフレーズ(言い換え)で見落とさないためには?
- 名詞・動詞の同義語、形容詞の程度変化(significant ⇔ major など)に注意
- 能動/受動、名詞化(decide ⇔ decision)など品詞変換を想定
- それでも核心の意味が本文に見つからなければNGを検討
背景知識が頭に浮かんで迷う時の対処は?
「本文に根拠があるか?」だけを基準にします。根拠が本文外(自分の知識)にあるならNGです。本文に戻って線引きで確認しましょう。
FalseとNGをよく取り違えます。復習方法は?
- 本文中の根拠候補に下線を引く
- そこに逆情報があるか(=False)、情報欠如か(=NG)を仕分け
- 「どの語句(数量・範囲・時制・条件)が不足していたか」をメモ
設問の語順は本文の情報順と連動しますか?
多くのT/F/NGセットは本文の流れに概ね沿います。順番ヒントは位置特定に有効ですが、必ずしも厳密一致ではない点に注意。
時間が足りない時、NGはどう処理する?
根拠探索を一定時間(例:40〜60秒)で打ち切り、見つからなければNG候補にマーク。後で時間があれば再確認する運用が効率的です。
「一部」「多くの」「ほとんど」など数量語の扱いは?
設問の数量(all/most/some)と本文の数量が一致しなければFalse、そもそも数量が示されていなければNGです。
例外句(except/unless/however)に気づけない時の対策は?
- 逆接・条件のシグナル語をハイライト(however, whereas, unless, except)
- 設問の断定と例外の有無を照合。例外に触れていなければNGの可能性
図表や注釈がある場合、NGの判定は?
本文・図表・キャプション全体が根拠の対象です。いずれにも該当情報がなければNG。図表だけにある情報は有効な根拠になります。
本文に一般論はあるが特定条件がない場合は?
設問が「特定の時期/地域/集団」に関する結論を問うのに、本文が一般論しかないならNGです。条件の欠落に注目。
練習でNG判定力を鍛える具体メニューは?
- 過去問からNGを含む設問だけを抽出し、根拠の有無を即時判定するスプリント練習
- 間違いノートに「不足していた情報の種類(数量・期間・原因・比較)」を分類記録
- 断定語・条件語のハイライトを習慣化