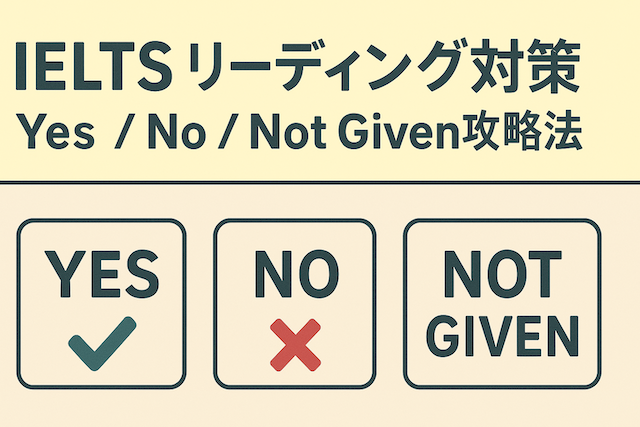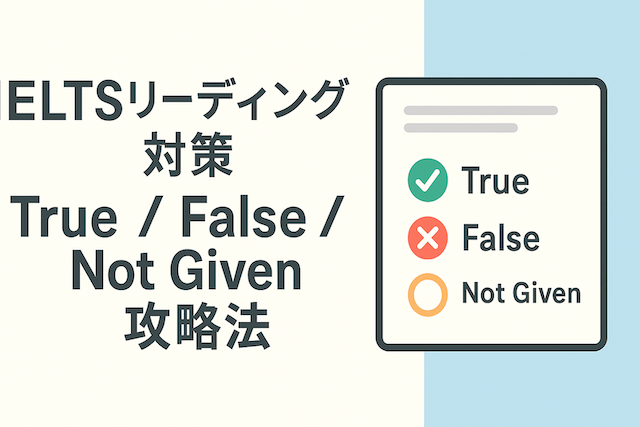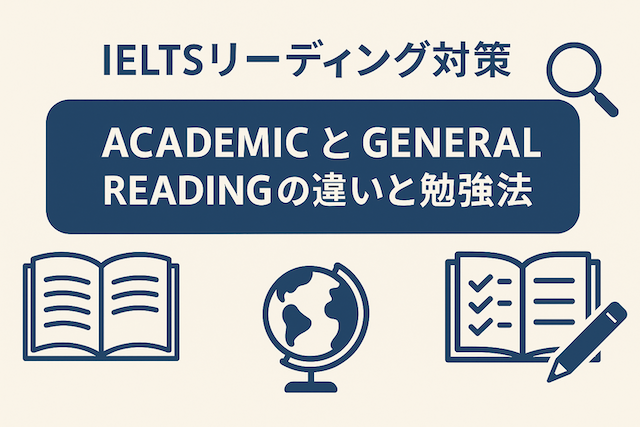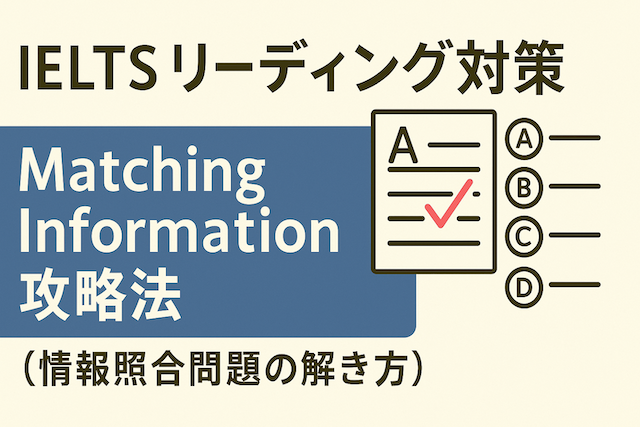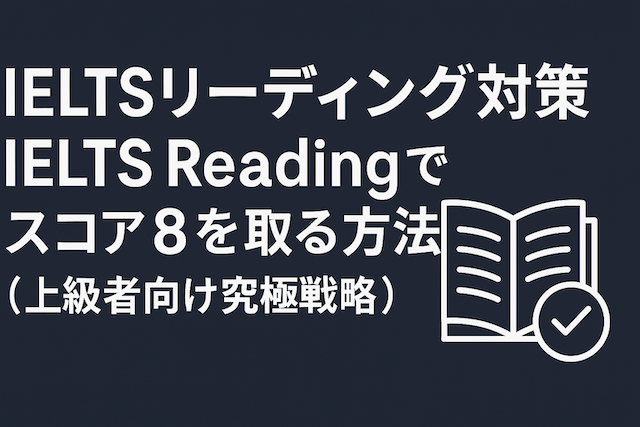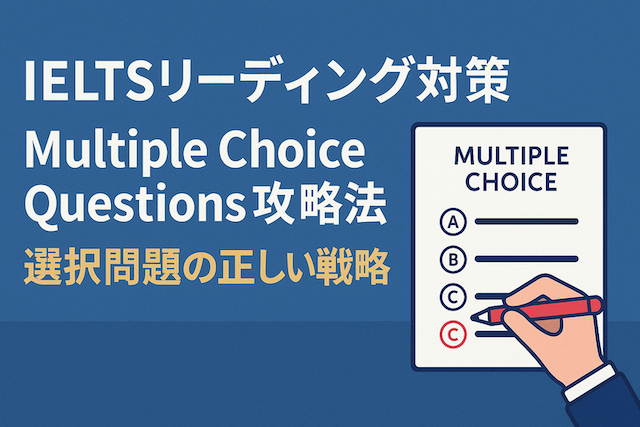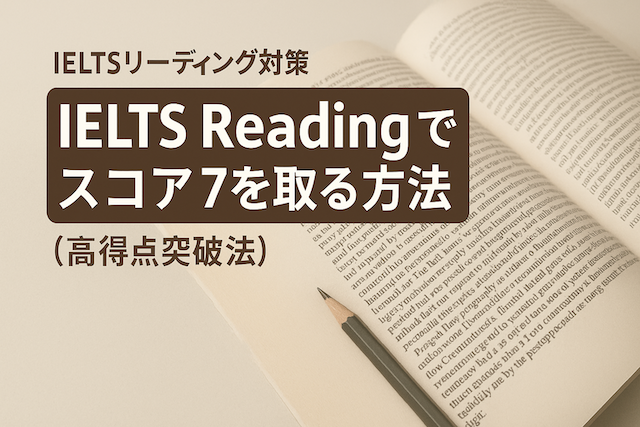目次
- IELTSリーディング対策:Yes/No/Not Given攻略法
- はじめに
- Yes/No/Not Givenの特徴
- True/False/Not Givenとの違い
- 解答手順のステップ
- よくある間違いと対策
- 実践練習のコツ
- まとめ
- FAQ:Yes/No/Not Given攻略法
- Yes/No/Not GivenはTrue/False/Not Givenと何が違いますか?
- Yes/No/Not Givenの基本的な判定基準は?
- Not Givenはどのように見分けますか?
- 設問の順序は本文の順序と対応しますか?
- 極端な表現(always, never, allなど)が出たらどう判断しますか?
- パラフレーズ(言い換え)にどう対応すれば良いですか?
- YesとNoを迷ったときの決め手は?
- 自分の背景知識は使っても良いですか?
- 効率的な解答手順は?
- 練習時にやるべき見直しは?
- 時間配分の目安は?
- ミスを減らすためのチェックリストはありますか?
- ミニ例題での判定のコツは?
- 同じ段落に根拠が見つからないときは?
IELTSリーディング対策:Yes/No/Not Given攻略法
はじめに
IELTSリーディングで多くの受験者を悩ませる設問のひとつが Yes/No/Not Given です。一見するとTrue/False/Not Givenと似ていますが、実は出題の意図や解き方が異なります。この問題では、事実の正誤ではなく、筆者の意見や主張 に一致しているかどうかを見抜く力が求められます。
「本文に答えが見つからない」「YesとNoの区別があいまいになる」というのは典型的な失敗例です。しかし、設問の特徴を正しく理解し、解答の手順を踏めば、安定して正答できるようになります。本記事では、Yes/No/Not Given問題を解くための考え方と実践的な攻略法をわかりやすく解説していきます。
Yes/No/Not Givenの特徴
Yes/No/Not Given問題は、リーディング本文に出てくる 筆者の主張や意見 に関する設問形式です。事実確認ではなく、筆者がどのように考えているか、賛成・反対・言及なしを判断する点が特徴です。
-
Yes = 設問文の内容が筆者の意見・主張と一致している場合
-
No = 設問文の内容が筆者の意見・主張と矛盾している場合
-
Not Given = 本文にその主張が書かれていない、または判断材料が不足している場合
重要なポイント
-
筆者の立場を理解する問題
→ 「筆者はこう考えている」と読み解く力が必要。 -
事実確認型ではない
→ True/False/Not Givenと異なり、客観的な事実ではなく「意見や立場」を軸に判断する。 -
本文に書かれていない場合はNot Given
→ 無理にYesかNoを選ばず、情報がなければNot Givenが正解。
True/False/Not Givenとの違い
IELTSリーディングの設問で混同しやすいのが、True/False/Not Given と Yes/No/Not Given です。見た目はよく似ていますが、実際には出題の意図が異なります。
True/False/Not Given
-
対象:本文中の「事実(Fact)」
-
True = 設問文の記述が本文の事実と一致している
-
False = 設問文が本文の事実と矛盾している
-
Not Given = 本文に事実が書かれていない
科学的な説明や歴史的な出来事など、客観的な情報 に基づいて判断する。
Yes/No/Not Given
-
対象:本文中の「筆者の意見や主張(Opinion/Claim)」
-
Yes = 設問文の意見が筆者の主張と一致している
-
No = 設問文の意見が筆者の主張と矛盾している
-
Not Given = 筆者がその点に触れていない
評論文や意見文で、筆者がどう考えているかを把握することが重要。
違いを一言でまとめると
-
True/False/Not Given → 「事実」についての確認
-
Yes/No/Not Given → 「筆者の意見」についての確認
解答手順のステップ
Yes/No/Not Given問題は、やみくもに本文を読むのではなく、手順を踏んで判断するのが正解への近道です。
ステップ1:設問文を確認する
-
設問文が事実確認ではなく「筆者の意見・主張」に関するものかを意識する。
-
キーワード(例:believes, claims, argues など)に注目。
ステップ2:本文で該当箇所を探す
-
設問は本文の順序通りに出題されることが多い。
-
設問文のキーワードを使って、対応する段落や文を特定する。
ステップ3:筆者の意見を読み取る
-
直接的な表現だけでなく、言い換えや示唆も含めて把握する。
-
筆者の立場(賛成・反対・中立)を明確に整理する。
ステップ4:設問文と比較する
-
意見が一致 → Yes
-
意見が反対 → No
-
どちらとも言えない/言及なし → Not Given
ステップ5:極端な表現に注意
-
“always” “never” “all” “only” などの絶対的な表現は、本文と矛盾しやすい。
-
本文が限定していないのに設問が断定している場合は、No か Not Given になる可能性が高い。
よくある間違いと対策
1. Not Givenを無理にYes/Noで答えてしまう
-
間違い例:「本文に直接は書いていないけど、きっとYesのはず」と推測してしまう。
-
対策:本文に情報がなければ潔く Not Given を選ぶ。推測や常識で補わない。
2. 自分の知識や常識で判断してしまう
-
間違い例:「一般的にはそうだからYesだろう」と考える。
-
対策:IELTSは本文に書かれた情報だけで判断する試験。背景知識は切り捨てる。
3. YesとNoを混同する
-
間違い例:筆者が明確に反対しているのに「言及していない」と考えてしまう。
-
対策:「筆者が賛成か反対か」を明確に見極める。反対意見なら迷わず No。
4. パラフレーズ(言い換え)を見逃す
-
間違い例:設問と本文の表現が違うため、同じ内容と気づかない。
-
対策:同義語や言い換え表現に慣れる。例:
-
“increase” ⇔ “go up”
-
“important” ⇔ “crucial / significant”
-
5. 絶対表現に惑わされる
-
間違い例:設問に “always” や “never” が含まれていると自動的にYesと判断する。
-
対策:本文に「例外なし」の表現がない場合、No や Not Given になる可能性が高い。
実践練習のコツ
1. 集中的にYes/No/Not Givenだけを解く
-
過去問や練習問題をジャンル別に分け、まずはこの設問形式に慣れる。
-
同じタイプを繰り返すことで「判断基準の感覚」が身につく。
2. 根拠を必ず確認する
-
正解を選んだら、本文のどの文が根拠になったのかを必ず確認する。
-
「この一文があるからYes」と説明できる状態が理想。
3. Not Givenの練習を強化する
-
受験者が最も苦手とするのがNot Given。
-
「本文に言及がない」ことを確認する練習を積み重ねると、迷いが減る。
4. パラフレーズに慣れる
-
設問と本文で同じ単語が使われないことが多い。
-
同義語リストを作って、実際に使われやすい言い換え表現を覚える。
5. 制限時間を意識する
-
Yes/No/Not Given問題は比較的短時間で解ける形式。
-
迷ったら長く時間をかけすぎず、次の問題に進む判断も大切。
まとめ
Yes/No/Not Given問題は、筆者の意見や主張 を読み取る力を試す設問です。True/False/Not Givenのように事実を確認する問題とは異なり、筆者の立場を正しく把握することが鍵となります。
-
Yes = 筆者の意見と一致
-
No = 筆者の意見と矛盾
-
Not Given = 筆者が言及していない
このルールを明確に理解し、パラフレーズへの対応や極端な表現への注意を徹底すれば、正答率を安定して高めることができます。
最後に大切なのは、本文の情報だけを根拠にする こと。背景知識や常識に引っ張られず、文章の中で判断する習慣をつけることで、難問にも落ち着いて対応できるようになります。
FAQ:Yes/No/Not Given攻略法
Yes/No/Not GivenはTrue/False/Not Givenと何が違いますか?
Yes/No/Not Givenは筆者の意見・主張に対する一致/不一致/非言及を判定します。一方、True/False/Not Givenは客観的事実の一致/不一致/非言及を判定します。
Yes/No/Not Givenの基本的な判定基準は?
- Yes:設問の主張が筆者の主張と一致
- No:設問の主張が筆者の主張と矛盾
- Not Given:本文に判断材料がない(筆者が言及していない)
Not Givenはどのように見分けますか?
本文を該当箇所まで精読しても、設問の主張を肯定・否定する直接的根拠が見つからない場合はNot Givenです。推測や一般常識で補わないことが重要です。
設問の順序は本文の順序と対応しますか?
多くの場合、設問は本文の流れに沿って出題されます。前の設問の根拠がある段落の近くに、次の設問の根拠があることが多いです。
極端な表現(always, never, allなど)が出たらどう判断しますか?
本文がそのレベルの断定をしていなければ、No または Not Given になりやすいです。本文に「例外なし」の明言があるかを確認しましょう。
パラフレーズ(言い換え)にどう対応すれば良いですか?
設問と本文は同じ語を使わないことが多いです。例:increase ⇔ go up、important ⇔ crucial/significant。同義語・反意語、因果の言い換え(because⇔due to)に慣れましょう。
YesとNoを迷ったときの決め手は?
筆者の立場が明確に賛成方向か反対方向かで判断します。ニュアンスが弱い・立場が曖昧なら、無理にYes/Noにせず本文の明示性を再確認し、該当しなければNot Givenを検討します。
自分の背景知識は使っても良いですか?
いいえ。IELTSは本文の情報に基づく読解力を測る試験です。外部知識で空所を補うと誤答の原因になります。
効率的な解答手順は?
- 設問で「筆者の意見」を問うていることを意識する。
- 設問のキーワードで本文の該当段落を特定。
- 筆者の立場を読み取り、設問の主張と比較。
- 一致=Yes、矛盾=No、言及なし=Not Given。
練習時にやるべき見直しは?
選択後に必ず本文の根拠文に下線を引き、なぜその選択になったかを一文で説明します。特にNot Givenは「どこまで読んでも根拠がない」ことを確認しましょう。
時間配分の目安は?
Yes/No/Not Givenは比較的短時間で解けます。1問あたり約60〜90秒を目安に、迷ったら印をつけて先に進み、最後に戻って再判定しましょう。
ミスを減らすためのチェックリストはありますか?
- 設問は「意見」か?(事実ではないか)
- 本文に断定があるか?(極端表現の確認)
- パラフレーズを見逃していないか?
- 根拠文が一つは明確に挙げられるか?
- 外部知識で補っていないか?
ミニ例題での判定のコツは?
例:設問「The author believes online learning can fully replace classroom education.」
本文「Online learning offers valuable flexibility, but it should complement classroom instruction rather than replace it.」
⇒ 筆者は「補完」であり「完全な代替」を否定しているので No。
同じ段落に根拠が見つからないときは?
設問の前後関係を手がかりに近い段落へ範囲を広げます。それでも見つからなければ推測せず、Not Givenの可能性を検討します。