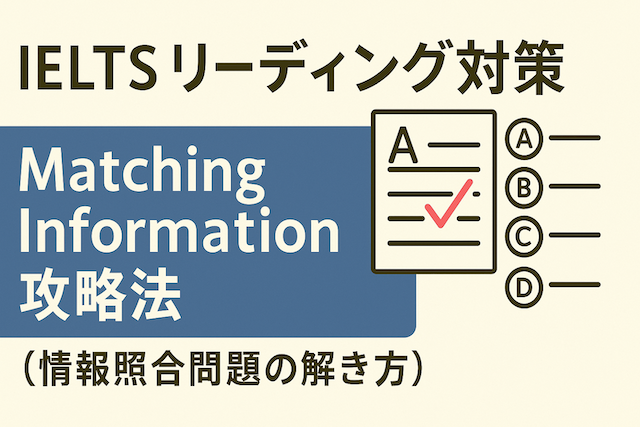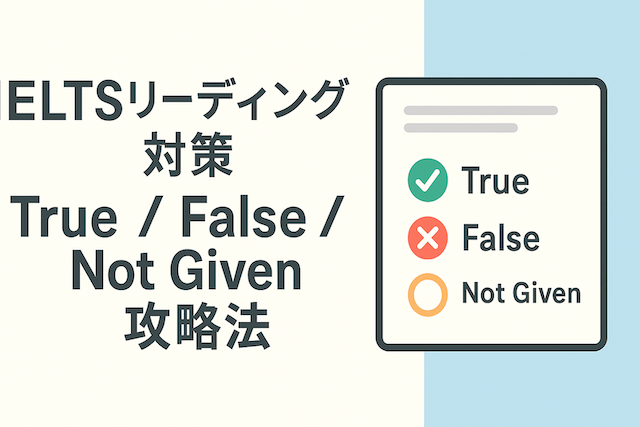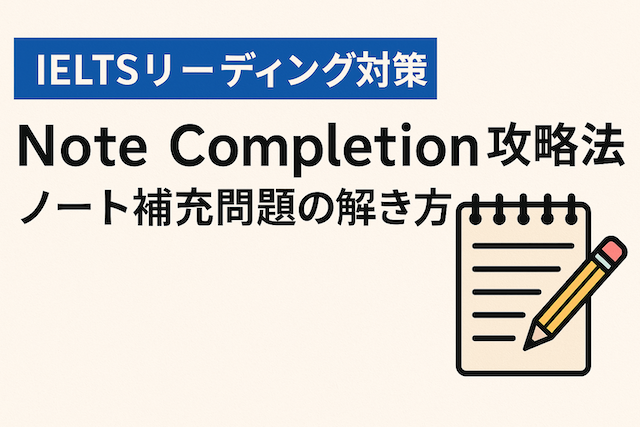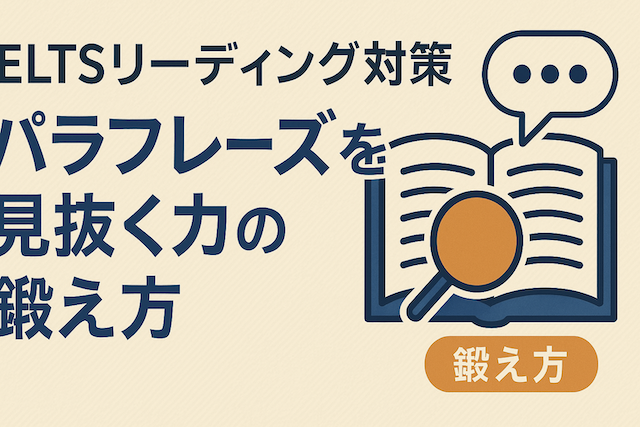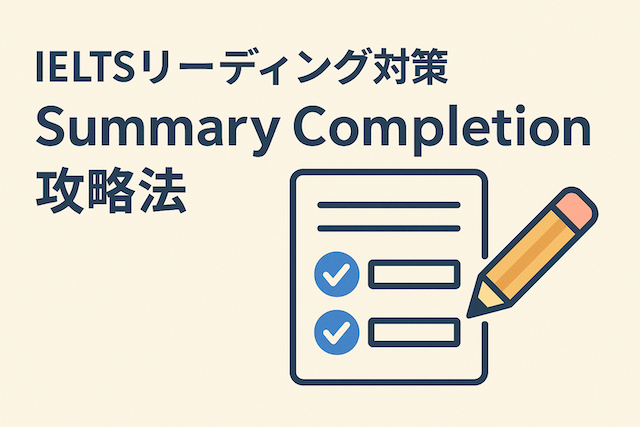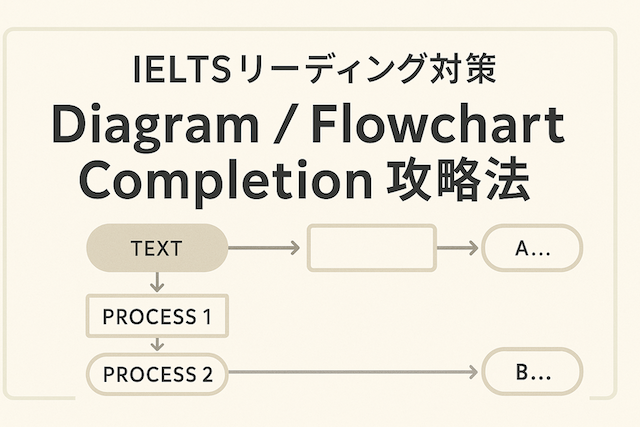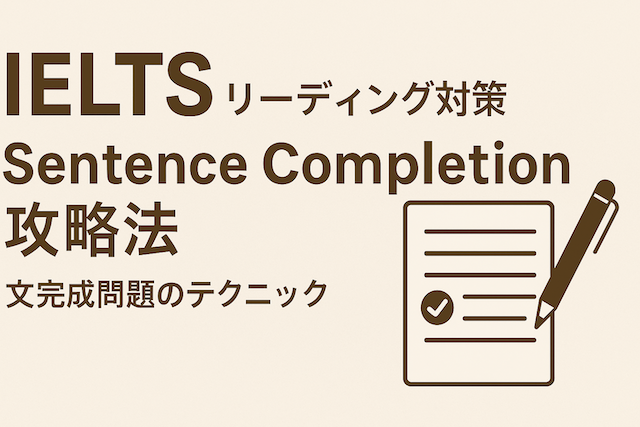目次
- IELTSリーディング対策: Matching Information攻略法(情報照合問題の解き方)
- はじめに
- Matching Informationとは?
- 難易度が高い理由
- 攻略のステップ
- 時間配分のコツ
- よくあるミス
- 練習方法
- まとめ
- Matching Information(情報照合問題)とは何ですか?
- Matching HeadingsやTrue/False/Not Givenと何が違いますか?
- 設問は本文の順番通りに並んでいますか?
- 同じ段落を複数回答に使っても大丈夫ですか?
- 時間配分の目安はどれくらいですか?
- 素早く該当箇所を見つけるコツは?
- よくあるミスと対策は?
- パラフレーズ(言い換え)にはどう対応すればよいですか?
- 段落のどの部分を優先して読みますか?
- 設問が難しくて決めきれない時は?
- 効率的な練習法はありますか?
- 本文を全部精読すべきですか?
- 語彙が弱いと解けませんか?
- 設問の「情報タイプ」はどう見分けますか?
- スコア向上のためにすぐ始められることは?
IELTSリーディング対策: Matching Information攻略法(情報照合問題の解き方)
はじめに
IELTSリーディングで頻出する問題タイプのひとつに「Matching Information(情報照合問題)」があります。これは文章の中から特定の情報を探し出し、設問と対応させる形式で出題されます。設問では「どの段落にこの事実や理由、例が書かれているか」を問われることが多く、本文の細かい情報を正確に読み取る力が必要とされます。
一見するとシンプルに見えますが、実際には設問と本文がそのまま同じ言葉で対応していることは少なく、多くの場合は**言い換え(パラフレーズ)**が用いられています。そのため、単語の一致だけで判断するのではなく、文脈を理解する読解力が求められます。
この問題は、解き方のコツを押さえれば得点源にしやすい一方で、効率的に解かないと時間を大きく消費してしまうリスクもあります。この記事では、Matching Information問題の特徴や解法ステップ、注意すべきポイントを整理し、実際の試験でスムーズに解答できるようになるための攻略法を解説します。
Matching Informationとは?
IELTSリーディングで出題される「Matching Information(情報照合問題)」は、受験者が文章の中に散りばめられた具体的な情報を正しく探し出せるかを試す問題形式です。
出題形式
-
設問は「次の情報はどの段落に含まれていますか?」という形で提示される。
-
段落はA, B, C…とラベル付けされており、設問番号ごとに対応する段落を選ぶ。
-
設問の内容は、人名・年代・研究結果・理由・具体例・定義など細かいディテールが中心。
特徴
-
段落全体の要旨ではなく、部分的な情報に焦点を当てる。
→ Heading問題のように「全体の主題」を問うのとは異なる。 -
1つの段落に複数の答えが含まれる場合もある。
-
設問と本文は「同じ表現」で登場せず、**言い換え(パラフレーズ)**されていることが多い。
例(イメージ)
-
設問:「実験が失敗した理由」
-
本文: “The attempt collapsed due to technical errors during the final stage.”
→ 設問の「理由(reasons for failure)」が本文では「collapsed due to technical errors」と言い換えられている。
このように、Matching Information問題は単なる単語検索ではなく、意味の対応関係を素早く見抜く力が問われる形式です。
難易度が高い理由
Matching Information問題は一見シンプルに見えますが、実際に解いてみると多くの受験者が時間を取られてしまいます。その理由は以下の通りです。
1. 言い換え(パラフレーズ)の多用
-
IELTSでは、設問文と本文が同じ単語で一致することはほとんどありません。
-
例:設問が「reasons for decline」となっていても、本文では「the causes of decrease」「the factors behind the reduction」といった言い換えが使われる。
-
このため、語彙力と同義表現への感度が求められます。
2. 答えが段落の一部にしか書かれていない
-
Heading問題のように段落全体の要旨ではなく、数行だけに答えが隠れているケースが多い。
-
そのため、段落をざっと読むだけでは見落としやすい。
3. 紛らわしい情報が含まれている
-
段落内には似たような事実や関連する情報が複数書かれていることがある。
-
設問に直接対応している情報を見極められず、誤った段落を選んでしまうことも多い。
4. 他の問題形式との混在
-
Matching Informationは、同じパッセージ内でTrue/False/Not GivenやMatching Headingsと一緒に出題されることが多い。
-
それぞれで読む観点が異なるため、頭の切り替えと時間管理が難しい。
5. 時間制限との戦い
-
リーディング全体は60分。その中で約40問を解かなければならない。
-
Matching Informationに時間をかけすぎると、後半の設問に影響が出てしまう。
以上の理由から、Matching Informationは「ただ読む」だけでは不十分で、効率的な戦略が必要になるのです。
攻略のステップ
Matching Information問題を効率よく解くには、行き当たりばったりで本文を読むのではなく、戦略的な手順を踏むことが重要です。以下のステップに沿って練習すると、正答率とスピードの両方が向上します。
1. 設問を先に読む
-
本文を読む前に設問を確認し、探すべき情報の種類を把握しておきましょう。
-
キーワード(人名、年代、専門用語、数字など)に印をつける。
-
設問が「理由」「結果」「定義」「例」など、どのタイプの情報を問うているのかを意識する。
2. 段落の概要をざっと把握する
-
本文に入ったら、まず各段落の冒頭文・結論部分を読んで、大まかなトピックを理解。
-
例:「この段落は研究の背景説明」「この段落は実験結果」などと頭の中でラベルを付ける。
-
この作業によって、設問に対応しそうな段落を絞り込みやすくなる。
3. パラフレーズを意識して読む
-
設問と本文は同じ言葉で出てくるとは限らない。
-
「increase → rise」「problem → issue」「researcher → scientist」など、よく使われる言い換えを意識する。
-
語彙力を鍛えるとともに、設問文と本文の意味的対応を見抜く練習を重ねることが大切。
4. 段落内をスキャンして確認
-
設問のキーワード、あるいは同義表現が現れそうな部分をスキャン読み。
-
数字・固有名詞・カタカナ語などは視覚的に見つけやすい。
-
該当箇所を見つけたら、前後の文を読んで「設問の意図」と合致するか確認する。
5. 1つの段落が複数回答になる可能性を忘れない
-
Matching Informationでは、同じ段落を複数の設問に使うこともある。
-
「一度使った段落は二度と使えない」と思い込まないこと。
6. 判断できない場合は仮置きする
-
時間を浪費しすぎないように、迷ったときは仮の答えを入れて次に進む。
-
後から他の問題を解く中でヒントが見つかることもある。
このステップを徹底することで、Matching Informationの正答率を安定させることができます。
時間配分のコツ
IELTSリーディングは60分で40問を解く必要があり、Matching Informationのような「情報探し型」の問題に時間をかけすぎると、後半の設問に支障が出ます。効率よく得点するためには、以下の時間管理の工夫が効果的です。
1. 1問あたりの目安時間を決める
-
Matching Informationは通常4〜6問程度。
-
1問あたり1〜1.5分以内で処理できるのが理想。
-
長くても2分以上はかけないように意識する。
2. 段落を精読しない
-
各段落を最初から最後まで読むと時間が足りなくなる。
-
「概要をつかむ → 必要な情報をスキャンする」という流れで処理する。
3. 設問順にこだわらない
-
設問は必ずしも本文の順序通りではない。
-
迷った問題は一旦飛ばして、解けるものから先に答えることで時間を節約できる。
4. キーワードを意識したスキャンで時間短縮
-
数字、固有名詞、日付、人名、専門用語は最も探しやすい手がかり。
-
設問を見た時点で、本文内でどこにありそうか予測してからスキャンする。
5. 最後の見直し時間を確保する
-
すべての設問を解いたあと、必ず数分を残して見直しを行う。
-
特にMatching Informationは「仮置き解答」を修正できるチャンスになる。
Matching Informationは精読よりも「要点の抽出」と「効率的なスキャン」が鍵です。時間配分を徹底することで、他の問題形式に余裕を持って取り組めます。
よくあるミス
Matching Information問題では、時間的プレッシャーや設問のトリックにより、受験者が同じような誤りを繰り返すことが多いです。以下に典型的なミスと、その回避方法をまとめます。
1. 表面的な単語一致に頼る
-
設問と本文に同じ単語が登場すると、それが答えだと早合点してしまう。
-
実際には設問の意図と本文の文脈がずれているケースが多い。
-
対策: 単語の一致だけでなく、文全体の意味が一致しているか確認する。
2. 段落を読み飛ばして見落とす
-
「この段落は関係なさそう」と思い込み、答えを飛ばしてしまう。
-
実際には段落の一文だけが答えに対応している場合が多い。
-
対策: 段落を完全に無視せず、キーワードが出ていないか最低限スキャンする。
3. 部分的な情報だけで判断する
-
本文の一部が設問と似ているため、前後の文脈を確認せずに答えてしまう。
-
設問が求めているのは「理由」なのに、本文には「結果」しか書かれていない、というケースなど。
-
対策: 該当箇所を見つけたら、必ず前後の文も読んで文脈を確認する。
4. 「段落は1回しか使えない」と思い込む
-
実際には1つの段落に複数の答えが含まれることがある。
-
この誤解によって、正しい答えを避けてしまうことがある。
-
対策: 段落の再利用は可能だと意識しておく。
5. 時間をかけすぎて他の問題を圧迫する
-
1問にこだわりすぎると、リーディング全体のバランスを崩す。
-
対策: 決めた制限時間(1〜1.5分)を過ぎたら仮置きして次に進む。
これらのミスを防ぐためには、**「意味を理解すること」と「時間管理」**の両立が欠かせません。
練習方法
Matching Informationは、問題形式に慣れれば必ず得点源にできるタイプです。効率的にスキルを伸ばすための練習方法を紹介します。
1. 過去問・模試で「根拠探し」を徹底
-
問題を解いたあと、必ず本文のどの文が答えの根拠になったかに線を引く。
-
設問の表現と本文の表現がどのように言い換えられているかを確認。
-
例:設問「reasons for failure」→ 本文「collapsed due to technical errors」
2. パラフレーズ集を作る
-
解いた問題で見つけた言い換え表現をノートや単語帳にまとめる。
-
「increase → rise → grow」「problem → issue → difficulty」などをストックしておく。
-
繰り返すうちに「IELTSでよく使われるパターン」が自然と身につく。
3. 制限時間を意識したトレーニング
-
1問にかける時間は1〜1.5分以内を目安に。
-
模試や実際の過去問演習でストップウォッチを使い、時間感覚を養う。
-
最初は時間オーバーでも、徐々にスピードが上がっていく。
4. 読解力の基礎を強化する
-
IELTSの長文は学術的な内容が多いため、普段から英字新聞・学術記事・雑誌を読む習慣をつけると効果的。
-
内容を要約したり、重要な事実や例をピックアップする練習はMatching Information対策に直結する。
5. 「段落のラベル付け」練習
-
本文を読むときに、各段落のトピックを一言でメモする(例:「背景説明」「研究の方法」「実験結果」)。
-
設問を見たときに「これはこの段落っぽい」と予測できるようになる。
このように、単なる問題演習だけでなく「言い換えへの慣れ」「段落理解力」「時間管理力」を総合的に鍛えることが、Matching Information攻略のカギとなります。
まとめ
IELTSリーディングにおけるMatching Information(情報照合問題)は、文章中の細かい情報を正確に探し出す力を問う問題形式です。一見シンプルに見えますが、設問と本文の言葉がそのまま一致しないため、パラフレーズへの対応力と段落の要点を素早く見抜く力が必要です。
攻略のポイントは次の通りです。
-
設問を先に読み、キーワードと情報の種類(理由・結果・例など)を把握する
-
段落の冒頭と結論を押さえて、大まかなトピックを頭に入れる
-
単語一致に頼らず、言い換え表現を意識して答えを探す
-
段落を再利用できることを忘れない
-
1問に時間をかけすぎず、解けるものから先に進める
さらに、過去問を使って「答えの根拠に線を引く」練習や、見つけたパラフレーズをストックしていくことで、実戦でのスピードと正確性が向上します。
Matching Informationは慣れてしまえば大きな得点源にできます。普段の練習から戦略的に取り組み、本番では効率よく解答できるように準備していきましょう。
Matching Information(情報照合問題)とは何ですか?
段落(A, B, C…)の中から、設問で問われた具体的な情報(事実・理由・例・定義・年代・人名など)が書かれている段落を特定する問題形式です。段落の要旨ではなく、部分的な情報を素早く正確に見抜く力が求められます。
Matching HeadingsやTrue/False/Not Givenと何が違いますか?
- Matching Headings:段落全体の主題(要旨)を対応させる。
- True/False/Not Given:設問文の主張と本文の内容が一致するか判断する。
- Matching Information:段落内の特定情報(点)を探して照合する。
設問は本文の順番通りに並んでいますか?
必ずしも順番通りではありません。設問の並びと本文の情報位置がズレることがあるため、設問順に拘らない解き方が有効です。
同じ段落を複数回答に使っても大丈夫ですか?
可能です。Matching Informationでは、1つの段落が複数の設問に該当することがあります。「一度使った段落は使えない」という制約はありません。
時間配分の目安はどれくらいですか?
1問あたり1〜1.5分を目安にし、最大でも2分を超えないようにしましょう。迷ったら仮置きして先に進み、最後に見直し時間を確保します。
素早く該当箇所を見つけるコツは?
- 人名・年代・数字・固有名詞など視覚的手がかりを優先してスキャンする。
- 設問の情報タイプ(理由・結果・定義・例)を意識し、該当しやすい文(因果や例示)を狙う。
- 本文では言い換え(パラフレーズ)が多い点を前提に読む。
よくあるミスと対策は?
- 単語一致に頼る:文脈が一致しているか前後の文も読む。
- 段落の読み飛ばし:関係なさそうでも最低限のスキャンは行う。
- 部分読みで早合点:該当文の前後を確認して「理由・結果」などの種別を照合する。
- 段落は1回だけの思い込み:再利用可と覚えておく。
- 時間超過:上限時間を決め、超えたら仮置き。
パラフレーズ(言い換え)にはどう対応すればよいですか?
過去問で見つけた言い換えをノート化し、同義語・類義表現のパターンを蓄積します。例:increase → rise / grow、problem → issue / difficulty、reasons for → causes of / factors behind など。
段落のどの部分を優先して読みますか?
まずは段落の冒頭文と結論文で概要を把握し、次に設問の手がかり(キーワードや同義表現)が出やすい文(因果・対比・例示の文)をスキャンします。
設問が難しくて決めきれない時は?
時間をかけすぎないために仮置きし、他の設問を解く中でヒントが見つかったら戻って修正します。最後の見直し時間を必ず確保しましょう。
効率的な練習法はありますか?
- 解答後に根拠の本文箇所に線を引く(検証習慣)。
- パラフレーズ帳を作り、頻出の言い換えをストック。
- タイムトライアルで1問1〜1.5分の感覚を体に入れる。
- 各段落に一言ラベル(背景・方法・結果など)を付ける練習。
本文を全部精読すべきですか?
いいえ。精読は時間オーバーの原因です。概要把握 → スキャン → 前後確認の順で効率的に該当情報を特定しましょう。
語彙が弱いと解けませんか?
語彙は有利ですが、構文と文脈の手がかり(因果・対比・例示)を掴めれば対応可能です。語彙強化と並行して、言い換え認識と段落構造の把握を鍛えましょう。
設問の「情報タイプ」はどう見分けますか?
設問の動詞・名詞に注目します。reasons(理由)/ results(結果)/ definition(定義)/ example(例)/ method(方法)/ evidence(根拠)など、求められる情報の性質を先に意識して本文を探すと命中率が上がります。
スコア向上のためにすぐ始められることは?
- 過去問1セットで根拠マーキング+パラフレーズ抽出を必ず実施。
- 毎回の演習を時間制限付きにする(1問1〜1.5分)。
- 段落ラベル付けのミニ練習を日課化する(3段落だけでもOK)。