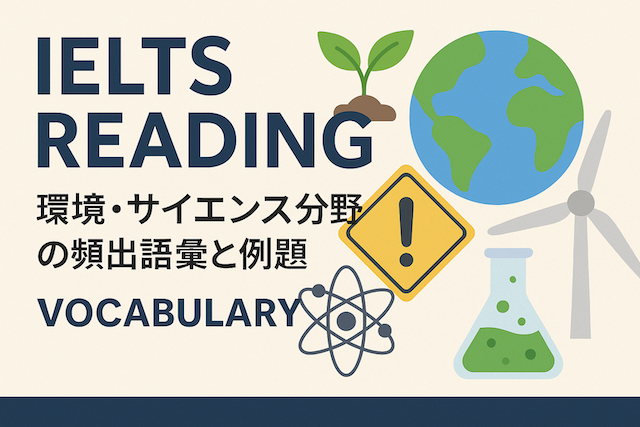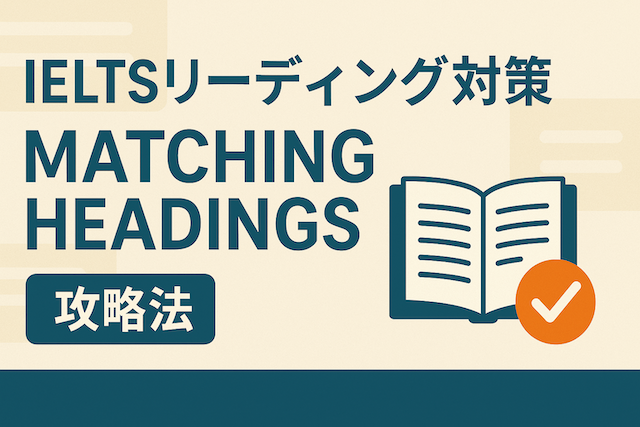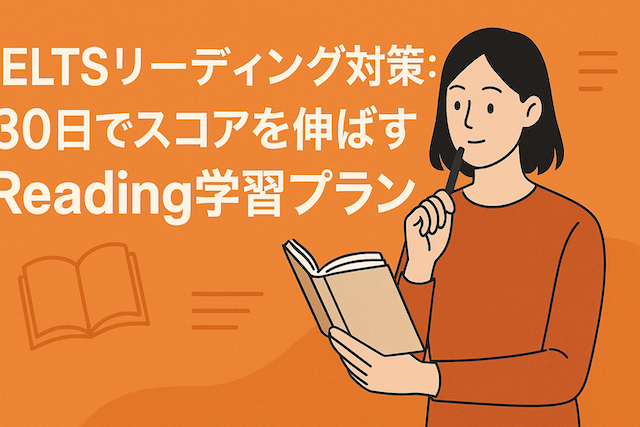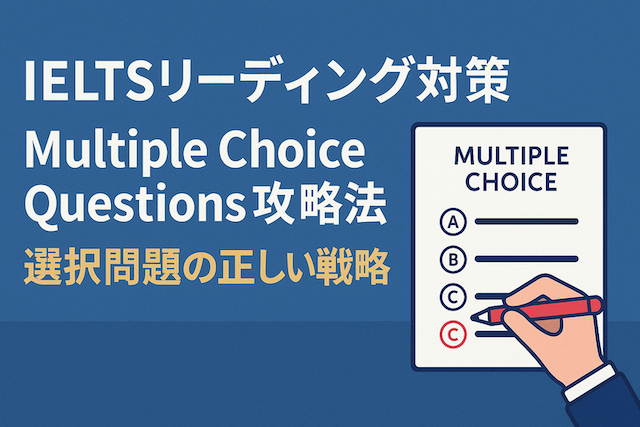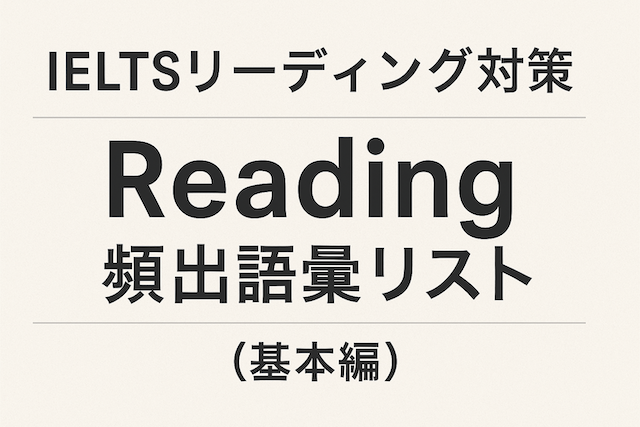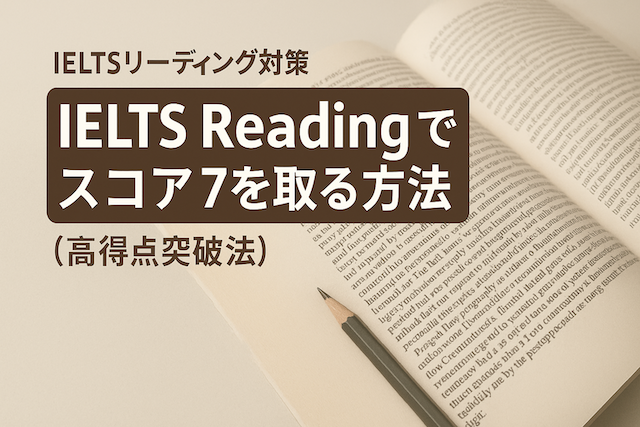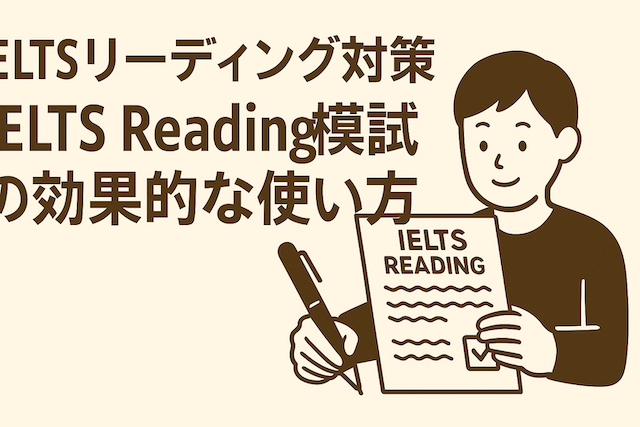目次
- IELTSリーディング対策: 環境・サイエンス分野の頻出語彙と例題
- はじめに
- 環境・サイエンス頻出語彙リスト
- 語彙の使い方:例文で確認
- IELTSリーディング例題(模擬)
- 学習アドバイス
- まとめ
- FAQ:環境・サイエンス分野の頻出語彙と例題
- 環境・サイエンス分野の語彙はどれくらい覚えるべき?
- 同義語や言い換えへの対策は?
- 未知語が出たときの読み方は?
- True/False/Not Given(TFNG)のコツは?
- 時間配分はどうすべき?
- 環境・サイエンス特有の設問で注意点は?
- 語彙学習は暗記と読解のどちらを優先?
- 効果的な練習素材は?
- Not Givenを減らすには?
- バンド7+を狙う語彙の伸ばし方は?
- 語彙テストの自作方法は?
- 環境分野とサイエンス分野の読解の違いは?
- 数値・割合の言い換えに弱いです
- 語彙が多すぎて覚えられません
- 学習計画のサンプルは?(2週間)
IELTSリーディング対策: 環境・サイエンス分野の頻出語彙と例題
はじめに
IELTSリーディングでは、学術的なテーマを扱う文章が頻繁に登場します。その中でも特に「環境」と「サイエンス」は出題率が高く、スコアアップを狙う上で避けて通れない分野です。気候変動や生態系の保護、科学的実験や理論などは、ニュース記事や学術雑誌に限らず、IELTSのリーディングパッセージでも繰り返し取り上げられます。
この分野に関連する語彙は、日常会話ではあまり使わない専門的なものが多いため、知らないまま試験に臨むと内容理解に時間がかかり、解答のスピードが落ちてしまいます。逆に、重要な語彙を事前に整理しておけば、文章の主旨を早くつかみ、設問の意図も理解しやすくなります。
本記事では、環境・サイエンス分野でよく出てくる語彙を一覧で紹介し、さらに例文や模擬問題を通して実際の使われ方を確認します。語彙を「知っている」にとどめず、「読んで理解できる」状態にまで高めることを目指しましょう。
環境・サイエンス頻出語彙リスト
IELTSリーディングにおいて、環境や科学分野に関連する語彙は、文章の理解に直結します。ここでは、テーマ別に重要単語をまとめました。意味だけでなく、文脈と一緒に覚えることで記憶が定着しやすくなります。
環境関連の語彙
-
sustainable(持続可能な)
-
renewable energy(再生可能エネルギー)
-
conservation(保護・保存)
-
climate change(気候変動)
-
pollution(汚染)
-
biodiversity(生物多様性)
-
ecosystem(生態系)
-
deforestation(森林破壊)
-
carbon footprint(二酸化炭素排出量)
サイエンス関連の語彙
-
experiment(実験)
-
hypothesis(仮説)
-
data analysis(データ分析)
-
theory(理論)
-
laboratory(研究室)
-
innovation(革新)
-
genetics(遺伝学)
-
evolution(進化)
-
scientific evidence(科学的証拠)
ポイント:これらの単語は文章中で同義語や言い換え表現に置き換えられることが多いため、synonym(同義語)もあわせて確認しておくと有効です。
語彙の使い方:例文で確認
単語は意味だけでなく、実際にどのように文中で使われるのかを知ることが重要です。IELTSリーディングでは、語彙が「言い換え」や「別の文脈」で出題されることが多いため、例文を通じて理解を深めておきましょう。
-
Climate change is largely caused by human activities such as deforestation and the burning of fossil fuels.
(気候変動は主に森林破壊や化石燃料の燃焼といった人間の活動によって引き起こされている。) -
The hypothesis was tested through several experiments conducted in the laboratory.
(その仮説は研究室で行われた複数の実験によって検証された。) -
Renewable energy sources such as solar and wind power are essential for a sustainable future.
(太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、持続可能な未来に不可欠である。) -
Biodiversity loss has a direct impact on ecosystems and can threaten human survival.
(生物多様性の喪失は生態系に直接的な影響を与え、人類の生存を脅かす可能性がある。)
ポイント:例文を読みながら、自分でも音読してみると、文の流れや使い方が自然に身につきます。
IELTSリーディング例題(模擬)
実際のIELTSリーディングでは、文章中に環境やサイエンス分野の語彙がちりばめられ、設問ではその理解が問われます。以下は短い模擬問題の例です。
問題文(抜粋)
Many scientists argue that biodiversity is crucial for maintaining a balanced ecosystem. However, rapid deforestation and pollution are threatening various species across the globe. To address climate change, governments are investing more in renewable energy and conservation projects.
設問例
-
What do scientists believe is important for maintaining ecosystems?
-
What are the two major threats mentioned in the passage?
-
What measures are governments taking to fight climate change?
解答例
-
Biodiversity
-
Deforestation and pollution
-
Investing in renewable energy and conservation projects
ポイント:本文のキーワードが設問では言い換えや要約の形で問われることが多いため、本文を正確に理解する力が求められます。
学習アドバイス
環境・サイエンス分野のリーディング対策を効果的に進めるためには、以下の学習法がおすすめです。
1. 語彙を文脈で覚える
単語リストだけで覚えるのではなく、必ず例文や記事の中で出てくる形で学習しましょう。IELTSでは同義語の置き換えが多いため、周辺の表現と一緒に理解しておくことが重要です。
2. 英語ニュースや記事を読む
BBC、National Geographic、Scientific Americanなどのニュースや雑誌を活用すると、実際に出題されやすいテーマや言い回しに触れられます。
3. 設問形式を意識して練習する
「True/False/Not Given」「Heading Matching」「Summary Completion」など、IELTS特有の設問形式に慣れることが必要です。同じ語彙が設問では別の言い回しになることに注意しましょう。
4. 自分で要約練習をする
環境や科学に関する短い記事を読み、英語で2〜3文にまとめてみると、キーワードを素早く拾う練習になります。
ポイント:単語暗記に終始せず、「読む → 理解する → 設問に答える」まで一連の流れを意識することで、本番での実力発揮につながります。
まとめ
IELTSリーディングでは、環境やサイエンス分野のテーマが頻繁に出題されます。これらのトピックは専門的な語彙が多く含まれるため、事前に頻出単語を押さえておくことで、文章の理解が格段にスムーズになります。
-
頻出語彙の習得は、文章理解のスピードを上げる近道。
-
例文や実際の記事を通じて、語彙を文脈とともに定着させる。
-
模擬問題や要約練習で、知識を実践的に使える力に変える。
語彙力を強化し、文章を効率的に読み解く練習を重ねれば、リーディングスコアの安定した向上が期待できます。今日から少しずつ、環境・サイエンス分野の英語に触れて慣れていきましょう。
FAQ:環境・サイエンス分野の頻出語彙と例題
環境・サイエンス分野の語彙はどれくらい覚えるべき?
まずは頻出の基礎語彙200語を目安にし、分野別(環境・エネルギー・生態系・研究方法・データ分析)で20〜40語ずつ増やしてください。暗記は段階的に行い、例文とコロケーション(例:renewable energy policy、conduct an experiment)で定着させます。
同義語や言い換えへの対策は?
設問は本文の語をそのまま使わず、paraphrase(言い換え)で問うことが多いです。語彙帳には必ず主な同義語・反意語を併記し、ミニ辞書を作成しましょう(例:conservation=preservation、protection)。
未知語が出たときの読み方は?
語源・接頭辞/接尾辞(bio-、-logy、-ation)で推測し、前後の定義・具体例・対比などの手掛かり(シグナル)を利用します。固有名詞や専門用語は多くが説明付きで登場します。
True/False/Not Given(TFNG)のコツは?
True=本文が明言、False=本文が明確に否定、Not Given=本文に必要情報が欠落。推測で埋めず、本文の情報量で判断します。some/all、may/mustなど数量・確実性の語に注意。
時間配分はどうすべき?
各パッセージ約20分を目安に、スキミング(2〜3分)→設問把握(1〜2分)→本文精読&根拠探し(12〜14分)→見直し(2分)。難化を感じたら設問タイプを先に解けるものから進めます。
環境・サイエンス特有の設問で注意点は?
データ・研究手順に関するSummary/Flow-chart、見出し一致では段落の主眼(原因・結果・対策・方法)を特定。グラフ・数値の言い換え(decline=fall、by 30%など)に敏感になること。
語彙学習は暗記と読解のどちらを優先?
両輪ですが、優先度は「文脈での語彙運用」。単語→例文→短文要約の順でアウトプットすると定着率が上がります。週次でミニテスト(英英定義→語、コロケーション穴埋め)を実施。
効果的な練習素材は?
環境報告や科学記事(学術的だが一般向けの媒体)を選び、1本を「精読+要約+言い換え抽出」まで行うのが理想。過去問は設問タイプごとに分解し、弱点タイプを集中反復。
Not Givenを減らすには?
本文にない情報を常識で補わないこと。設問文の主語・条件・範囲に線を引き、本文の該当箇所に一致・不一致・欠落の三択でマークしてから選択肢を確定します。
バンド7+を狙う語彙の伸ばし方は?
基礎200語→アカデミック語彙(AWL)→コロケーション強化の順。類義語のニュアンス差(mitigate vs alleviate、robust evidence など)を例文で整理し、要約タスクで能動運用します。
語彙テストの自作方法は?
- 記事からキーワードを抽出(見出し・定義・因果接続詞を目安)。
- 英英定義→語、語→同義語、語→コロケーションの三形式で各5問。
- 翌日・1週後・1か月後に再テスト(遅延反復)。
環境分野とサイエンス分野の読解の違いは?
環境記事は「現状→原因→影響→対策」の構成が多く、評価言語(問題視・推奨)が頻出。サイエンス記事は「仮説→方法→結果→解釈」の研究レポ型が多く、用語定義と受動態が増えます。
数値・割合の言い換えに弱いです
increase by 20%(20%増える)とincrease to 20%(20%になる)を区別。twofold=double、one in five=20% など頻出表現をカード化しましょう。
語彙が多すぎて覚えられません
週40〜60語に絞り、1セットを「意味→例文→要約→ミニテスト」で回します。不要語は思い切って削除し、試験頻度・言い換え多さ・自分の弱点の3軸で優先度を決めます。
学習計画のサンプルは?(2週間)
- Day1–3:基礎語彙(環境)+コロケーション練習+TFNG 10問
- Day4–6:基礎語彙(サイエンス)+要約練習(100語×2本)
- Day7:過去問1セット(復習日)
- Day8–10:言い換え強化(見出し一致・Summary Completion)
- Day11–13:模試1セット×2、誤答分析
- Day14:弱点タイプ総復習+語彙再テスト