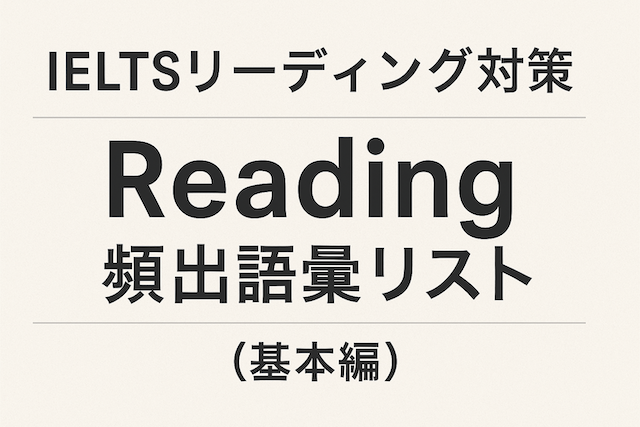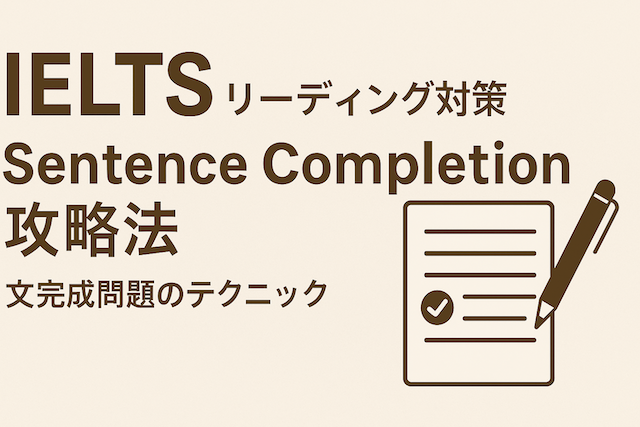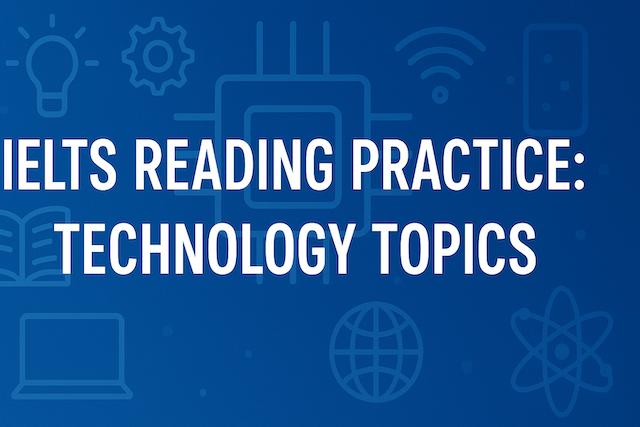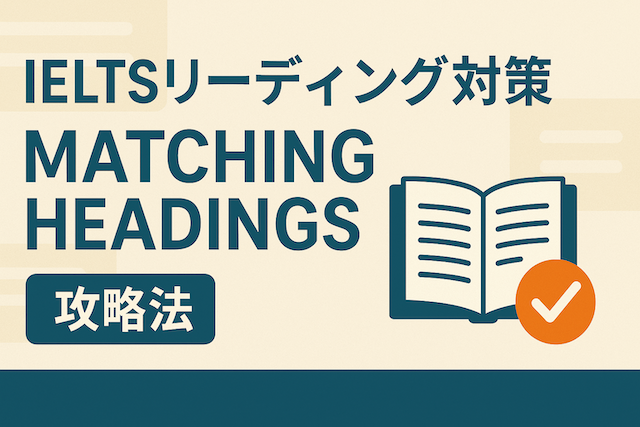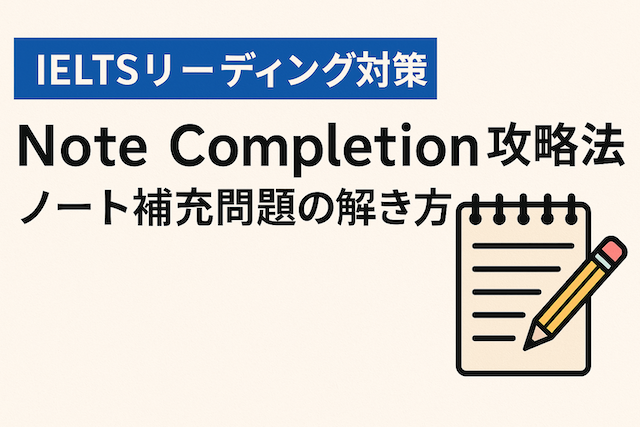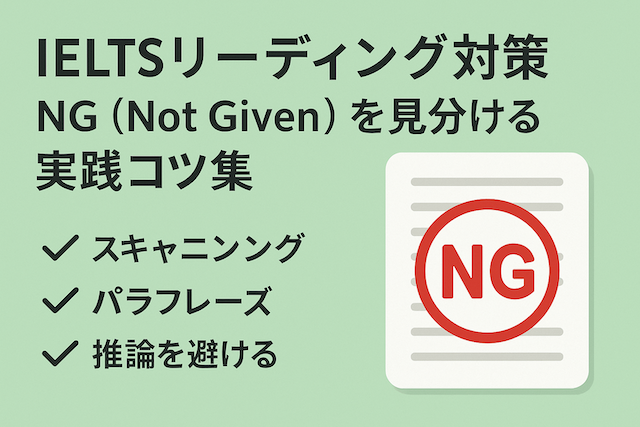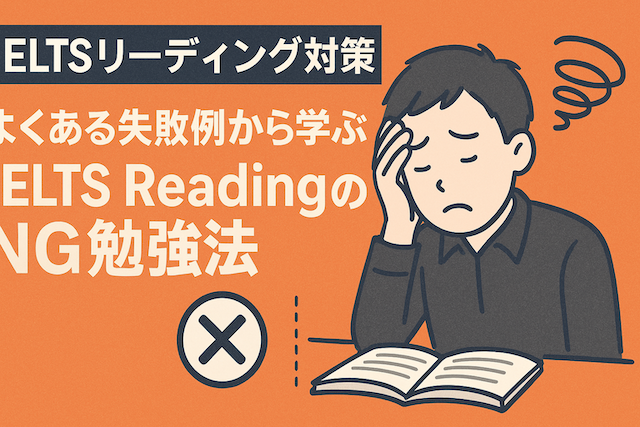目次
- IELTSリーディング対策: Reading頻出語彙リスト(基本編)
- はじめに
- なぜ頻出語彙を押さえることが重要なのか
- 頻出語彙リスト(基本編)
- 効率的な覚え方
- まとめ
- FAQ:Reading頻出語彙リスト(基本編)
- このFAQの目的は?
- 頻出語彙とは何を指しますか?
- 何語くらいを目安に学べば良いですか?
- 効率よく覚えるコツは?
- パラフレーズ対策はどうすれば良いですか?
- 辞書は英英と英和どちらを使うべき?
- 接頭辞・語源は学ぶべき?
- British/Americanの綴りは気にする?
- 単語テストはどう設計する?
- 推奨の学習サイクルは?(1日の例)
- よくある失敗は?
- 進捗はどう測る?
- リーディング以外にも効果はありますか?
- どの順番で学べば良い?(優先順位)
- 未知語に出会った時の対処法は?
- 応用編に進むタイミングは?
IELTSリーディング対策: Reading頻出語彙リスト(基本編)
はじめに
IELTSリーディングで多くの受験者がつまずく最大の理由は、「知らない単語が多すぎて本文が理解できない」ことです。長文読解の問題は一見すると複雑に見えますが、実際には頻出する単語や表現のパターンが決まっており、それを押さえておくかどうかで理解度は大きく変わります。
たとえば、「increase(増加する)」や「significant(重要な)」のような基本的な学術語は、どの分野のトピックでも繰り返し登場します。さらに、設問と本文では同じ意味を別の言葉で言い換えることが多いため、語彙を幅広く知っているほど正解にたどり着きやすくなります。
この「基本編」では、まずリーディングに必須の基礎語彙をジャンル別に整理しました。はじめてIELTSの勉強を始める方や、リーディングで「語彙力不足」を感じている方は、このリストを学習の出発点として活用してください。
なぜ頻出語彙を押さえることが重要なのか
IELTSリーディングは、単なる単語の暗記テストではありません。しかし、頻出語彙を知っているかどうかで理解スピードと正答率が大きく変わります。
-
文脈理解がスムーズになる
知らない単語が出てくると、そのたびに意味を推測する必要があり、読むスピードが落ちてしまいます。逆に、よく出る基本語彙を知っていれば、内容をスムーズに追うことができます。 -
言い換え表現に対応できる
IELTSでは「本文:significant」「設問:important」のように、同じ意味を異なる語で表現することが頻繁にあります。頻出語彙を押さえておくことで、この“パラフレーズ”に対応しやすくなります。 -
設問タイプごとの戦略に役立つ
True/False/Not Given や Matching Headings の問題では、キーワードを素早く見抜く力が必要です。基礎的な語彙を知っていると、どこを探せばいいかの判断が早くなります。 -
スコア全体の底上げにつながる
リーディングだけでなく、ライティングやリスニングにも同じ語彙が出てくるため、語彙力の強化はIELTS全体のスコア改善につながります。
つまり、頻出語彙は「読むための道具」であり、最小の努力で最大の成果を出すための必須アイテムなのです。
頻出語彙リスト(基本編)
1. 学術的な基本語彙(Academic Word Listから抜粋)
リーディング本文に必ず登場するといってよい学術用語。設問でも言い換えられて出やすい。
-
analyze(分析する)
-
approach(取り組み方、方法)
-
assess(評価する)
-
concept(概念)
-
data(データ)
-
evidence(証拠)
-
factor(要因)
-
issue(問題、論点)
-
method(方法)
-
significant(重要な)
2. 数値・変化を表す単語
グラフや統計、傾向を扱う文章で頻出。特にライティングTask 1とも重複して役立つ。
-
increase(増加する)
-
decrease(減少する)
-
fluctuate(変動する)
-
proportion(割合)
-
trend(傾向)
-
stable(安定した)
3. 意見・論理展開でよく出る単語
議論型のトピック(教育、社会問題、科学分野など)に登場。設問のパラフレーズにも多用される。
-
claim(主張する)
-
argue(論じる)
-
support(支持する)
-
oppose(反対する)
-
justify(正当化する)
-
controversial(議論を呼ぶ)
4. 時間・因果関係を示す単語
因果関係をつかむことで文章の構造が理解しやすくなる。
-
cause(原因)
-
effect(効果)
-
result(結果)
-
due to(〜のために)
-
therefore(したがって)
-
consequence(結果)
5. 環境・社会分野で頻出する単語
リーディングで定番のテーマ。環境・人口・教育関連の単語は特に出題率が高い。
-
pollution(汚染)
-
resource(資源)
-
population(人口)
-
urban(都市の)
-
rural(田舎の)
-
technology(技術)
-
education(教育)
このリストは「最低限押さえるべき基本単語集」です。暗記よりも、実際の文章で遭遇したときに即座に理解できることを目指すのが効果的です。
効率的な覚え方
1. カテゴリーごとに覚える
単語をバラバラに覚えるのではなく、「学術語」「数値表現」「因果関係」など意味的にまとまりのあるグループで覚えると記憶に残りやすくなります。
2. 例文と一緒に学ぶ
単語単体ではなく、実際の文脈の中で使われている例文を通して学ぶのが効果的です。たとえば、
-
The population of the city increased significantly in the last decade.
こうした例文ごと覚えると、実際の試験で意味を取りやすくなります。
3. 同義語・言い換えに注目する
IELTSは「本文」と「設問」で違う単語を使うことが多いです。
例:
-
significant ↔ important
-
increase ↔ rise ↔ go up
-
result ↔ outcome ↔ consequence
同じ意味を複数の単語で理解できるようにすることが必須です。
4. 過去問や模試で“既知化”する
暗記だけで終わらせず、実際の過去問や模試を解く中で出てきた単語を確認しましょう。1度出会った単語を「既知の単語」に変えていくことで、語彙力が実力になります。
5. 毎日の少しずつの積み重ね
一度に100語を覚えようとするより、毎日10〜15語を確実に定着させる方が効果的です。短時間でも継続が最大の成果を生みます。
まとめ
IELTSリーディングでスコアを伸ばすためには、難しい専門用語を追いかけるよりも、まず頻出する基本語彙を確実に押さえることが最優先です。
本記事で紹介した単語は、過去問や模試で繰り返し登場するものばかりです。これらを知っているだけで、文章の大枠をつかみやすくなり、設問のパラフレーズにも対応しやすくなります。
大切なのは、
-
単語を「文脈」で理解すること
-
同義語や言い換えを意識すること
-
実際の演習で“既知化”していくこと
です。
この基本編を土台にすれば、応用編やより専門的なトピックの語彙にもスムーズに取り組めます。語彙力を強化し、読むスピードと正答率を同時にアップさせていきましょう。
次のステップとして、「Reading頻出語彙リスト(応用編)」を用意すれば、さらに実戦的な語彙力強化につなげられます。
FAQ:Reading頻出語彙リスト(基本編)
このFAQの目的は?
IELTSリーディングで頻出する基礎語彙の学び方と運用方法を短時間で確認できるようにすることです。暗記だけで終わらせず、設問のパラフレーズに対応できる読み方を前提にしています。
頻出語彙とは何を指しますか?
過去問や模試で繰り返し現れる、学術一般語(例:analyze, evidence, significant)や、数量・因果・論証を表す汎用語です。専門固有名詞より、複数トピックで横断的に出る語を優先します。
何語くらいを目安に学べば良いですか?
まずは300〜500語の基礎セット(本記事のカテゴリ+同義語)を1〜2周で定着させ、その後600〜800語へ拡張すると効果的です。
効率よく覚えるコツは?
- カテゴリー学習(学術語/数値変化/因果など)
- 例文ごと暗記(文脈依存で記憶を固定)
- 同義語・言い換えを対で覚える(significant = important など)
- 過去問で「既知化」する(見かけた語を都度復習リストへ)
パラフレーズ対策はどうすれば良いですか?
単語カードを見出し語→主同義語2〜3個→短文の構成にします。設問と本文で語が入れ替わっても意味がつながるかを、短文で確認するのが近道です。
辞書は英英と英和どちらを使うべき?
初回理解は英和で素早く意味取得→定着段階は英英でコア定義と用例を確認、の二段構えが効率的です。
接頭辞・語源は学ぶべき?
re-, inter-, -tion, -ment などの生産的な形態素は読解の推測力を上げます。週に10個程度のマイクロ学習を推奨します。
British/Americanの綴りは気にする?
意味は同じでも綴りが違う語(behaviour/behavior, analyse/analyze)に慣れておきましょう。設問照合で取り逃しを防げます。
単語テストはどう設計する?
- Dayテスト:その日の10〜15語を英日・日英・穴埋めで3周
- 週末ミックス:7日分を文脈穴埋め(本文風)で確認
- 模試連動:模試で遭遇→カードへ即追加→48時間内に復習
推奨の学習サイクルは?(1日の例)
- 朝15分:新出10語(例文音読)
- 昼10分:SRS復習(前日・3日前・1週間前)
- 夜20分:過去問の1パラグラフ精読→出現語をカードに追記
よくある失敗は?
- 単語単体の丸暗記のみで文脈確認をしない
- 同義語ネットワークを作らない(パラフレーズに弱い)
- 復習間隔が不適切(忘れた頃に出会わない)
進捗はどう測る?
週1回、ランダム20語の文脈穴埋め正答率80%を合格ラインに。加えて、過去問1セットの未知語率が5%未満なら次の語彙帯へ進みます。
リーディング以外にも効果はありますか?
同じ語彙はライティング・リスニングでも頻出です。特に因果・数量語はTask 1/2で即戦力になります。
どの順番で学べば良い?(優先順位)
- 学術基礎語(AWL的中核)
- 数量・変化語
- 因果・論証語
- 環境/社会の汎用語
未知語に出会った時の対処法は?
まずは文脈推測→品詞と接頭辞で意味範囲を絞る→必要なら辞書→カード化→48時間内に復習、の順で処理します。
応用編に進むタイミングは?
基礎300〜500語の文脈テストで80%以上を2週連続で達成し、過去問で未知語率が安定的に下がってきたら移行しましょう。