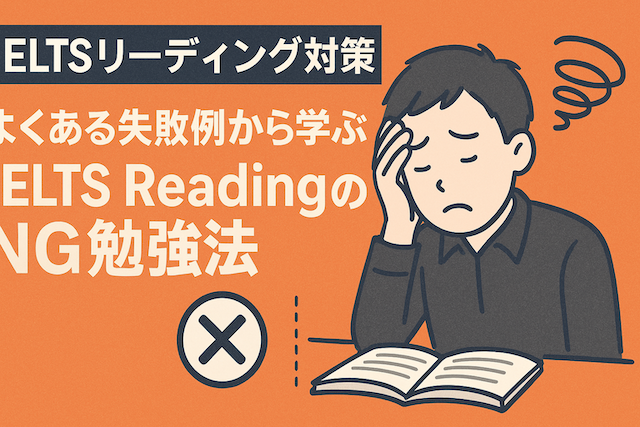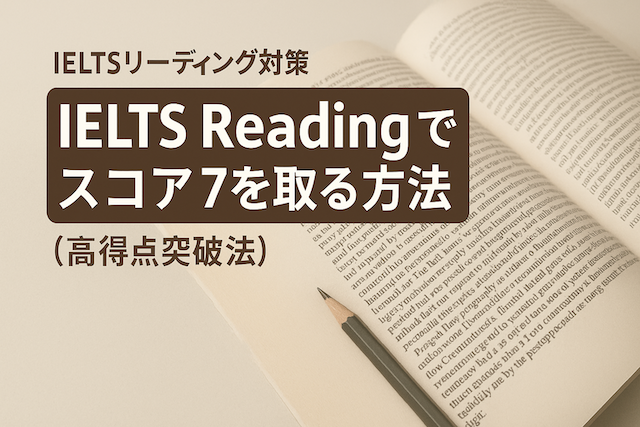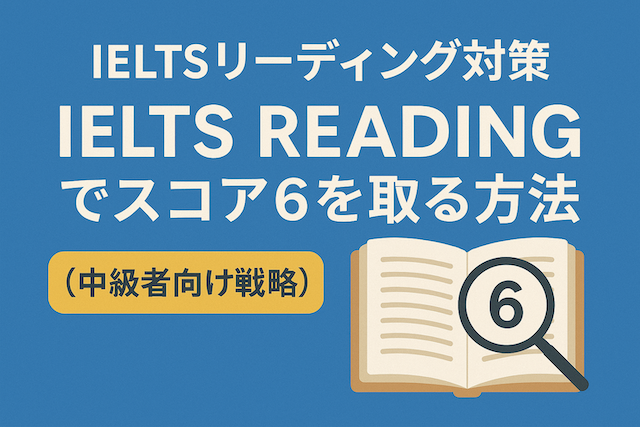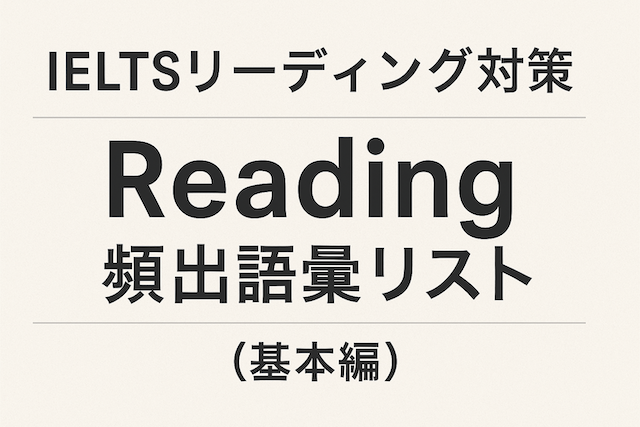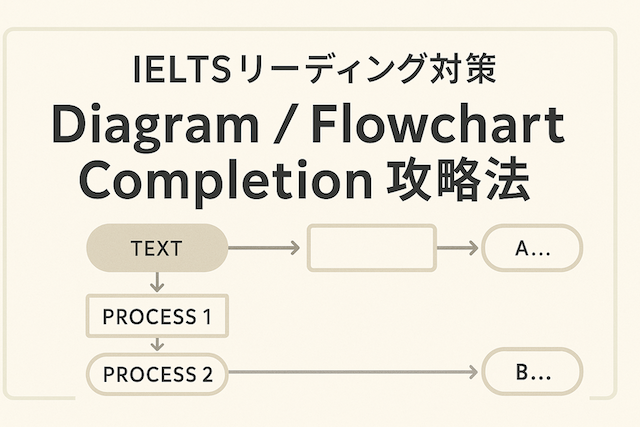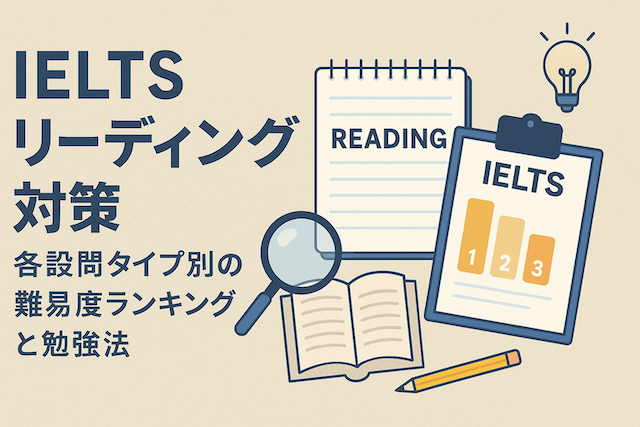目次
- IELTSリーディング対策: よくある失敗例から学ぶIELTS ReadingのNG勉強法
- はじめに
- NG勉強法① 単語暗記だけに偏る
- NG勉強法② 精読ばかりで時間を意識しない
- NG勉強法③ 問題形式を無視して勉強する
- NG勉強法④ 答え合わせをして終わり
- NG勉強法⑤ 過去問を解かずに本番に挑む
- まとめ
- FAQ:よくある失敗例から学ぶIELTS ReadingのNG勉強法
- IELTSリーディングのNG勉強法とは何ですか?
- 単語帳をひたすら覚えるのはダメですか?
- Not Given(NG)でよく間違えます。対処法は?
- 時間が足りません。おすすめの時間配分は?
- 精読と速読はどちらを優先すべき?
- 効果的な復習方法は?
- 過去問は何回やればいい?
- 公式問題集と多読、どちらを優先?
- パラフレーズに強くなるには?
- 回答順は本文→設問、設問→本文、どちらが良い?
- 辞書は使っても良い?学習時のルールは?
- アカデミックとジェネラルで対策は変わる?
- 目標スコア別の最短アプローチは?
- 1か月でできる現実的な計画は?
- 解けない問題に固執すると時間が溶けます。打ち切り基準は?
- 見直しでは何を確認すべき?
- 多読は不要ですか?
- スコアが伸び悩む停滞期の突破口は?
- 参考書は何冊必要?
IELTSリーディング対策: よくある失敗例から学ぶIELTS ReadingのNG勉強法
はじめに
IELTSリーディングは、多くの受験生が「時間が足りない」「本文を読んだはずなのに正解できない」と悩むセクションです。実際に60分で3つの長文と40問を解き切るのは容易ではなく、単なる英語力だけでなく「正しい勉強法」が求められます。
しかし、多くの人は間違った学習方法に取り組み、努力の割に点数が伸びないという壁にぶつかります。例えば、単語暗記ばかりに偏ったり、精読に時間をかけすぎたり、問題形式に慣れないまま本番を迎えたり…。これらはすべて「NG勉強法」の典型例です。
この記事では、受験生が陥りがちなリーディング学習の失敗例を整理し、それを避けるための効果的なアプローチをご紹介します。正しい勉強法を知り、NGパターンを回避することで、短期間でも着実にスコアアップを目指すことができます。
NG勉強法① 単語暗記だけに偏る
よくある失敗例
IELTS対策と聞くと、まず「語彙力を増やさなければ」と考えて、ひたすら単語帳を暗記する人が多いです。確かに語彙力はリーディング力の土台になりますが、「単語の意味を覚えること=点数が上がること」ではありません。
なぜダメなのか
IELTSリーディングでは、同じ単語が本文と設問でそのまま使われることはほとんどありません。パラフレーズ(言い換え)表現が頻繁に登場し、文脈理解が必須になります。
例えば、設問に “increase” と書かれていても、本文には “go up” や “rise” など別の表現で書かれていることが多いのです。単語の暗記だけではこうしたつながりを見抜けず、本文を理解できても解答につなげられないというミスを招きます。
改善策
-
文脈の中で覚える: 単語を単体で暗記するのではなく、文章ごと記憶する。
-
パラフレーズ集を作る: 問題演習の中で出てきた「言い換え表現」をまとめておく。
-
多読より精選した素材を活用: IELTS公式問題集やCambridgeシリーズから出てきた語彙を中心に学習する。
このように「語彙力+文脈理解」の両方を意識して学ぶことで、リーディングの正答率は大きく向上します。
NG勉強法② 精読ばかりで時間を意識しない
よくある失敗例
英語力を高めるために、一文一文をじっくり精読する練習は大切です。しかし、その方法をそのまま本番形式に当てはめてしまうと、1パッセージを終えるのに20分以上かかってしまい、最後のパッセージに手をつけられないまま時間切れになるケースが多発します。
なぜダメなのか
IELTSリーディングは 60分で3パッセージ・40問。平均すると1パッセージに使える時間は20分弱しかありません。精読中心の読み方では、長文を最後まで読み切れず、答えを書き込む時間も不足してしまいます。特に第3パッセージは難易度が高いため、時間を残せなければ大きく失点してしまいます。
改善策
-
スキミング(速読) を使い、文章全体の流れや主題をつかむ練習をする。
-
スキャニング(情報検索) を取り入れ、設問に必要なキーワードを本文中から素早く探す力を磨く。
-
タイムトライアル形式の練習 を行い、1パッセージを18〜20分で解くことを習慣化する。
本番では「全部を理解する」ことではなく、「解答に必要な情報を素早く見つける」ことが重要です。精読は基礎固めに使い、本番対策では速読・情報検索スキルを鍛えることがスコアアップにつながります。
NG勉強法③ 問題形式を無視して勉強する
よくある失敗例
「英語力さえあれば大丈夫」と思い、洋書や英字新聞を多読してリーディング力を鍛える人は少なくありません。もちろん英語力の底上げには役立ちますが、IELTSの独特な設問形式に慣れていないと、本番で戸惑って時間を浪費してしまいます。
なぜダメなのか
IELTSリーディングには以下のような特徴的な問題形式があります:
-
True / False / Not Given
-
Matching Headings(見出しの対応付け)
-
Sentence Completion(穴埋め問題)
-
Summary / Note / Table Completion
-
Multiple Choice Questions
これらは単なる「読解力」ではなく、設問のルールに従って答えを探すスキル が必要です。例えば、True / False / Not Given の問題では「本文に明確な情報があるか/書かれていないか」を正しく区別しなければなりません。慣れていなければ、本文を理解していても不正解になる可能性が高いのです。
改善策
-
設問タイプごとに練習する: 例えば「今日はTrue/False/Not Givenだけ」と絞って解く。
-
解答の根拠を探す習慣: 正解が本文のどこにあるかを必ず確認する。
-
間違えた問題を形式ごとに分析: 「Not GivenをFalseと判断してしまった」など、自分の弱点パターンを把握する。
英語力だけではIELTS Readingに対応できません。問題形式を理解し、形式別の攻略法を身につけることが、高得点への近道です。
NG勉強法④ 答え合わせをして終わり
よくある失敗例
模試や過去問を解いたあと、答え合わせをして「○か×か」だけ確認して満足してしまうケースです。間違った問題を「たまたま間違えた」と流し、解説を読んでも深掘りせずに次の問題集へ移ってしまう人は少なくありません。
なぜダメなのか
IELTSリーディングの学習で最も大切なのは、「なぜ正解できなかったのか」を徹底的に分析すること です。本文のどの部分を読み違えたのか、設問の意図をどう誤解したのか、パラフレーズを見抜けなかったのか——原因を特定しなければ、同じミスを繰り返すことになります。答え合わせだけで終わる勉強は、成長につながらず「解いた数=実力アップ」にはなりません。
改善策
-
必ず根拠を確認する: 正解が本文のどこにあるのかをチェックし、線を引いておく。
-
間違いノートを作る: 自分が誤った理由(例:Not GivenをFalseと判断/時間切れで読み飛ばした)を記録する。
-
パターン化された弱点を克服する: 「特定の設問形式でミスが多い」などの傾向を見つけ、集中的に練習する。
答え合わせを“ゴール”にするのではなく、“スタート”に変えること。これこそが、短期間でスコアを伸ばす人が実践している学習法です。
NG勉強法⑤ 過去問を解かずに本番に挑む
よくある失敗例
「英語力があればなんとかなるだろう」と考え、過去問や模試を解かずに本番に臨む受験生もいます。中には洋書やニュース記事でリーディング力を鍛えているから大丈夫だと思い込むケースもありますが、実際の試験では形式や時間配分に戸惑い、思ったように実力を発揮できません。
なぜダメなのか
IELTSリーディングは60分間で40問を解くスピード勝負です。しかも、独特の設問形式や「Not Given」のようなひっかけ問題があるため、本番の形式に慣れていなければ高スコアは難しいのです。過去問を通じて以下の感覚を養っておくことが不可欠です:
-
時間配分(1パッセージに18〜20分)
-
問題形式のルール理解
-
集中力の持続力
これらを経験せずに本番を迎えると、途中で焦りやパニックに陥りやすくなります。
改善策
-
本番同様の環境で過去問演習をする: 時計を使い、辞書やスマホは封印して60分集中する。
-
解き終わったら徹底分析: 正答率だけでなく、時間の使い方・読み飛ばした箇所・集中力が切れたタイミングを振り返る。
-
繰り返し同じ過去問を解く: 1回解いて終わりではなく、弱点が克服されるまで繰り返すことで着実に力がつく。
実際の試験を想定した「模擬練習」を重ねることで、試験本番でも落ち着いて解答でき、安定してスコアを伸ばすことができます。
まとめ
IELTSリーディングでスコアが伸び悩む原因は、英語力そのものよりも「勉強法の誤り」であることが少なくありません。
今回紹介したNG勉強法を振り返ると:
-
単語暗記だけに偏る
-
精読ばかりで時間を意識しない
-
問題形式を無視して勉強する
-
答え合わせをして終わり
-
過去問を解かずに本番に挑む
これらは多くの受験生が陥りやすい落とし穴です。どれか1つでも当てはまる人は、勉強法を見直すだけでスコアが大きく改善する可能性があります。
IELTSリーディングで高得点を取るためには、語彙+文脈理解+設問形式への慣れ+時間管理+復習の質 がカギです。正しい学習プロセスを踏めば、短期間でも6.5や7.0といったスコアは十分に狙えます。
失敗例から学び、効率的な対策を積み重ねることで、あなたのIELTSリーディングは必ず飛躍します。
FAQ:よくある失敗例から学ぶIELTS ReadingのNG勉強法
IELTSリーディングのNG勉強法とは何ですか?
単語暗記に偏る、精読だけで時間を意識しない、設問形式に慣れない、答え合わせで終える、過去問を本番同様に解かない——これらはスコア停滞の典型例です。
単語帳をひたすら覚えるのはダメですか?
「単語=意味」だけの暗記は効果が薄いです。本文と設問のパラフレーズを見抜くために、例文ごと・文脈ごとに覚え、同義語・言い換えをセットで記録しましょう。
Not Given(NG)でよく間違えます。対処法は?
「本文に明示があるか」を基準に判定します。本文に肯定・否定の根拠がない場合はNG。設問の主語・条件が本文と一致するかをライン引きで可視化し、安易にTrue/Falseへ寄せない癖をつけます。
時間が足りません。おすすめの時間配分は?
60分で3パッセージ・40問が目安。P1: 18分、P2: 20分、P3: 22分+見直し2〜3分を基準に、各パッセージ開始前に設問タイプを確認して配分を微調整します。
精読と速読はどちらを優先すべき?
本番対策では「スキミング(全体把握)+スキャニング(情報検索)」を優先。精読は基礎固め・文法確認の時間に回し、試験では解答に必要な情報にリソースを集中します。
効果的な復習方法は?
正誤だけでなく「根拠」を本文にマーキング。間違いの原因(語彙・設問解釈・パラフレーズ・時間切れ等)を分類した「エラーノート」を作り、形式別に弱点ドリルを回します。
過去問は何回やればいい?
最低2〜3周。1周目は本番同様に通し、2周目で設問タイプ別に反復、3周目で「根拠再現(本文の該当箇所を即指差しできるか)」を確認します。
公式問題集と多読、どちらを優先?
スコア直結は公式問題集(Cambridge等)。多読は基礎体力づくりとして有効ですが、直前期は公式形式への適応を優先しましょう。
パラフレーズに強くなるには?
設問⇄本文で対応する言い換えを対にして単語帳化(例:increase⇄rise/go up)。分野別(科学・歴史・社会)で頻出の言い換え表を自作し、毎回の復習で更新します。
回答順は本文→設問、設問→本文、どちらが良い?
多くの設問は本文の順序に沿うため、設問先読み→本文スキャンが効率的。Matching Headingsのみ、段落主旨を先に掴むために本文を軽くスキミングしてから取り組むのがおすすめです。
辞書は使っても良い?学習時のルールは?
演習中は原則禁止(本番は辞書不可)。復習時のみ使用し、未知語は「推測→確認→パラフレーズ登録」の手順で定着させます。
アカデミックとジェネラルで対策は変わる?
読解スキルのコアは共通ですが、文章のジャンルと設問傾向が異なります。受験モジュールに合わせて、公式問題で形式適応を最優先に。
目標スコア別の最短アプローチは?
6.0:設問タイプ別の処理手順を確立。
6.5:時間内完答の安定化とNG判定の精度向上。
7.0+:パラフレーズ検出の高速化、見出し対応・要約完成の正答率底上げ。
1か月でできる現実的な計画は?
週5〜6日、1日90〜120分を確保。
前半2週:公式2セットを本番同様+徹底分析。
後半2週:弱点形式のドリル化/過去問リピートで根拠再現トレ。毎週1回はフル模試。
解けない問題に固執すると時間が溶けます。打ち切り基準は?
30〜45秒で根拠の目星が立たなければ一旦スキップ。後回し用のマークを付け、回収は最後に。完答よりも総合得点最大化を優先します。
見直しでは何を確認すべき?
固有名詞・数値・単位の誤写、True/False/Not Givenの根拠有無、スペリング、転記ミス。時間が少ない場合は配点が高い/易しい設問から優先的にチェックします。
多読は不要ですか?
不要ではありません。基礎読解力や背景知識の蓄積に有効。ただし直近は「公式形式の適応>多読」。時間配分と設問処理の自動化を先に完成させましょう。
スコアが伸び悩む停滞期の突破口は?
「設問タイプ別の誤答原因」を1週間分集計し、最多の2タイプに学習を集中。根拠再現トレとパラフレーズ帳の更新で、処理の再現性を高めます。
参考書は何冊必要?
「公式問題集(数冊)+形式別対策1冊+語彙・パラフレーズ帳(自作)」で十分。冊数よりも「復習の深さ」と「根拠の再現性」を重視してください。