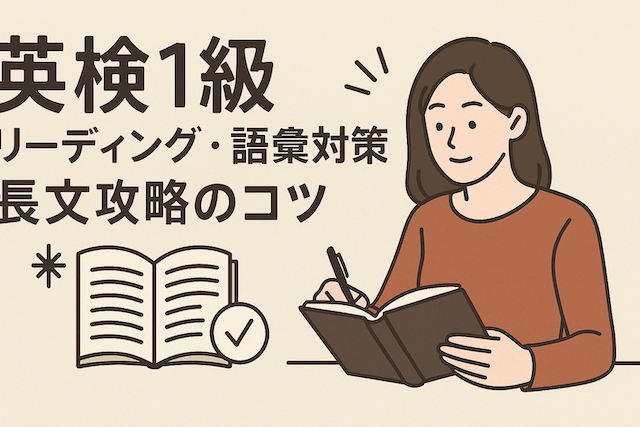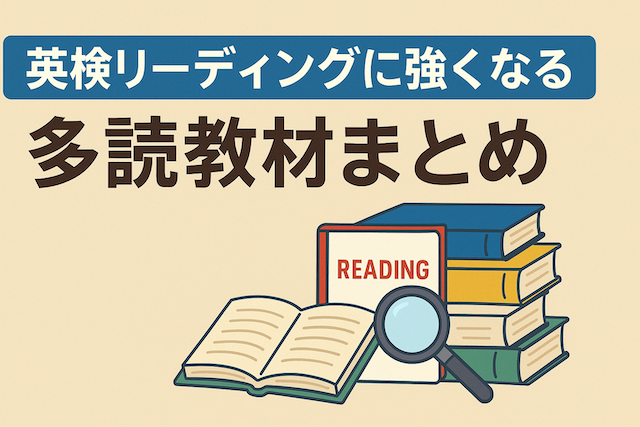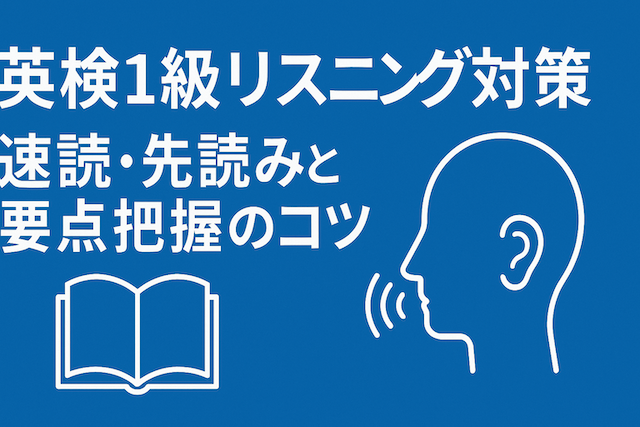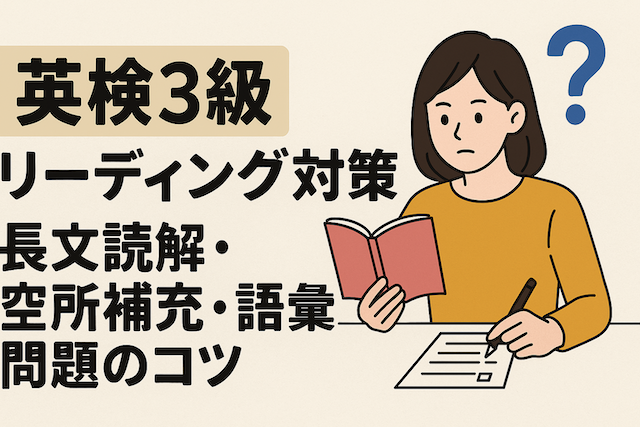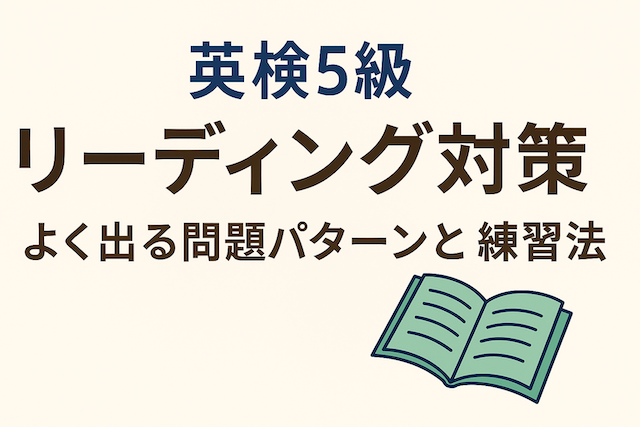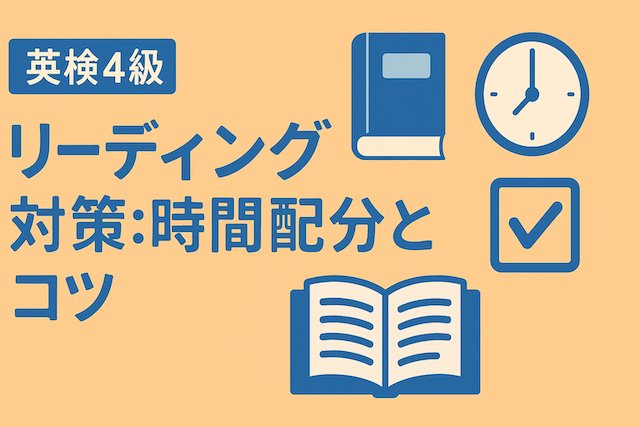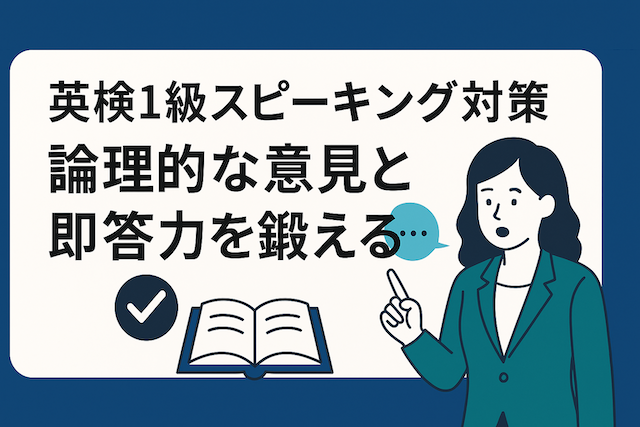目次
- 英検1級リーディング・語彙対策:長文攻略のコツ
- はじめに
- 英検1級リーディングの全体構成と特徴
- 語彙力アップの戦略:本番に強い単語学習法
- 長文読解のコツ①:構造をつかむ読解力を磨く
- 長文読解のコツ②:設問別アプローチ
- スピードを上げる読解練習法
- 長文に出やすいテーマと背景知識
- 模試・過去問の活用法
- 試験直前の確認ポイント
- まとめ
- よくある質問(FAQ)
- 英検1級のリーディングはなぜ難しいのですか?
- 語彙を効率よく覚えるにはどうすればいいですか?
- 難しい単語が多くて意味がわからないときは?
- 長文読解を効率よく進めるコツは?
- 時間配分の目安を教えてください。
- 過去問はどう活用すれば効果的ですか?
- 読解スピードを上げる練習法は?
- 推論問題が苦手です。どうすれば克服できますか?
- 背景知識はどれくらい必要ですか?
- リーディング練習はライティングにも役立ちますか?
- 試験前日にやるべきことは?
- 最後に:リーディングを得点源にするために
英検1級リーディング・語彙対策:長文攻略のコツ
はじめに
英検1級のリーディングセクションは、多くの受験者にとって最大の壁と言われます。語彙レベルは大学上級〜ネイティブアカデミック層に匹敵し、長文も抽象的・論理的な内容が中心です。ニュースや専門誌を日常的に読む力が求められ、準1級までとは明らかに次元が異なります。
英検1級の読解問題は、単に「英文を読む」だけでは太刀打ちできません。語彙力、背景知識、読解スピード、そして筆者の主張を正確に把握する論理力が必要です。特に語彙問題(Part 1)は、単語の微妙なニュアンスを理解していないと誤答しやすく、長文(Part 2・3)は時間との勝負になります。
とはいえ、闇雲に長文を読み続けてもスコアは伸びません。大切なのは、「英検1級の問題構成を理解し、出題者の意図を読む」ことです。つまり、どのような語彙が狙われ、どのような構文・論理展開が出やすいかを体系的に分析し、それに沿って練習を積むことが最短ルートとなります。
本記事では、英検1級リーディングの全体構成と出題傾向を整理したうえで、語彙問題と長文問題をどのように攻略すべきかを具体的に解説します。さらに、時間配分・速読法・おすすめ教材まで実践的に紹介します。
「読むスピードが遅い」「語彙が難しすぎて意味が取れない」「要旨問題で毎回迷う」──こうした悩みを抱えている方でも、正しい方法でトレーニングすれば確実に得点力を上げられます。英検1級は“英語力の総合試験”ですが、リーディングを制すれば合格の道がぐっと近づきます。
次章では、まずリーディングパートの構成と特徴を理解し、どの部分で差がつくのかを見ていきましょう。
英検1級リーディングの全体構成と特徴
英検1級の一次試験は、Reading・Listening・Writingの3セクションで構成されます。そのうちリーディングは、語彙問題から長文読解まで、英語運用力を総合的に測る設計になっています。全体で41問前後、制限時間は約85分。スピードと正確さの両立が求められます。
リーディングパートは大きく以下の3セクションに分かれます。
1. 語彙問題(Part 1)
25問。文中の空欄に最も適切な語を選ぶ形式です。英検準1級のような日常語中心ではなく、学術的・抽象的な単語が頻出します。
特徴:
-
選択肢はすべて意味が近く、文脈判断が必須
-
「単語の核となる意味(コア)」を理解していないと区別できない
-
慣用表現や派生語も問われる
例:
Although the new policy was initially welcomed, it soon became a source of public ( ).
A) controversy B) sympathy C) stability D) harmony
→ 正解は A) controversy(論争)
→ 「歓迎されたがすぐに問題になった」という文脈から判断します。
このように、語彙問題では「語感」と「文脈の流れを読む力」が重要です。単語帳の暗記だけでなく、実際の英文中での使われ方を理解する練習が効果的です。
2. 短文読解(Part 2)
数段落程度の英文を読み、内容一致問題に答える形式。テーマは社会問題や科学技術、文化など多岐にわたります。
特徴:
-
要点を素早くつかむ「スキャニング」力が必要
-
各段落の主張・理由・例を明確に整理できるかがカギ
-
設問は要旨・詳細・文脈判断など多様
短文読解では「段落ごとの主題文(トピックセンテンス)」を見抜くのがコツです。最初の文か最後の文に主張があることが多いため、そこを中心に読むと効率的です。
3. 長文読解(Part 3)
リーディングの最大の山場。約800〜1000語の長文が2〜3題出題され、内容一致・要旨・推論などの問題が出されます。
特徴:
-
英字新聞・学術エッセイに近い文体
-
論理構成(主張 → 理由 → 例 → 結論)を理解できるかが問われる
-
「筆者の意図」「因果関係」「対比構造」を把握する力が必要
文章の内容は高度ですが、構成そのものは一貫しています。多くの受験者は文の難解さよりも、「どこを読めば答えがあるか」を特定できずに時間を浪費してしまいます。そのため、段落構成を意識しながら読む訓練が欠かせません。
4. 時間配分の目安
| セクション | 問題数 | 目安時間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 語彙問題(Part 1) | 25問 | 約15分 | 直感的にテンポよく進める |
| 短文読解(Part 2) | 約7問 | 約20分 | 段落要旨をつかむ |
| 長文読解(Part 3) | 約9問 | 約50分 | 論理展開を追う読み方が鍵 |
試験では後半の長文で時間が不足するケースが多いため、前半の語彙問題を1問30秒以内で進める意識が重要です。
語彙力アップの戦略:本番に強い単語学習法
英検1級の語彙問題は、英語力の“基礎体力”を問うパートです。高得点を狙うには、単語の意味をただ暗記するのではなく、「どのように使われるか」「文脈でどう働くか」を理解する必要があります。ここでは、実際に合格者が実践している効果的な語彙学習法を紹介します。
1. 単語のコア(核心イメージ)を理解して覚える
英検1級では、単語の派生的な意味や比喩的な使われ方がよく出題されます。単語帳で最初の意味だけを覚えても、文脈が変われば見抜けないことが多いのです。
例:
-
compound:化合物 → 「悪化させる」という動詞の意味で出題されることもある
-
temper:気性 → 「和らげる」という意味で出るケースがある
これらは単語の「コアとなる意味(中心イメージ)」を理解していれば推測可能です。
たとえば temper は「調整する」「バランスを取る」イメージを持つため、怒りを“調整して和らげる”という意味が自然に理解できます。
2. 英検単語帳+実際の英文で定着させる
単語帳だけで覚えるのではなく、実際の英文中での使われ方を確認することが重要です。
おすすめは以下の組み合わせです:
-
『英検1級語彙・イディオム問題500』や『パス単英検1級』で基礎を作る
-
その単語を BBC, The Economist, National Geographic などのニュース記事で再確認
-
自分で例文を作り、音読・シャドーイングして定着
特に、ニュースや評論文で見た「生きた用例」をストックしておくと、試験で似た文脈に出会ったときに即座に反応できるようになります。
3. 派生語・コロケーションをまとめて覚える
英検1級の語彙問題では、同じ語幹を持つ派生語が出ることも多いです。
また、コロケーション(単語の自然な組み合わせ)を知っておくことで、選択肢の違和感を判断できます。
例:
-
advocate(動詞:主張する)
-
advocacy(名詞:提唱・支援)
-
advocate for 〜(〜を主張する)
このようにセットで覚えることで、単語の使い方が体感的に理解できるようになります。単語帳を「意味の暗記ツール」ではなく「使い方を理解する辞書」として使うのが理想です。
4. 苦手分野ごとに語彙を整理する
英検1級の長文では、テーマごとに特定の語彙が繰り返し登場します。
効率的に学ぶには、以下のように分野別に整理するのがおすすめです。
| 分野 | 代表的な語彙例 | 対策方法 |
|---|---|---|
| 環境・エネルギー | emissions, renewable, depletion | BBC Earthなどの特集を読む |
| 政治・社会 | legislation, advocate, inequality | The Economistの記事を要約練習 |
| 科学・医療 | molecule, synthetic, immune | Scientific Americanの短文を精読 |
| 文化・心理 | empathy, perception, cognition | TED Talksスクリプトで語彙確認 |
背景知識と一緒に覚えると、単語の意味が「知識」として定着しやすくなります。
5. AnkiやQuizletで「反復・音声」学習を習慣化
単語は忘れる前に復習することで長期記憶に残ります。
アプリを使えば、復習間隔を自動で調整してくれるため効率的です。
-
Anki:例文+音声を登録して、発音・文脈を同時に確認
-
Quizlet:スマホでスキマ時間にクイズ形式で確認
音声つきの例文で「耳から覚える」習慣をつけると、Listening対策にもつながります。
6. 英検1級レベルの語彙数を目標にする
合格者の多くは、最低1万2000語〜1万5000語レベルの語彙力を持っています。
ただし、数を増やすことよりも「使える語彙」を増やすことが大切です。
「意味がわかる」から「文脈で使える」へ。
この意識の転換こそが、英検1級リーディング攻略の第一歩になります。
長文読解のコツ①:構造をつかむ読解力を磨く
英検1級の長文は、一見して難しそうに見える文章が多いですが、実は構成はとても論理的です。文章の「構造」を意識して読むことで、内容の整理がしやすくなり、設問への対応スピードも格段に上がります。ここでは、長文の流れを理解するための具体的な読み方を紹介します。
1. 段落ごとの役割を把握する
英検1級の長文は、英字新聞や評論文のようなエッセイ構成になっています。多くの文章は、次のようなパターンで構成されています。
-
導入(Introduction):問題提起や主張の提示
-
展開(Body):理由や例を挙げて主張を支える部分
-
結論(Conclusion):主張のまとめ、または提案
段落ごとの役割を意識して読むことで、筆者の立場や主張の流れをつかみやすくなります。特に最初の1〜2文は「トピックセンテンス(段落の主題文)」であることが多く、段落の方向性を示しています。
2. 論理マーカーを意識して読む
筆者の主張を読み解くには、文中に出てくる**論理マーカー(接続詞・転換語)**が重要な手がかりになります。
たとえば以下のような表現は、それぞれの論理展開を示しています。
| 論理関係 | マーカー例 | 意味の方向性 |
|---|---|---|
| 逆接 | however, on the other hand, in contrast | 意見や立場の対比 |
| 因果 | therefore, as a result, consequently | 原因・結果の関係 |
| 例示 | for example, such as, to illustrate | 具体例の提示 |
| 強調 | indeed, in fact, above all | 主張の補強 |
| 追加 | moreover, furthermore, in addition | 論点の追加 |
これらの単語を見逃さずに読むだけで、筆者の論理展開を追うのがはるかに楽になります。
3. 主語と動詞を先に見つける
英検1級の長文は、修飾語が多く、一文が非常に長くなりがちです。
しかし、英文の「骨格」はいつでも**主語(S)+動詞(V)**です。これを最初に見つけるだけで、文の意味をすばやく把握できます。
例文:
The government, despite facing severe criticism from opposition parties and media outlets, decided to implement the controversial policy.
この文は途中に長い挿入句が入っていますが、
-
主語:The government
-
動詞:decided
と分かれば、全体の骨格が明確になります。あとは「何を決めたのか」「どんな背景か」を補うだけで理解可能です。
4. 「話の流れ」を図解する意識を持つ
長文を読んでいるときは、頭の中で「マインドマップ」を描くイメージで構成を整理します。
たとえば次のような形です:
筆者の主張 → 理由①(例) → 理由②(反論) → 結論(提案)
こうした流れを把握しておけば、内容一致問題や要旨問題でも「どの段落が根拠か」をすぐに見つけられます。読解後に段落ごとに一行要約をつける練習も効果的です。
5. 難文は「分解して」読む
英検1級では、文法的に複雑な構文も頻出します。
-
関係代名詞が2つ以上入る文
-
分詞構文や挿入句が多い文
-
抽象名詞+修飾節で構成された文
これらは、1文を3ブロック程度に区切って理解するのがコツです。
例:
Although the number of electric vehicles has increased rapidly, / charging infrastructure has not kept pace, / creating challenges for widespread adoption.
このようにスラッシュを入れて読む(スラッシュリーディング)ことで、構造が明確になり、速読力も自然に鍛えられます。
6. 英検1級の長文に共通する「型」をつかむ
出題されるテーマは毎回異なりますが、構成の「型」は似ています。
多くの英文は、次のような3段構成で展開されます。
-
問題提起(現状の課題を説明)
-
原因・背景の分析(統計や研究を引用)
-
筆者の結論(解決策や提案)
この型を意識して読むと、初見の英文でも流れを予測できるようになります。
筆者の主張を追う「構造的な読み方」ができるようになると、内容一致問題や要旨問題への正答率が一気に上がります。
次のセクションでは、実際の設問タイプごとに「どのように読んで答えるか」を詳しく解説します。
長文読解のコツ②:設問別アプローチ
英検1級の長文読解では、設問の種類によって求められる読み方が異なります。
問題文を読む前に「どのタイプの質問か」を把握し、それに合わせたアプローチを取ることで、無駄な読み返しを減らせます。ここでは、主な設問タイプごとの攻略法を紹介します。
1. 要旨問題(Main Idea / Summary)
出題傾向:
-
「本文の主題を最もよく表しているものを選べ」
-
「筆者の主張を要約しているものはどれか」
攻略法:
-
各段落の「トピックセンテンス(主題文)」を1行でまとめ、全体の流れをつなぐ
-
結論段落の主張を中心に考える(筆者の立場は多くの場合ラストで明確になる)
-
選択肢のうち、「本文の一部にしか当てはまらない内容」や「極端な主張(always, completelyなど)」は除外
コツ:
「タイトルをつけるなら何とするか?」という視点で考えると、要旨が整理しやすくなります。
2. 内容一致問題(Detail / Fact Check)
出題傾向:
-
「本文の内容と一致しているものを選べ」
-
「本文で述べられていないものはどれか」
攻略法:
-
設問のキーワード(名前、数字、固有名詞など)を本文で探し、該当箇所を精読
-
同義語・言い換え表現(paraphrase)を意識する
-
例:「increase」⇔「grow」「rise」
-
「because」⇔「as a result of」
-
-
選択肢が“本文の表現を部分的に引用している”場合、前後の文脈まで確認
注意:
“not mentioned(触れられていない)”タイプの問題では、「本文に書いていないこと」を根拠に選ぶ必要があります。
曖昧な記憶で「たぶん出てきた」と思って選ぶのは危険です。
3. 推論問題(Inference)
出題傾向:
-
「筆者が示唆していることはどれか」
-
「本文から推測できる内容を選べ」
攻略法:
-
推論問題は、本文に直接書かれていない内容を問うが、根拠は必ず本文内にある
-
“筆者が本当に言いたいこと”や“背景の意図”を読み取る
-
「文と文の関係」「因果関係」「比較構造」などを分析して、含意をつかむ
例:
Some researchers argue that happiness cannot be measured objectively.
→ 選択肢:「The author implies that defining happiness is challenging.」
→ 正解。本文の意図を言い換えている。
コツ:
選択肢に「本文の表現をそのまま使っている」ものは、逆に誤答であることも多い。
“言葉を変えた理解”が求められます。
4. 語彙・表現の意味問題(Vocabulary in Context)
出題傾向:
-
「下線部の単語に最も近い意味を選べ」
-
「本文中の表現の意味として正しいものを選べ」
攻略法:
-
単語そのものではなく、文脈の中でどう使われているかに注目
-
直前・直後の文にヒントが隠れていることが多い
-
“否定構文”“対比構文”の中では意味が反転している場合もある
例:
The politician’s comments were dismissed as superficial.
→ “superficial”=「浅はかな」「表面的な」と推測できる。
5. 構成・指示語問題(Reference / Structure)
出題傾向:
-
「下線部の“it”は何を指すか」
-
「本文の構成として正しいものを選べ」
攻略法:
-
指示語(it, this, theyなど)の前後を読んで、「単数・複数」「抽象・具体」を照合
-
段落の流れを理解して、どの部分が例示・対比・結論かを把握
コツ:
指示語問題はリーディング力の本質が問われる部分。構造をつかめていれば、自然に答えが見えてきます。
6. 設問を先に読む「逆順読み」も有効
長文問題では、本文を読む前に設問を一読しておくと、どの情報を探せばよいかが明確になります。
特に内容一致や語彙問題では、「出題箇所を特定する」目的で非常に有効です。
ただし、要旨問題など全体理解が必要な設問では、本文を読んだ後に取り組むほうがミスが少なくなります。
設問タイプごとに読む順番を変えるのが、時間短縮のコツです。
要するに、英検1級の長文では「すべての文を完璧に読む」必要はありません。
重要なのは、「どの設問がどの情報を求めているか」を見抜き、正確に該当部分を探し出すこと。
読む力と問題処理力を両立させることが、リーディング高得点への最短ルートです。
スピードを上げる読解練習法
英検1級のリーディングでは、時間配分が最も大きな課題のひとつです。
問題数に対して制限時間が短く、1文1文を丁寧に訳していては到底間に合いません。ここでは、読解スピードを上げるための具体的なトレーニング方法を紹介します。
1. タイマーを使って過去問を解く習慣をつける
リーディング全体の制限時間は約85分。目安は以下の通りです。
-
語彙問題(Part 1):15分
-
短文読解(Part 2):20分
-
長文読解(Part 3):50分
まずはこの時間配分で解き、どのパートで時間がかかっているかを分析します。
苦手なセクションを特定し、そこだけ重点的に「時間を意識した練習」を繰り返しましょう。
また、タイマーを使うことで“本番と同じ緊張感”を再現できるため、集中力も高まります。
2. スラッシュリーディングで意味の区切りを意識
読解スピードを上げるためには、「意味のかたまり」を素早くつかむことが大切です。
1文を日本語に訳さず、英語のまま構造で理解する力を鍛えましょう。
例:
Although the number of electric vehicles has increased rapidly, / charging infrastructure has not kept pace.
→ EVの台数が急増しているが、充電設備が追いついていない。
このようにスラッシュを入れて読むことで、構文の区切りが明確になります。
“返り読み”をせずに、英語を左から右へ処理するクセをつけることがポイントです。
3. 要約練習で「要点抽出力」を磨く
リーディング力の本質は、単語を知っているかどうかではなく、要点をつかめるかにあります。
長文を読んだあと、各段落を一文で要約する練習をしてみましょう。
例:
-
段落1:テクノロジーの進化が社会構造を変えている
-
段落2:その変化は労働市場に新しい課題を生んでいる
-
段落3:教育改革がその解決の鍵である
このように段落ごとの「役割」をまとめる習慣をつけると、要旨問題や推論問題にも強くなります。
4. 音読とシャドーイングで理解のスピードを上げる
英語を“声に出して読む”ことで、読解スピードと理解力が同時に鍛えられます。
特に英検1級レベルの長文はリズムや構文が複雑なので、音読練習が非常に効果的です。
おすすめの方法:
-
過去問や問題集の長文を音読する
-
音声CDやオンライン教材を使ってシャドーイング(聞こえた英語を即座に真似して発話)
-
同じ英文を何度も繰り返し、自然なスピードで理解できるまで練習
このトレーニングにより、リスニング力も同時に向上します。
5. “一度読み”を目標にする練習
多くの受験者が時間を失う原因は、「何度も読み返してしまうこと」です。
“最初の一読で要旨をつかむ”意識を持つだけで、解答スピードが劇的に変わります。
具体的な練習法としては:
-
最初に設問を読んで、読む目的を明確にする
-
読みながら「重要情報」だけをマーキング(数字・人名・主張)
-
読み終えたら、本文を見ずに内容を口頭で要約
このプロセスを繰り返すと、自然と一読で全体像をつかめるようになります。
6. 定期的な「模試形式リーディング練習」で実戦感覚を養う
最後に重要なのは、本番を想定した通し練習です。
模試や過去問を使って、時間制限内にリーディング全体を解く練習を行いましょう。
特に英検1級では、長文の後半で集中力が落ちる傾向があります。
週1回でもいいので、実際の試験と同じ時間で挑戦することで「後半の粘り」を身につけられます。
リーディングのスピードは、才能ではなく“訓練の積み重ね”です。
読解筋を鍛え、時間感覚を磨くことで、試験中の焦りがなくなり、安定して高得点を狙えるようになります。
長文に出やすいテーマと背景知識
英検1級の長文は、日常会話レベルの英語とは異なり、社会的・学術的テーマが中心です。
単語の難易度だけでなく、内容そのものの理解に背景知識が必要な場合も多く、ニュース・評論・科学記事を普段から読む習慣があるかどうかで差がつきます。ここでは、過去10年の出題傾向から見た「頻出テーマ」と「効果的な知識習得法」を紹介します。
1. 環境・エネルギー問題
最も出題頻度が高いジャンルの一つです。
再生可能エネルギー、気候変動、生態系保全、資源枯渇などがよく扱われます。
例題テーマ:
-
The impact of climate change on developing nations
-
Renewable energy as a solution to global warming
対策:
-
BBC Earth や National Geographic の記事を定期的に読む
-
環境に関連する基本単語をまとめて覚える(emission, renewable, sustainable, depletionなど)
-
問題文中の「原因 → 結果」「問題 → 解決策」の構造を意識して読む
2. 政治・社会・経済
社会構造や制度に関する英文も頻出です。英検1級の問題は、特定の政治的立場を取るわけではなく、「社会問題を論理的に分析する力」を問います。
例題テーマ:
-
The role of government in reducing inequality
-
The effects of globalization on local communities
対策:
-
The Economist や Reuters の社説を読み、要約練習をする
-
policy, legislation, reform, inequality, regulation などの政治・経済語彙を整理
-
一文に含まれる「主張 → 根拠 → 反論」の流れを分析
3. 科学・テクノロジー
AI、医療、宇宙、遺伝子研究などの科学的トピックも頻出です。
専門用語が出ることもありますが、重要なのは“研究の意図”と“結果の意味”を理解することです。
例題テーマ:
-
Artificial intelligence and ethics
-
Advances in genetic engineering
対策:
-
Scientific American や Nature News の短い記事を読む
-
専門用語の意味を覚えるよりも、文の論理展開を重視する
-
科学記事特有の「因果関係」「比較」「データ提示」を見抜く練習をする
4. 文化・教育・心理
この分野は、文章構造が比較的シンプルですが、抽象概念が多いため理解に時間がかかることがあります。
心理学や教育論は、筆者の意見が明確に出る傾向があり、推論問題が多いのも特徴です。
例題テーマ:
-
The importance of empathy in education
-
How cultural background influences communication styles
対策:
-
TED Talks や Psychology Today の記事を活用
-
empathy, perception, cognition, bias などの心理系語彙を整理
-
「筆者の主張」と「事実説明」を混同しないよう注意
5. 歴史・哲学・倫理
出題頻度はやや低めですが、時折出ると受験者を悩ませるテーマです。
特定の人物や時代の出来事を扱うよりも、「歴史や思想の意義」を考察する論文が多い傾向です。
例題テーマ:
-
The relevance of ancient philosophy in modern society
-
How history shapes our sense of morality
対策:
-
New York Times Opinion や Aeon Magazine のエッセイを読む
-
主張が抽象的な文章では「例」と「結論」の関係に注目する
6. 背景知識を増やすための実践法
英検1級の読解スピードと理解度を上げるためには、英語力だけでなく、世界知識を広げる習慣が欠かせません。
以下のような学習法を取り入れると、自然に読解の「土台」が強化されます。
-
毎日1本、英語ニュース記事を読む(200〜300語程度でも可)
-
気になった単語や表現をノートにまとめ、ジャンル別に整理
-
記事を日本語で要約してから、再度英語でまとめ直す(要約力+思考力の訓練)
また、同じテーマの英文を複数読むと、内容の理解が深まるだけでなく、語彙の使われ方や表現のパターンも身につきます。
背景知識を持っているだけで、英文を読むスピードが格段に速くなります。
知らないテーマに出会ったときでも、「どのような構成になるか」を予測できるようになれば、焦らずに読解を進められるでしょう。
模試・過去問の活用法
英検1級リーディング対策で最も効果的な学習法は、過去問分析と模試形式の演習です。
単に問題を解くだけではなく、「どこで間違えたのか」「なぜその選択肢が正解なのか」を深掘りすることで、問題作成者の意図を理解できるようになります。ここでは、過去問を最大限に活用するための具体的なステップを紹介します。
1. 「読む練習」ではなく「分析練習」をする
多くの受験者がやってしまうのが、「過去問を一度解いて終わり」にする学習です。
しかし英検1級では、出題パターンが非常に安定しているため、分析して学ぶことが圧倒的に重要です。
分析のポイント:
-
間違えた選択肢:どの単語や文脈を読み違えたか
-
正解の根拠:本文のどの部分に明示・示唆されていたか
-
設問のタイプ:要旨・内容一致・推論・語彙のどれか
誤答ノートを作り、間違えた問題を「もう一度同じ形式で出されたら解けるか?」を確認することが上達への近道です。
2. 英検公式問題集を軸に使う
最も信頼できる教材は、英検公式問題集です。
実際の出題形式・文体・語彙レベルが完全に再現されているため、本番対策としてはこれ以上の教材はありません。
おすすめ教材:
-
『英検1級 過去6回全問題集』(旺文社)
-
『英検1級 予想問題ドリル』(ジャパンタイムズなど)
使い方のコツ:
1回分をまず本番同様に通して解く
→ 採点後、本文を精読して構造分析
→ 不正解の原因をまとめ、次の回で意識的に改善
過去問は最低3周するのが理想です。1周目は実力確認、2周目で弱点分析、3周目で定着を確認するイメージです。
3. 音読・リスニング教材としても再利用
リーディング教材として使い終わった過去問も、音読・シャドーイング練習に再利用できます。
長文を音声とともに読むことで、構文感覚が身につき、英語の処理スピードが向上します。
-
英検公式アプリや音声CDを活用し、1日1長文を音読
-
リーディングでつまずいた構文をリスニングで再確認
-
“意味のわからないまま音読しない”ことが大切
この方法で、リーディング+リスニングの二重強化が可能になります。
4. 定期的に模試形式で実戦練習
過去問を分析するだけでなく、定期的に模試形式で通し練習を行うことで、本番への耐性を高めましょう。
ポイント:
-
週1回、本番と同じ85分で通し演習
-
終了後は「どの問題にどれだけ時間を使ったか」を記録
-
読解スピード・集中力・時間配分を客観的に把握
模試を繰り返すうちに、**“焦らず解くリズム”**が身につきます。これはどんな参考書でも身につけられない実戦感覚です。
5. 苦手分野を「テーマ別リーディング」で補強
過去問の分析を続けると、「環境問題に弱い」「科学系が苦手」など、自分の傾向が見えてきます。
その場合は、弱点テーマを集中的に読む“テーマ別リーディング”を行いましょう。
例:
-
科学系が苦手 → BBC Science / Scientific American
-
社会・政治系が苦手 → The Economist / The Guardian
-
心理・文化系が苦手 → Psychology Today / Aeon
自分の苦手分野に慣れておくと、本番で未知のトピックが出ても落ち着いて読めるようになります。
6. 過去問の英文を「再構築」する
最後の仕上げとして、過去問の長文を自分で要約・書き直す練習を行うと効果抜群です。
-
各段落を一文で要約
-
文章全体を自分の言葉で英語に書き換え
-
“筆者の主張”を短く英語で説明できるようにする
この練習は、ライティング対策にも直結します。リーディングの理解が浅いとライティングで論理的な文が書けないため、両方をつなげて学ぶのが理想です。
過去問は単なる「確認」ではなく、「最強のトレーニング素材」です。
出題形式を知り尽くし、問題作成者の思考を読む力を磨けば、本番でも落ち着いて正答を導けるようになります。
試験直前の確認ポイント
試験直前の1〜2週間は、新しい知識を詰め込むよりも、これまで学んだ内容を整理し、ミスを減らすことに集中すべき時期です。ここでは、英検1級リーディング本番直前にやっておくべきチェックポイントをまとめます。
1. 苦手テーマを1つずつ短時間で復習
これまでの学習で特に苦手だったテーマ(環境・政治・科学など)を、1日1トピックずつ確認しましょう。
過去問やニュース記事を使い、次の3点を意識して復習します。
-
そのテーマでよく使われる重要語彙
-
よく出る論理展開(原因→結果、問題→解決など)
-
筆者の主張パターン
短時間でも「この分野はもう大丈夫」と自信を持てるだけで、試験中の集中力が全く違ってきます。
2. 接続詞・論理マーカーの一覧を見直す
英検1級の長文は、複雑な構文でも論理マーカーが理解の手がかりになります。
前日に軽く復習しておくと、読解スピードが一気に安定します。
代表的なマーカー:
-
逆接:however, nevertheless, on the other hand
-
因果:therefore, consequently, as a result
-
追加:furthermore, moreover, in addition
-
例示:for instance, to illustrate, such as
-
強調:indeed, in fact, notably
これらを見かけたら、「筆者がここで何を強調・転換しているのか」を意識して読み進めましょう。
3. 新出語彙を“確認だけ”する
試験直前に新しい単語を覚えるのは非効率です。
その代わり、これまでの単語帳やメモから「忘れかけている単語」だけを復習しましょう。
効果的な方法:
-
過去問で間違えた語彙をリスト化してチェック
-
アプリ(Anki, Quizlet)でランダム再生して反射的に答える練習
-
意味を見て「例文が口から出るか」確認する
新規暗記より“定着確認”が最優先です。
4. 英文速読1本を音読して感覚を整える
試験当日にいきなり英文を読むと、リズムをつかむまで時間がかかります。
そこで、本番前日の夜か当日の朝に、短い英文を声に出して読むのがおすすめです。
例:
-
過去問の短文(Part 2)
-
CNNやBBCのニュース記事(200〜300語程度)
音読することで「英語を英語のまま理解する感覚」を呼び戻し、脳をリーディングモードに切り替えられます。
5. 本番中の時間配分を再確認
本番では、時間切れが最大の失点要因になります。
リーディング85分をどう使うか、試験前に明確にしておきましょう。
理想的な目安:
-
Part 1(語彙)…15分
-
Part 2(短文読解)…20分
-
Part 3(長文読解)…50分
語彙問題で時間を節約し、長文に十分な余裕を残すことが重要です。
焦らず、1問あたりの平均ペースを意識して進めましょう。
6. メンタル面の準備も忘れずに
英検1級は長丁場の試験です。集中力を維持するために、次の点も意識しましょう。
-
試験前に軽くストレッチ・深呼吸
-
時計の位置と時間配分を確認
-
難しい問題に固執せず、迷ったら後回し
“完璧に解こうとしない”ことが結果的に高得点につながります。
本番では、知識よりも冷静さとリズムが勝負を分けます。
前日までの準備を信じて、いつものペースで英文を読むこと。それが最高の結果を引き出す秘訣です。
まとめ
英検1級のリーディングは、単なる「英語力テスト」ではなく、思考力・分析力・情報処理力が総合的に問われる試験です。難解な単語や抽象的なテーマに圧倒されがちですが、構造と論理を意識すれば、確実に理解できるようになります。
このパートを攻略するための本質は、次の3つに集約されます。
-
語彙力を“使えるレベル”まで高める
意味を覚えるだけでなく、文脈の中で使われ方を理解する。
派生語やコロケーションもセットで定着させる。 -
論理構造を読み取る力を鍛える
段落ごとの役割、接続詞、主語と動詞の関係を意識して読む。
文章の流れを「主張 → 理由 → 例 → 結論」として整理する。 -
時間管理と集中力を磨く
1問あたりの時間配分を守り、焦らずリズムよく進める。
模試形式の練習で“試験勘”を養い、後半の長文でも冷静さを維持する。
また、日常的に英字記事やエッセイを読むことで、背景知識と語彙を自然に強化できます。
英検1級のリーディングは、読書量と分析習慣が結果に直結するパートです。
「読む → 要約する → 分析する」という流れを毎日少しずつ積み重ねれば、必ず英文理解力が向上します。
そして試験本番では、自分が培ってきた読解の型を信じて、落ち着いて問題に向き合うこと。
リーディングを制すれば、英検1級合格はもう目前です。
よくある質問(FAQ)
英検1級のリーディングはなぜ難しいのですか?
英検1級のリーディングは、単語の難しさだけでなく、扱われるテーマが非常に抽象的で学術的な点が難関です。内容はニュース、科学、社会問題、哲学など幅広く、単語の意味を知っているだけでは解けません。筆者の主張、段落構成、論理展開を正確に把握する力が求められます。単語力とともに「英文の流れを読む力」が試される試験です。
語彙を効率よく覚えるにはどうすればいいですか?
単語を単独で暗記するのではなく、文脈の中で意味を理解することが重要です。
単語の「コアイメージ(核心的な意味)」を掴み、派生的な使われ方も関連づけて覚えましょう。
たとえば compound は「化合物」という名詞のほかに、「悪化させる」という動詞でも使われます。
語源・イメージを理解すれば、初めて見る使い方にも対応できます。
また、『英検1級パス単』などの単語帳に加えて、BBCやThe Economistなど実際の英語記事で単語を確認するのも効果的です。AnkiやQuizletといったアプリを使って「反復+音声」で記憶を定着させましょう。
難しい単語が多くて意味がわからないときは?
すべての単語を理解する必要はありません。
重要なのは、段落全体で何を主張しているのかを把握することです。
わからない単語が出てきた場合でも、前後の文脈や接続詞(however, therefore など)から推測できます。英検の問題は「1語の意味」よりも「文脈理解」を重視して作られています。
長文読解を効率よく進めるコツは?
まず段落ごとの役割を把握しましょう。
多くの英文は「導入 → 展開 → 結論」という構成になっています。
各段落の最初か最後の文が主題文になっていることが多いため、そこを中心に読むのが効果的です。
また、however, in contrast, as a result などの論理マーカーを意識すると、筆者の考えの流れをつかみやすくなります。段落ごとに「1文要約」をしながら読むと、内容が整理しやすくなります。
時間配分の目安を教えてください。
英検1級リーディングの制限時間は約85分です。
理想的な時間配分は以下の通りです。
-
Part 1(語彙問題):15分
-
Part 2(短文読解):20分
-
Part 3(長文読解):50分
語彙問題で時間を節約し、長文に余裕を残すのがポイントです。
1問に悩みすぎず、迷ったら一度飛ばして後で戻る勇気も必要です。
過去問はどう活用すれば効果的ですか?
過去問は「解く」だけでなく、「分析する」ことが大切です。
間違えた問題は、どの選択肢がなぜ誤りだったのかを明確にし、本文の根拠を探します。
また、設問タイプ(要旨・内容一致・推論)ごとに間違い傾向を整理しておくと、次の試験で同じミスを防げます。
英検公式問題集(旺文社)は最も信頼できる教材です。最低でも3周し、2回目以降は「解答根拠を探す練習」として使いましょう。
読解スピードを上げる練習法は?
スラッシュリーディング(意味のかたまりごとに区切る読み方)を習慣化しましょう。
英語を日本語に訳さず、英語の語順で理解する練習です。
また、音読やシャドーイングも効果的です。リズムや構文の感覚が身につき、読むスピードと理解力が同時に上がります。
さらに、短い英文を読んだ後に1行で要約する練習をすると、要点を瞬時に把握する力がつきます。
推論問題が苦手です。どうすれば克服できますか?
推論問題は、本文に直接書かれていない内容を「論理的に導く力」を問う問題です。
本文の事実・因果関係をしっかり把握し、筆者の意図を読み取る訓練をしましょう。
特に「筆者が示唆していることはどれか」という設問では、表現をそのまま繰り返す選択肢よりも、言い換え・要約された選択肢が正解になることが多いです。
背景知識はどれくらい必要ですか?
環境問題、科学技術、社会政策、心理学などの基本的な知識があると、読解スピードが大幅に上がります。
完全に専門知識を理解している必要はありませんが、よく出るテーマの概要をニュースやTEDトークで知っておくと、文章構成を予測しやすくなります。
リーディング練習はライティングにも役立ちますか?
はい。リーディングで身につけた構文理解や論理展開の感覚は、ライティング・スピーキングにも直結します。
文章を読んだ後に「筆者の主張を自分の言葉で英語で要約する」練習をすれば、論理的に意見を書く力が自然に身につきます。
試験前日にやるべきことは?
前日は新しい単語を覚えるより、これまでの復習に集中しましょう。
接続詞や論理マーカーを見直し、短い英文を音読して“英語脳”をウォームアップするのがおすすめです。
時間配分を再確認し、「どんな順番で解くか」を明確にしておくと、本番で焦らずに済みます。
最後に:リーディングを得点源にするために
英検1級のリーディングを制するカギは、
「語彙力 × 構造理解 × 時間管理」 の3要素を磨くことです。
日々の学習では、読むだけでなく「要約」「分析」「音読」をセットで行いましょう。
継続すれば、難解な英文も自然に理解できるようになります。