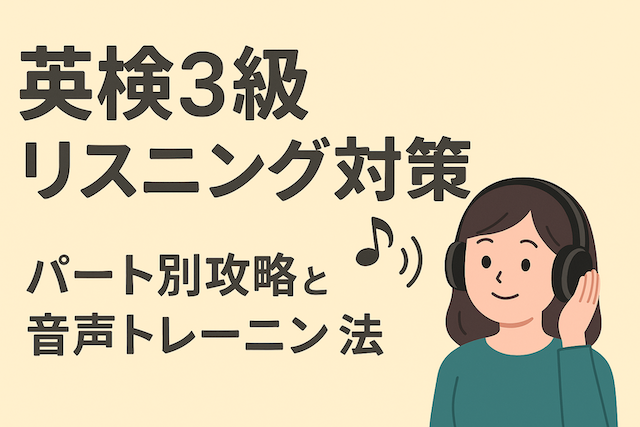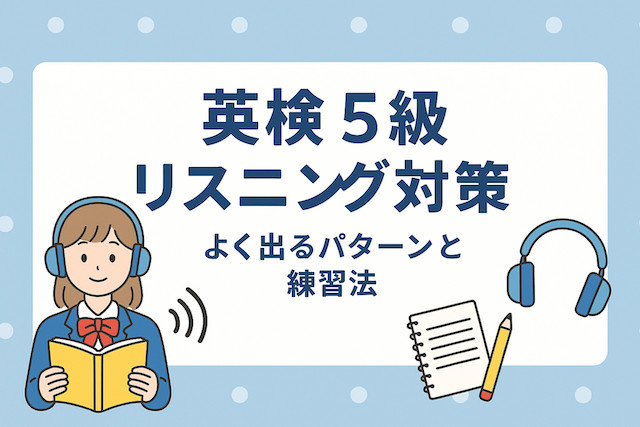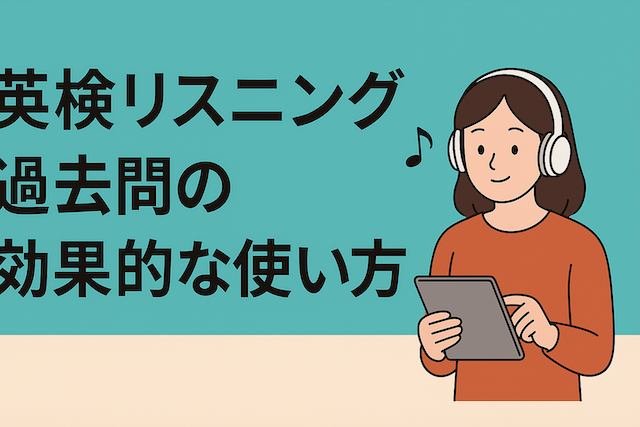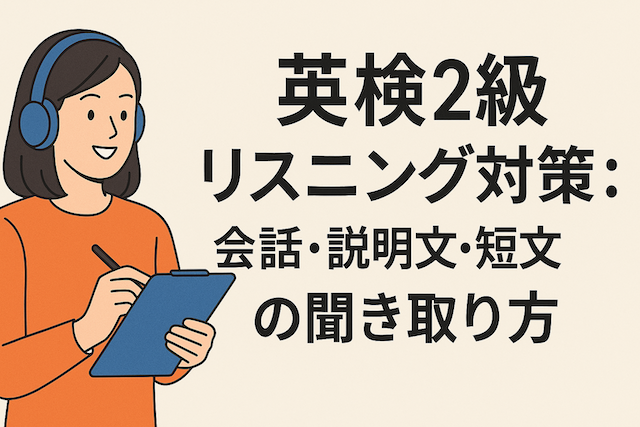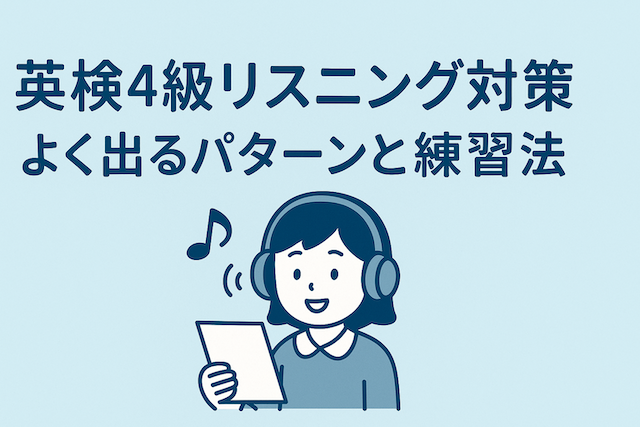目次
- 英検リスニング攻略法:スコアを上げる練習習慣
- はじめに
- 1. 英検リスニングで点数を上げるには「耳の習慣化」がすべて
- 2. レベル別リスニングの特徴と対策ポイント
- 3. スコアを上げるための「1日のリスニング習慣」
- 4. リスニング力を伸ばすおすすめ教材・アプリ
- 5. “伸び悩み”を感じたときのチェックリスト
- 6. 英検リスニング高得点者の共通点
- 7. まとめ:リスニングは“勉強”ではなく“習慣”
- よくある質問(FAQs)
- 英検リスニングは毎日どれくらい練習すれば良い?
- 「聞き流し」だけでも効果はある?
- どの級でも共通して伸ばすべき力は?
- 伸び悩んだときの最優先の見直しは?
- シャドーイングの正しいやり方は?
- ディクテーションはやるべき?
- 過去問は何周すればいい?
- おすすめの無料音源は?
- アプリは何を使えば良い?
- 忙しくて時間が取れないときの最小セットは?
- 何週間でスコアは上がる?
- 語彙はどう増やす?音で覚えるコツは?
- イギリス英語とアメリカ英語、どちらに合わせる?
- 本番直前の前日・当日の過ごし方は?
- 解答時に意識すべきことは?
- 中高生と社会人で学び方は変えるべき?
- リスニングだけでなくスピーキングも上げたい
- モチベ維持のコツは?
- よくあるミスを一つだけ直すなら?
- どの順序で練習するのが最適?
英検リスニング攻略法:スコアを上げる練習習慣
はじめに
英検のリスニングは、多くの受験者にとって最も点数が伸びにくい分野のひとつです。単語や文法を覚えても、実際の音声を聞くと「何を言っているのか分からない」という壁にぶつかる——そんな経験をした人は少なくありません。
しかし、リスニング力は特別な才能ではなく、“耳の習慣”をつくることで誰でも伸ばすことができるスキルです。
英検で高得点を取る人ほど、毎日少しずつ英語の音に触れ、耳を慣らす仕組みを生活の中に取り入れています。
本記事では、英検のリスニングパートでスコアを上げるための具体的な練習習慣と勉強の進め方を、レベル別に分かりやすく解説します。
忙しい人でも続けられる「毎日のリスニング習慣」づくりのコツや、おすすめ教材、伸び悩みを感じたときの見直しポイントまで、実践的に紹介します。
英語の音が「早い」「難しい」と感じていたあなたも、この記事を読み終える頃には、「こうすれば聞き取れるようになる」という明確な道筋が見えるはずです。
1. 英検リスニングで点数を上げるには「耳の習慣化」がすべて
英検のリスニング問題で高得点を取る人と、なかなか点数が伸びない人の差は、**知識量よりも「英語の音にどれだけ慣れているか」**にあります。
多くの学習者は「単語を覚える」「スクリプトを読む」といった文字中心の勉強に偏りがちです。しかし、リスニング力を伸ばすために本当に必要なのは、英語の音を毎日聞き、脳に“英語モード”を作ることです。
● リスニング力=慣れ × 反応 × 推測力
リスニング力は、単純に「耳がいい」かどうかではなく、次の3つの要素で成り立っています。
-
慣れ(Exposure):英語の音のリズムや発音パターンに日常的に触れているか
-
反応(Processing Speed):聞こえた音を意味に変換するスピード
-
推測力(Context Guessing):聞き取れない単語を文脈で補う力
つまり、「全部聞き取れない=ダメ」ではなく、聞こえた部分から意味を組み立てる練習が重要なのです。
● 「聞き流し」では伸びにくい理由
「英語を聞き流しているのに、全然伸びない」という声をよく聞きます。
これは、脳が“意味処理”をしていないためです。
英語の音をただ聞くだけでは、「英語のリズムに慣れる」効果はあっても、理解力や反応速度は鍛えられません。
効果的な方法は、集中して聞く時間と確認する時間をセットにすること。
1日15〜20分でも、
-
集中して聞く
-
スクリプトで答え合わせ
-
聞き直して確認
この3ステップを続ければ、確実に「音→意味」の変換速度が上がります。
● 習慣化のコツ
リスニングは“勉強時間を増やす”より、“習慣を固定する”ほうが大切です。
おすすめは次の3つ:
-
朝に5〜10分、英語の音を聞く(脳を英語モードに)
-
昼に1回、英検形式の問題を解く
-
夜にスクリプトを見ながらシャドーイング
このリズムを1〜2か月続けるだけでも、英語が「聞こえる感覚」が生まれます。
2. レベル別リスニングの特徴と対策ポイント
英検のリスニングは、級が上がるごとにスピード・語彙・内容の抽象度が少しずつ変化していきます。
つまり、5級と準1級では「聞く力の種類」自体が違うのです。
ここでは、各レベルごとの特徴と効果的な練習法を整理します。
● 5級〜3級:英語の音に慣れる「耳の基礎づくり」
特徴
・ゆっくりした日常会話が中心
・単語やフレーズの意味を問う問題が多い
・質問文が短く、選択肢もシンプル
対策
-
毎日10分の音読+リピーティング
→ スクリプトを見ながら音をまねる練習を。 -
日本語訳を見ずに「意味のイメージ」を持つ
→ “I’m thirsty.”を「のどが渇いた」ではなく「飲み物を求めている場面」として理解。 -
子ども向け英語番組・絵本音声を活用
→ “Peppa Pig”や“Super Simple Songs”など、短く分かりやすい音源がおすすめ。
● 準2級:文脈をつかむ「ストーリー理解力」を養う
特徴
・会話+説明文が混ざる
・一部に意見や理由が含まれる
・語彙レベルが上がり、スピードも速くなる
対策
-
文全体の流れをつかむ練習をする
→ 「誰が・何を・なぜ」話しているのかを意識。 -
英検過去問を音源中心で復習
→ 答え合わせよりも、「なぜそう答えるのか」を音から推測。 -
NHK World Easy Englishなどを聞き、要点を日本語でまとめる
● 2級:スピードと情報量の中で“取捨選択”する力を磨く
特徴
・会話スピードが速く、1文が長い
・質問内容が「理由・意図・要点」など理解型に変化
・一部でイディオムや日常表現が多く出る
対策
-
部分的に聞き取れなくても止まらない練習
→ “聞き逃した=終わり”ではなく、次の文で挽回する姿勢を。 -
「話の目的」を意識して聞く
→ 例:「Aは何をしようとしているか?」に集中。 -
TED-EdやYouTubeの短い英語スピーチを要約する
→ 要点を自分の言葉でまとめる力がリスニング力の土台になる。
● 準1級〜1級:意見・論理を聞き取る「思考リスニング」
特徴
・ニュース・インタビュー・ディスカッション形式
・抽象的なテーマ(環境・社会・テクノロジーなど)
・スピーカーの意見や感情を問う問題が多い
対策
-
英字ニュースやポッドキャストで多様なトピックを聞く
→ “The Guardian Audio Long Reads”や“BBC Learning English – 6 Minute English”など。 -
内容を自分の意見として要約・コメントする
→ 「私はどう思うか」を口に出すと理解が定着。 -
ディクテーション(書き取り)で正確さを鍛える
→ 難しい単語よりも、つなぎ音(リエゾン)を正確に認識する練習が有効。
✔ まとめ:レベルが上がるほど“理解型”へ
リスニング問題は、級が上がるごとに「音を聞き取る」から「話の流れを理解する」へと進化します。
つまり、**スコアアップの鍵は“英語の物語をイメージで理解できるか”**です。
次章では、こうした理解力を支えるための「毎日のリスニング習慣」を、時間帯別に紹介します。
3. スコアを上げるための「1日のリスニング習慣」
リスニング力は、一度に長時間勉強するよりも、毎日少しずつ音に触れる時間を積み重ねることで伸びていきます。
ポイントは「量」ではなく「リズム」。
1日を3つの時間帯に分けて、耳を英語に慣らすサイクルを作りましょう。
朝:英語の“耳慣らし”タイム(10〜15分)
朝は脳がリセットされていて、新しい音を吸収しやすい時間帯です。
ここでは「内容理解」よりも「音に慣れる」ことを目的にします。
おすすめのやり方
-
朝の支度中や通学・通勤中に英語音声を流す
-
内容は理解しようとせず、英語のリズムとイントネーションに集中
-
聞いたフレーズの1つでも口に出してまねしてみる
おすすめ音源
-
BBC Learning English
-
VOA Learning English
-
Apple Podcasts「All Ears English」など
ポイント:朝は「脳のスイッチを英語モードに入れる時間」と割り切りましょう。
☀️ 昼:集中リスニング練習(20〜30分)
昼は、英検の形式に近い音源を使って「集中トレーニング」を行う時間です。
この時間帯は、精聴(せいちょう:細かく聞く)+分析をセットにします。
ステップ練習法
-
一度聞いて解答 → 自分の感覚で答える
-
スクリプトを見て意味・音を確認
-
同じ音源をもう一度聞く(理解した状態で再確認)
この3ステップを繰り返すことで、「音」と「意味」の結びつきが強くなります。
1日1セット(10〜15問)でも効果は十分。
使いやすい教材
-
英検公式問題集(CD音声付き)
-
旺文社『英検リスニング問題120』シリーズ
-
アプリ「abceed」や「スタディサプリENGLISH」
ポイント:「答えを覚える」よりも「音と文の流れを理解」することを重視。
夜:シャドーイング&音読トレーニング(15〜20分)
夜は、1日の仕上げとしてシャドーイング(音を聞きながら同時に話す)を行います。
英語のリズムや音のつながりを体で覚える時間です。
ステップ
-
短い音声(30秒〜1分)を選ぶ
-
スクリプトを見て意味を理解する
-
音声を聞きながら、できるだけ同じスピードで声に出す
-
自分の発音を録音して確認する
シャドーイングの効果
-
英語の「音変化(リエゾン、脱落)」に強くなる
-
聞き取れない箇所の理由が明確になる
-
スピーキングにも直結する
ポイント:完璧を目指さず、「リズムとスピードをまねる」ことを意識。
習慣化のコツ
-
「短時間でも毎日やる」ほうが、週1時間まとめて聞くより効果的
-
タイマーを使い、朝・昼・夜の固定スロットにする
-
学習記録をアプリやノートに残して「見える化」する
リスニング力は“筋トレ”と同じで、サボるとすぐ衰えますが、続ければ確実に伸びる力です。
毎日このリズムを繰り返すことで、耳が自然と英語をキャッチできるようになります。
4. リスニング力を伸ばすおすすめ教材・アプリ
効果的なリスニング学習には、「レベルに合った教材を使うこと」と「使い方を固定すること」が重要です。
ここでは、英検対策・総合力アップ・日常慣れ、それぞれの目的に応じたおすすめ教材とアプリを紹介します。
英検対策に特化した教材
■ 英検公式問題集(旺文社)
最も信頼できるリスニング教材。
実際の試験と同じ形式・ナレーション・スピードで構成されており、“本番の耳”を作るにはこれが最適です。
使い方:
-
1回通して解く(模試形式)
-
答え合わせ後にスクリプトで音確認
-
聞き取れなかった箇所を集中反復
ポイント:同じ問題を3回繰り返すだけで、正答率が安定して上がる。
■ 『英検リスニング問題120』(旺文社)
級別に構成された実践型ドリル。
問題数が多く、日替わりで短時間学習に最適。
特に準2級〜2級の“スピード慣れ”に効果的です。
おすすめ活用法:
-
毎日1ユニット(5〜10分)を解く
-
スマホ音声をダウンロードして隙間時間にも練習
日常リスニング力を鍛える教材・メディア
■ NHK World Easy English
日本人向けに発音が明瞭で、ニュース内容もわかりやすい。
スクリプト・語彙リストが付いているので、中級者が文脈理解を練習するのに最適です。
■ BBC Learning English
多彩なシリーズ(6 Minute English, English at Work など)があり、
2級〜準1級レベルの耳慣らしにぴったり。
“イギリス英語”特有のイントネーションにも慣れられます。
■ VOA Learning English
アメリカ英語の標準的な発音。
スピードがゆっくりなので、準2級〜2級受験者に最適です。
短いトピックを毎日1つ聞くだけで、自然と語彙とリズムが定着します。
学習効率を上げるおすすめアプリ
| アプリ名 | 特徴 | 向いているレベル |
|---|---|---|
| abceed | 英検問題集を自動で管理・スコア予測機能つき | 3級〜1級 |
| スタディサプリENGLISH | スマホ1つで英検形式+会話練習まで完結 | 準2級〜準1級 |
| ELSA Speak | 発音矯正アプリ。シャドーイング練習にも◎ | 2級以上 |
| TED / TED-Ed | スクリプト付き短動画で上級者向けリスニング | 準1級〜1級 |
ポイント:どのアプリも「毎日開く時間」を固定して習慣化することが大切です。
アプリを“隙間時間の耳トレツール”として使うと、1日10分でも効果が積み上がります。
教材選びの基準
-
自分のレベル+1の難易度を選ぶ
→ 「少し速い・少し難しい」くらいが最も伸びる。 -
音声付き・スクリプト付き教材を選ぶ
→ 確認できる教材でなければ、復習ができない。 -
教材をコロコロ変えない
→ 1つの教材を3周以上使い込むのが最短ルート。
5. “伸び悩み”を感じたときのチェックリスト
どんなに努力していても、「ある程度までは伸びたのに、そこからスコアが止まってしまう」という時期があります。
リスニング力の伸び悩みは、“聞く量”の問題ではなく、“聞き方”のズレであることがほとんどです。
ここでは、原因を見つけるためのチェックポイントと、改善の方向性をまとめました。
✅ チェックリスト
| チェック項目 | 状況 | 改善の方向性 |
|---|---|---|
| □ 聞き流しだけで「集中して聞く時間」がない | なんとなく流して終わり | 「1日15分の集中リスニング」を設ける |
| □ スクリプトを確認せずに次へ進んでいる | 間違えた理由が不明 | 聞き取れなかった箇所をスクリプトで分析 |
| □ 音声を1回しか聞かない | 理解が浅く定着しない | 同じ音源を「初聴→確認→再聴」の3回聞く |
| □ 聞き取れない単語を放置している | 弱点が固定化 | その単語の「音と意味」を結びつけて復習 |
| □ 使う教材を頻繁に変えている | 脳が慣れず、成果が分散 | 1教材を3周使い込み、“耳が慣れる”まで固定 |
| □ 単語力・文法力に偏っている | 音として理解できていない | 音読・シャドーイングで耳と口のリンクを作る |
改善のための3つのアプローチ
1. 「聞く→読む→話す」ループを回す
聞き取れなかった部分をスクリプトで確認し、声に出して再現することで、音・意味・発音の三点が一致します。
リスニングは「読む力」と「発音力」を両方使う複合スキルです。
2. 「1音源×1週間」ルール
毎日違う音を聞くよりも、同じ音源を繰り返す方が効果的です。
脳が“予測”を始め、反応速度が上がります。
→ 英検の過去問1回分を1週間使い回すのが理想。
3. リスニングノートをつける
聞き取れなかった単語・フレーズをノートに書き出し、意味と音をセットで復習。
「なぜ聞こえなかったのか?」を分析すると、改善点が明確になります。
⚠️ よくある誤解
-
「とにかく量を聞けば上達する」→ ×
量だけでは「聞き取れる単語が増えない」。分析と復習が不可欠。 -
「全部聞き取れないと意味がない」→ ×
部分理解で十分。リスニングは“全体像をつかむ力”の方が得点につながる。 -
「自分は耳が悪い」→ ×
ほとんどのケースは、慣れと処理速度の問題。時間をかければ必ず改善する。
まとめ:停滞期は“再構築”のチャンス
リスニング力の伸び悩みは、「勉強しているのに成果が出ない」と感じる時期に必ず訪れます。
しかし、それは成長が止まったのではなく、次のレベルに進む前の準備段階です。
一度立ち止まり、
-
学習の“質”を見直す
-
聞き方を変える
-
復習の習慣を整える
この3点を意識するだけで、再びスコアが動き出します。
6. 英検リスニング高得点者の共通点
英検のリスニングで安定して高得点を取る人には、共通する「学習の型」があります。
それは“努力量”よりも“習慣の質”に表れます。ここでは、上位スコア層に見られる5つの特徴を紹介します。
① 毎日「音のある環境」をつくっている
高得点者は、英語を特別な勉強ではなく“生活の一部”として聞いている人が多いです。
朝の支度中や通勤時間、家事中など、無理のない範囲で英語音声を常に流しています。
-
通勤時にBBCやVOAを聞く
-
朝食時に英語ニュースを再生
-
スマホでPodcastを登録し、自動再生する
ポイント:耳を“英語環境に浸す”ことで、自然と脳が英語モードに切り替わる。
② 同じ音源を繰り返し使っている
「一度聞いて終わり」ではなく、1つの教材を繰り返すのが上位者の特徴です。
リスニングは反復するほど“予測力”が働き、音を先読みできるようになります。
-
英検の過去問1回分を1週間使い回す
-
シャドーイングは同じ音源を5回以上
-
苦手トピックを“暗唱できるレベル”まで反復
ポイント:新しい教材よりも、「聞き慣れた教材を使いこなす」方が効果的。
③ スクリプトを分析して「原因」を探している
上位者は、間違えた問題を“なんとなく復習”しません。
聞き取れなかった原因を分析し、次に同じミスをしないようにしています。
分析の例:
-
音がつながって聞こえなかった(発音問題)
-
単語の意味を知らなかった(語彙問題)
-
文脈を追えていなかった(集中力問題)
ポイント:「なぜ聞けなかったか」を1日1つでも明確にすることで、再現性のある成長が生まれる。
④ 模試や過去問を「本番のように」解いている
高得点者は、定期的に模試形式の練習を取り入れています。
本番の緊張感・集中力・時間感覚を再現することで、実戦力が鍛えられます。
-
週1回は過去問を時間通りに解く
-
結果をスプレッドシートに記録して弱点を可視化
-
ミスの傾向(Partごとの得点差)を分析
ポイント:得点の“波”を減らすことで、安定して合格ラインを超えられる。
⑤ 「聞く・話す・読む・書く」をつなげて学んでいる
リスニング力は、他の技能と密接に関係しています。
特にスピーキングと音読練習を並行すると、音への感度が飛躍的に上がります。
-
シャドーイング+音読で発音を身体化
-
英語日記を読み上げて「聞き取り→発話」の循環を作る
-
聞いたフレーズを自分の口で再現
ポイント:リスニング単独ではなく、英語を「出す」練習が“聞ける力”を育てる。
まとめ:高得点者は“英語を生活の中で使う人”
英検リスニングで高得点を取る人は、特別な才能を持っているわけではありません。
共通しているのは、「英語を勉強ではなく習慣にしている」ということ。
-
毎日音声を聞く
-
同じ教材を反復する
-
分析して改善する
この3点を続けるだけで、英検のスコアは必ず伸びます。
次章では、最後に全体のまとめとして、リスニング上達を持続させるための心構えをお伝えします。
7. まとめ:リスニングは“勉強”ではなく“習慣”
英検のリスニングは、短期間で劇的に上がるスキルではありません。
しかし、正しいやり方で毎日少しずつ積み重ねることで、必ず成果が出る分野でもあります。
「量よりリズム」で耳を育てる
1日2〜3時間の“詰め込み学習”よりも、
毎日20〜30分のリスニング習慣を続ける方が圧倒的に効果的です。
英語を「勉強する対象」から「毎日の音」として生活に溶け込ませる。
それが、リスニング上達の最大の近道です。
朝の10分でも、通勤の5分でも構いません。
継続的に英語を聞く時間を設けることで、脳が「英語の音を理解できるモード」に切り替わっていきます。
習慣を継続するための小さなコツ
-
同じ時間・同じ場所でリスニングする(例:朝食後の10分)
-
聞く教材を1週間ごとに固定する(迷わない)
-
聞いた内容を一言でもアウトプットする(口に出す・書く)
-
結果をノートやアプリで“見える化”する
小さな積み重ねを「記録」することで、自信がリズムを支える。
リスニング力が伸びると、英語全体が変わる
リスニングが上達すると、スピーキング・リーディング・ライティングすべてに好影響が出ます。
なぜなら、英語の「音」と「意味」が脳内で結びつき、英語を“日本語を介さず理解できる状態”になるからです。
その結果:
-
スピーキングで自然なイントネーションが出る
-
読むスピードが上がる
-
単語や文法が「使える知識」に変わる
リスニングは、英語力全体を底上げする最も効率的な学習分野です。
最後に
リスニングは、才能ではなく習慣で決まるスキルです。
英検のスコアアップを目指すなら、
-
「聞く時間」を生活に組み込み、
-
「同じ音源」を反復し、
-
「原因分析と改善」を繰り返す。
この3ステップを続けるだけで、確実に耳が変わっていきます。
明日からの10分が、あなたの次のスコアを作ります。
今日から“英語の音を聞く日常”を始めましょう。
よくある質問(FAQs)
英検リスニングは毎日どれくらい練習すれば良い?
合計30〜45分を目安に、朝10分(耳慣らし)+昼20分(精聴&過去問)+夜10〜15分(シャドーイング)の3分割がおすすめです。長時間よりも毎日の継続が効果的です。
「聞き流し」だけでも効果はある?
聞き流しはリズム慣れには役立ちますが、得点アップには不十分です。集中して解く→スクリプト確認→再聴の3ステップを最低1セット入れてください。
どの級でも共通して伸ばすべき力は?
慣れ(露出)× 反応速度 × 文脈推測の3要素です。全部聞き取れなくても、文脈から補う練習を重視しましょう。
伸び悩んだときの最優先の見直しは?
次の2点を即実行:
① 同じ音源を初聴→確認→再聴で最低3回回す。
② スクリプトで「聞けなかった原因(音変化/語彙/集中)」を1つ特定して対策。
シャドーイングの正しいやり方は?
30〜60秒の短音源を選び、意味を理解→音声に0.5秒遅れて重ねる→録音して癖を確認。完璧さよりもリズムとスピード模倣を優先します。
ディクテーションはやるべき?
準1級以上や「音の脱落・連結」が苦手な人に効果的です。週2〜3回、1回5分でOK。やりすぎると時間効率が落ちるのでポイント練習に限定。
過去問は何周すればいい?
最低3周を目安に。同一回を1週間使い倒すと「予測」が働き、反応速度が上がります。正解を覚えるのではなく、音と意味の一致を目的に。
おすすめの無料音源は?
BBC Learning English、VOA Learning English、NHK World Easy English。いずれもスクリプトがあり、精聴と再聴がしやすいのが利点です。
アプリは何を使えば良い?
英検対策はabceed、総合練習はスタディサプリENGLISH、発音矯正はELSA Speak、上級の要約力はTED/TED-Ed。毎日開く時間を固定すると継続しやすいです。
忙しくて時間が取れないときの最小セットは?
合計15分:朝5分の耳慣らし+昼5分の1セット精聴+夜5分シャドーイング。短くても3スロットに分けるのがコツです。
何週間でスコアは上がる?
個人差はありますが、4〜8週間の継続で安定感が出やすいです。学習記録を取り、正答率・聞き取り箇所の傾向を可視化しましょう。
語彙はどう増やす?音で覚えるコツは?
単語帳だけでなく、音声付きスクリプトで「発音・アクセント・使われ方」をセットで定着。聞こえなかった語は必ず音で再確認し、声に出して再現します。
イギリス英語とアメリカ英語、どちらに合わせる?
どちらにも触れておくのが理想ですが、まずは自分が受けやすい音(例:米音)で土台を作ってから英音にも慣れましょう。BBCとVOAを交互に使うのが簡単です。
本番直前の前日・当日の過ごし方は?
前日:同じ音源を軽く再聴して成功体験で終える/夜更かし厳禁。
当日:10分の耳慣らし→試験30分前から静かに英語モードを維持。直前の新規学習は避けます。
解答時に意識すべきことは?
設問先読みで「何を聞くか」を決める→聞き逃しても次で挽回→根拠が薄い選択肢は消去法。迷ったら「話の目的・理由・結果」に合うものを選ぶ。
中高生と社会人で学び方は変えるべき?
原則は同じですが、社会人は短時間・高密度に、中高生は毎日コツコツの時間設計が合います。いずれも朝の耳慣らしは効果大。
リスニングだけでなくスピーキングも上げたい
シャドーイング後に要約を自分の言葉で30秒話す「聞く→話す」循環が最短です。録音してフィードバックすると改善が加速します。
モチベ維持のコツは?
教材を週単位で固定し、チェックリストとスコア記録をつける。小さな達成(連続日数・再聴回数)を可視化して自己効力感を保ちます。
よくあるミスを一つだけ直すなら?
スクリプトを読まずに次へ進むこと。必ず原因分析→再聴まで実施し、同じ誤りを繰り返さない仕組みを作りましょう。
どの順序で練習するのが最適?
耳慣らし → 精聴(過去問) → スクリプト確認 → 再聴 → シャドーイング →(可能なら)要約発話。このループを毎日回せば着実に伸びます。