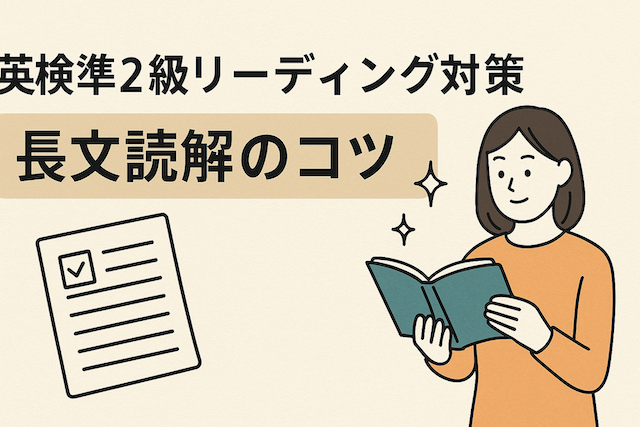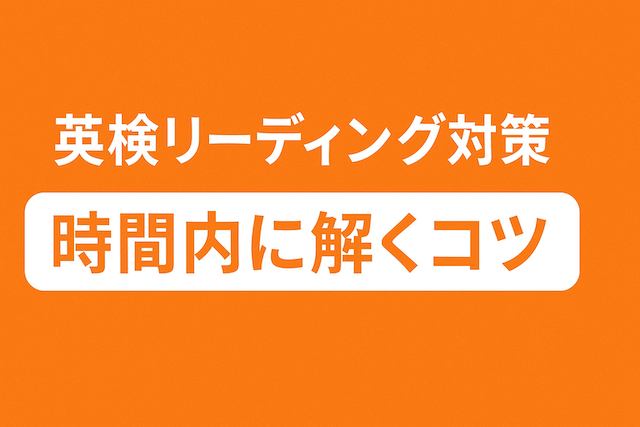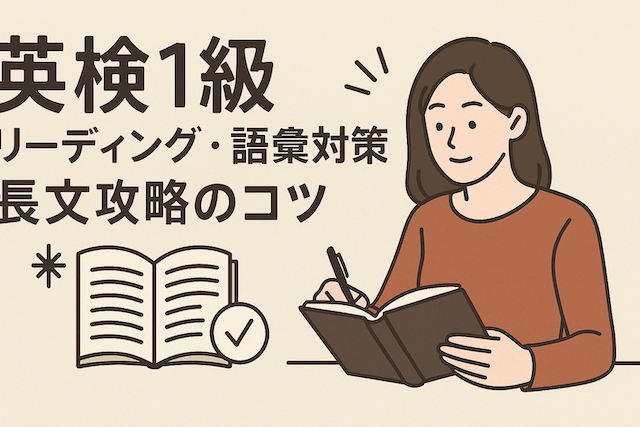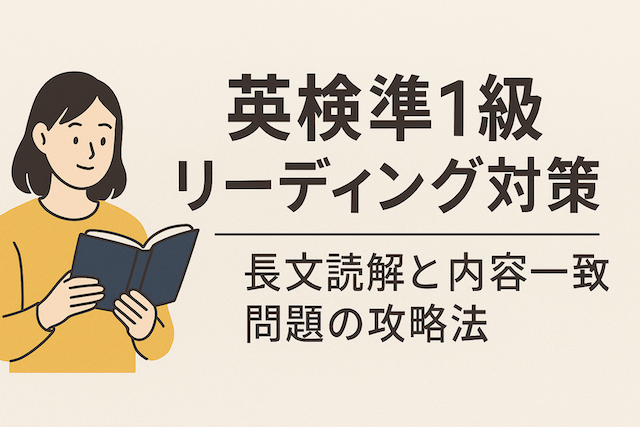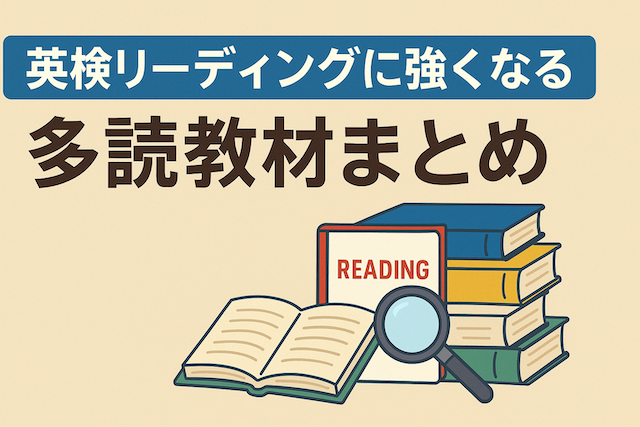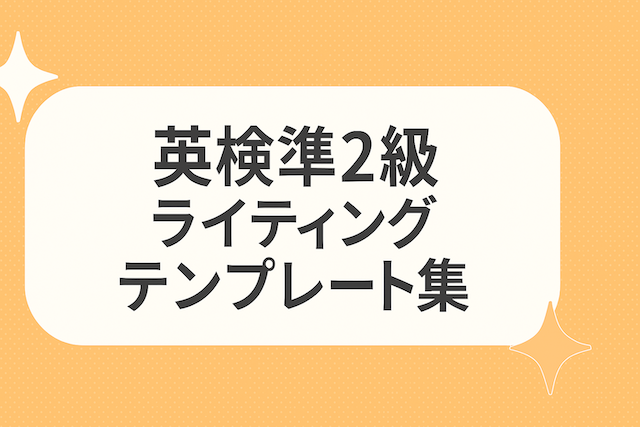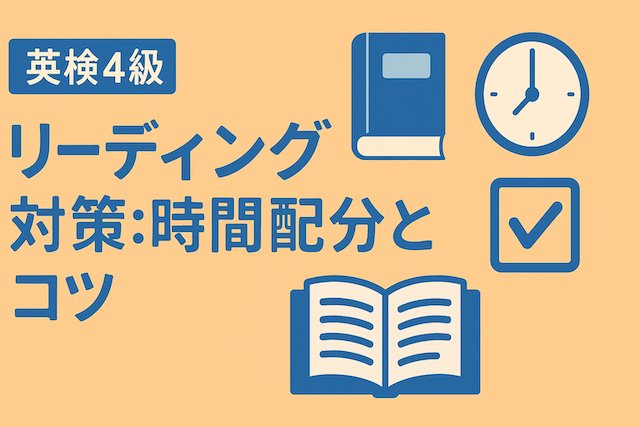目次
英検準2級リーディング対策:長文読解のコツ
はじめに
英検準2級のリーディングパートは、英文を正確に理解し、必要な情報を素早く見つける力が問われる重要なセクションです。語彙や文法の基礎を押さえていても、「長文になると時間が足りない」「選択肢の意味が似ていて迷う」と感じる受験者は多いでしょう。
準2級では、説明文・記事・Eメール・案内文など、日常的なトピックを扱う長文が中心です。そのため、単に英文を読むだけでなく、筆者の意図をつかむ読解力と、効率的に情報を処理するスキルが求められます。
この記事では、英検準2級のリーディング問題、とくに長文読解で得点を伸ばすための具体的なコツと練習法をわかりやすく紹介します。英語が少し苦手でも、「読む順番」「注目すべきポイント」を意識すれば、確実にスコアアップできます。
リーディングの出題構成を理解しよう
まずは、英検準2級のリーディングセクションがどのように構成されているのかを把握しましょう。出題形式を理解しておくことで、どの問題にどれくらい時間を使うべきかが明確になり、試験本番で焦らずに対応できます。
| パート | 内容 | 問題数 | 目安時間 |
|---|---|---|---|
| Part 1 | 短文の空所補充(語彙・文法) | 約10問 | 約10分 |
| Part 2 | 会話文の穴埋め | 約5問 | 約5分 |
| Part 3 | 長文読解(説明文・Eメール・記事など) | 約10問 | 約25分 |
リーディング全体は約40分で解く必要があります。特にPart 3の長文読解は文章量が多く、配点も高いため、ここでしっかり得点できるかどうかが合否を左右します。
準2級の長文は、「環境問題」「ボランティア活動」「文化紹介」「科学技術」「学校生活」など、身近なテーマをもとにした英文が多いのが特徴です。英語力だけでなく、一般的な知識や背景理解もあると読みやすくなります。
ポイント
長文のトピックは中学生~高校生が興味を持つ内容が中心
文体はフォーマルすぎず、実用的な英語
読解では「主旨」「理由」「具体例」などを問う問題が多い
出題構成を把握したら、次は長文読解を効率よく解くためのコツを学んでいきましょう。
長文読解のポイント①:設問を先に読む
英検準2級の長文問題では、本文を読む前に設問(質問文)をチェックするのが最も効果的なテクニックのひとつです。
なぜなら、あらかじめ「何を探せばいいのか」を意識して読むことで、無駄な読み返しを防ぎ、読解スピードと正答率の両方を上げられるからです。
なぜ先に設問を読むのか?
設問を先に読むことで、本文を読む際に「答えのヒントがどこにあるか」を意識できるようになります。
これにより、重要な部分を見逃さずに済みます。
例:
Q. Why did the writer decide to start the project?
→ この質問を先に読んでおけば、「筆者がプロジェクトを始めた理由」に関係する部分を注意して読むことができます。
逆に、設問を読まずに本文を最初から最後まで読むと、内容をすべて理解しようとして時間が足りなくなるケースが多いです。英検準2級では1つの長文に約300〜400語あり、全てを完璧に理解する必要はありません。
効果的な読み方の手順
-
設問を先に読む(3〜4問)
-
キーワード(who, why, what, whereなど)をチェック
-
本文をざっと読み、該当箇所で丁寧に読む
-
選択肢を照らし合わせて確認する
この流れを習慣にすると、読解時間が1題あたり2〜3分短縮できます。
ヒント
設問中のキーワードには線を引く(why / main reason / according to など)
答えは通常、本文の順番通りに出てくる
「not true」「incorrect」など否定表現を見落とさないよう注意
長文読解のポイント②:段落ごとの要点をつかむ
英検準2級の長文では、1つのテーマをもとに3〜4段落で構成された文章が多く出題されます。
段落ごとに「何について書かれているのか」を意識しながら読むことで、内容の流れを理解しやすくなり、設問に素早く対応できます。
段落ごとにメモを取るイメージで読む
本文を読んでいるときは、各段落をざっくりと以下のように整理してみましょう。
例:
-
第1段落:筆者の体験や背景説明
-
第2段落:問題点の提示や具体的な出来事
-
第3段落:解決策や結果
-
第4段落:まとめ・筆者の意見
このように「流れ」をつかむと、設問で「What is the main idea of the third paragraph?」と問われても、すぐに答えを導き出せます。
段落の冒頭と末文を意識する
筆者は段落の最初か最後の文に、その段落の主旨をまとめることが多いです。
つまり、「最初の1文」と「最後の1文」を注意深く読むだけでも、要点を把握しやすくなります。
例:
(1st sentence) Many students in Japan want to study abroad.
→ この段落は「日本の学生が留学を望む理由や背景」についての説明になる可能性が高い。
(last sentence) For this reason, more schools have started exchange programs.
→ 結論として「交換留学制度を始める学校が増えている」とまとめている。
練習法のコツ
-
段落ごとに一言で要約する練習をする(例:「背景」「理由」「結果」など)
-
過去問を使い、各段落の要点を書き出すトレーニングをする
-
英文を声に出して読むと、構成の流れがつかみやすくなる
ポイント
段落=情報のかたまりとして理解する
長文全体の構成を意識すれば、本文のどこに答えがあるか探しやすくなる
長文読解のポイント③:接続詞と指示語に注目
英検準2級の長文を読むときは、**接続詞(conjunctions)と指示語(reference words)**に注目することが非常に重要です。
これらは文章の「論理のつながり」や「筆者の意図」を理解するカギとなります。
接続詞で文章の流れをつかむ
接続詞は、文と文の**関係性(対比・理由・結果など)**を示します。
特に、次のような単語が出てきたら注意して読みましょう。
| 意味 | よく出る接続詞 | 読み方のポイント |
|---|---|---|
| 逆接 | however, but, on the other hand | 意見が逆転する合図。前後の内容を対比する。 |
| 理由 | because, since, as | 原因や理由の説明が続く。 |
| 結果 | so, therefore, as a result | 重要な「結論」が来るサイン。 |
| 追加 | also, in addition, moreover | 同じ内容を補強する部分。 |
| 例示 | for example, such as | 筆者の主張を支える根拠。 |
例:
She was tired. However, she continued studying.
→ 「疲れていたが、それでも勉強を続けた」=意見の転換。
このように、接続詞を見つけたら、文の関係性を意識して読むことで内容の整理がスムーズになります。
指示語の「指す内容」を確認する
“this”, “that”, “it”, “they”, “these”, “those” などの指示語が出てきたときは、「それ」が何を指しているのかを確認しましょう。
例:
Many people started recycling. This helped reduce waste.
→ “This” は「多くの人がリサイクルを始めたこと」を指している。
指示語を正確に理解できないと、設問で「内容一致」や「理由説明」を間違える原因になります。
特に “it” や “they” は前の文の名詞を指すので、前後をまとめて読む習慣をつけましょう。
練習法
-
過去問や模試の英文で、接続詞と指示語にマーカーを引く
-
それぞれの語が「どんな関係を示しているか」をメモする
-
文のつながりを意識して要約する
ポイント
接続詞=文の流れを示す「道路標識」
指示語=前後の文をつなぐ「橋」
この2つを見逃さなければ、筆者の意図を正確に読み取れます。
長文読解のポイント④:具体例と結論を見逃さない
英検準2級の長文では、筆者の主張を強調するために**具体例(example)や結論(conclusion)**がよく使われます。
これらの部分を正しく読み取れると、内容一致問題・主旨問題・理由説明問題をスムーズに解けるようになります。
「具体例」は筆者の主張を裏づける部分
文章中で “for example”, “for instance”, “such as” などが出てきたら、その後に来る文は筆者の意見を支える根拠や実例です。
つまり、「何を言いたいのか」を具体的に説明している部分になります。
例:
Some people prefer online shopping. For example, they can compare prices easily.
→ 筆者の主張「ネットショッピングを好む理由」を、具体例で説明している。
コツ:
-
“for example” の後に出てくる内容は、主張のヒントになる。
-
設問で「Why」や「What is the reason」などと問われた場合は、この部分に答えがあることが多い。
「結論表現」は文章全体のまとめ
筆者が文章をまとめるときに使う表現にも注目しましょう。
以下のような語句が出てきたら、「これが筆者の最も言いたいこと」と考えてOKです。
| 結論を示す表現 | 意味 |
|---|---|
| in conclusion | 結論として |
| as a result | 結果として |
| therefore | したがって |
| in short / to sum up | 要するに |
例:
In conclusion, learning another language gives us more opportunities.
→ 「結論として、外国語を学ぶことはチャンスを広げる」と筆者の主張を明確にしている。
このような「結論サイン」を見逃さずに読むことで、設問の “main idea(主旨)” や “purpose(目的)” に強くなります。
練習法のヒント
-
過去問の長文を使い、「for example」「in conclusion」などにマーカーを引く
-
その部分の英文を日本語で要約してみる
-
「筆者が伝えたかったこと」を一文で書き出す
ポイント
“for example”=主張を支える根拠
“in conclusion”=筆者の最終意見
“therefore / as a result”=因果関係を示す
長文読解のポイント⑤:選択肢の「言い換え」に注意
英検準2級のリーディング問題では、本文と全く同じ表現が選択肢に登場することはほとんどありません。
正解の選択肢は、本文の内容を別の英語表現で言い換えていることが多いのです。
この「言い換え(paraphrasing)」を見抜く力が、得点アップのカギになります。
なぜ言い換えが多いのか?
英検では、単純な単語の一致ではなく、**意味の理解力(reading comprehension)**を測るために、本文と選択肢を異なる表現で書き換えています。
したがって、「本文に同じ単語がある=正解」ではなく、内容が同じ意味かどうかを判断しなければなりません。
言い換えの代表例
| 本文の表現 | 選択肢の言い換え例 | 意味の関係 |
|---|---|---|
| She enjoyed helping others. | She was happy to support people. | enjoy=be happy to |
| He decided to join the event. | He made up his mind to take part in it. | decide=make up one’s mind |
| The company started a new project. | A new project was launched by the company. | start=launch |
| Students can easily access information. | It is easy for students to get information. | access=get |
このように、同じ意味でも文の形や語彙が違うだけで、見た目が全く異なる選択肢になります。
言い換えを見抜く練習法
-
過去問や模試の正解文を分析する
→ 本文と選択肢で「どの単語が置き換えられているか」を確認。 -
同義語・関連語をノート化する
→ 例:important=essential=crucial=necessary -
英文ニュースやリーディング教材で言い換えを意識して読む
ポイント
単語の一致よりも、意味の一致を重視する
文の構造が違っても「主語・動詞・目的語」の関係を確認
「同じ意味なのに言い方が違う」表現をストックする
例題で確認
本文:
Many people started using bicycles because they are good for health and the environment.
選択肢:
People began to ride bikes as they are healthy and eco-friendly.
→ “started using bicycles” と “began to ride bikes” は言い換え、
“good for health and the environment” と “healthy and eco-friendly” も言い換え。
内容が一致しているため、正解です。
長文読解の練習法
英検準2級のリーディング力を上げるためには、正しい方法で継続的に練習することが重要です。
ただ「たくさん読む」だけでは効果が出にくく、時間管理・分析・復習の3ステップを意識することで、実力を確実に伸ばすことができます。
① 過去問を時間を計って解く
まずは、英検公式過去問や問題集を使って制限時間内に解く練習をしましょう。
準2級ではリーディング全体に約40分あるため、長文1題にかけられる時間は7〜8分程度です。
最初は時間を気にせず正確に解き、慣れてきたら徐々にスピードを上げていくとよいでしょう。
ポイント
・1回目は「内容理解」を重視
・2回目は「時間配分」を意識
・3回目は「設問を先読みして解く」練習
② 間違えた問題の「根拠」を探す
間違えた問題は、なぜその選択肢が間違いなのか、正解の根拠はどの文にあるのかを必ず確認しましょう。
本文のどこで答えを見つけるべきだったかを理解することが、次回の正答率アップにつながります。
復習のコツ:
-
本文の該当箇所にマーカーを引く
-
正解と不正解の選択肢を日本語で比較する
-
「この選択肢はなぜダメか?」を自分の言葉で説明してみる
③ 段落ごとに要約する練習をする
本文を読み終えたら、各段落を一文で要約するトレーニングをしましょう。
内容理解の確認にもなり、主旨把握問題にも強くなります。
例:
-
第1段落:筆者がボランティアを始めた理由
-
第2段落:活動内容の紹介
-
第3段落:その経験から学んだこと
このように要約を続けることで、「何を伝えたい文章なのか」を掴む力が自然に身につきます。
④ 定期的に模試を解いて実力をチェック
学習の進捗を確認するために、2〜3週間に1回は模試を実施するのがおすすめです。
特に英検公式問題集や旺文社・学研などの模試形式教材は、本番に近い形式・語彙レベルで練習できます。
継続のコツ
「1日1長文」を目標に無理なく続ける
スマホアプリでリーディング練習をする
日本語訳を読んで理解を深めるよりも、英語で意味をつかむ練習を意識
読解力を伸ばすためのおすすめ勉強素材
英検準2級の長文をスムーズに読めるようになるには、試験対策+日常英語の両面から英語を読む習慣を作ることが大切です。ここでは、実際に受験者に人気のある教材・サイトを紹介します。
① 『英検準2級 過去6回全問題集』(旺文社)
最も定番で信頼できる教材です。
過去6回分の本試験問題が収録されており、問題傾向の分析・時間配分の練習・出題頻度の高い語彙チェックまで一冊でできます。
解説も丁寧なので、初心者でも自習しやすい構成になっています。
使い方のコツ
1回目は制限時間を気にせず理解を重視
2回目以降は「本番形式」で時間を計って解く
間違えた問題は本文にマーカーを引いて復習
② NHK WORLD “News Easy”
NHKが配信する「やさしい英語ニュース」。
ニュース英語を英検準2級レベル程度の語彙と文法で書いているため、長文読解の実践教材として最適です。
日本語訳付きで、難しい語句も解説されています。
NHK WORLD News Easy
(スマホ・PCどちらでも無料で読めます)
③ VOA Learning English
アメリカのニュースを「ゆっくり話す英語」で学べる無料サイト。
時事・文化・テクノロジー・環境など、英検の長文テーマに近い内容が多く、リスニング対策にもなります。
音声とスクリプトがあるので、読んで→聞いて→シャドーイングすることで理解が深まります。
④ 英検公式サイト(無料)
英検の公式サイトでは、過去問・リーディング問題・リスニング音声が無料でダウンロードできます。
本番に最も近い形式なので、模試前の仕上げに最適です。
⑤ 英語多読用アプリ(Oxford Reading Clubなど)
もしスマホ学習を取り入れるなら、Oxford Reading Club や Xreading などの多読アプリもおすすめです。
1話が短く、英検準2級レベルにちょうどよい難易度で読解スピードを鍛えられます。
コツ
知らない単語を辞書で調べず、前後関係で意味を推測する練習をする
1日1記事、2週間続けるだけで「英語を読むのが怖くなくなる」
時間配分のコツ
英検準2級のリーディングでは、限られた時間の中で正確に読み取るスピード力が求められます。
全体で約40分という制限時間の中で、各パートにどれくらい時間を使うかを事前に決めておくと、本番で焦らずに済みます。
セクションごとの理想的な時間配分
| パート | 内容 | 目安時間 | ポイント |
|---|---|---|---|
| Part 1 | 短文の空所補充(語彙・文法) | 約10分 | わからない問題は後回し。スピード重視。 |
| Part 2 | 会話文の穴埋め | 約5分 | 文脈と自然な返答を意識。 |
| Part 3 | 長文読解(3題前後) | 約25分 | 設問先読み+段落要約で効率的に読む。 |
長文1題あたり7〜8分を目安に進めましょう。
1題に時間をかけすぎると、残りの問題が手つかずになることが多いので要注意です。
時間を節約するテクニック
-
わからない単語は飛ばす
→ 文全体の意味をつかむことを優先。1語にこだわらない。 -
設問のキーワードを本文で探す
→ “because”, “main reason”, “what happened” などの語を目印に。 -
本文を最初から最後まで丁寧に読まない
→ 段落の最初と最後、設問に関係する部分を重点的に読む。
ヒント
「読めない単語=落ち着いて推測する」
「焦って全部読まない」
「1問あたりに使う時間を決めておく」
実践トレーニング方法
-
模試を解くときにストップウォッチを使う
-
各パートの終了目安時刻をメモしておく
-
本番同様の時間で「通し練習」を3回以上行う
こうした時間感覚の訓練を重ねることで、試験当日も落ち着いて解けるようになります。
まとめ
英検準2級のリーディングは、単語力や文法知識だけではなく、英語の論理をつかみながら内容を理解する力が問われます。
長文を読むのが苦手でも、コツを押さえて練習を重ねれば、確実に得点できるようになります。
✅ この記事のポイントまとめ
-
設問を先に読む:読む目的を明確にしてスピードアップ
-
段落ごとに要点をつかむ:内容の流れを理解しやすくする
-
接続詞と指示語に注目:文の関係や筆者の意図を読み取る
-
具体例と結論を見逃さない:主張の根拠と結論を意識する
-
言い換え表現に慣れる:本文と選択肢の意味の一致を見抜く
-
時間配分を意識:長文1題に7〜8分が目安
継続が合格への近道
リーディング力は、一朝一夕で身につくものではありません。
しかし、毎日少しずつ英語を読む習慣を続けることで、理解スピードと正答率が自然に上がります。
過去問・ニュース・短い英語記事など、どんな教材でも構いません。継続が最大の武器です。
「読む量 × 正しい方法」= 英検合格への最短ルート
英検準2級のリーディングに自信をつけて、次の級へのステップアップを目指しましょう!
次にこの