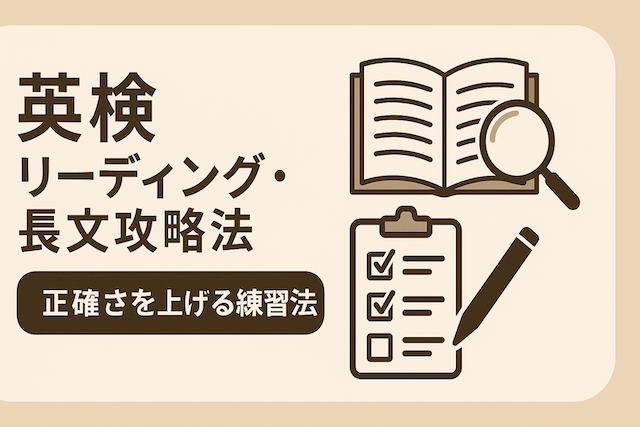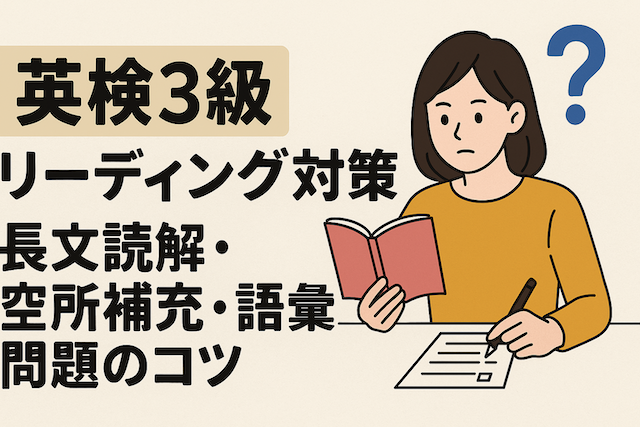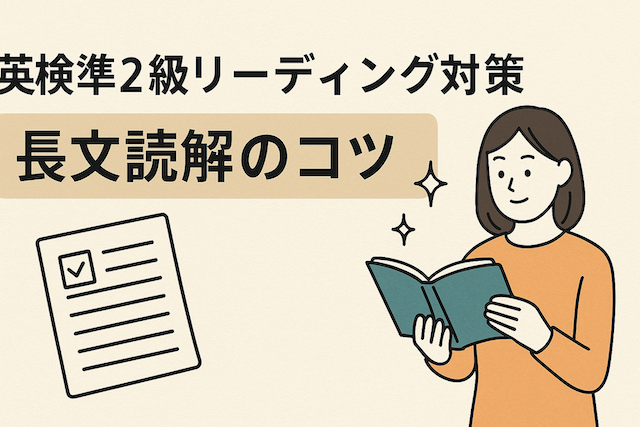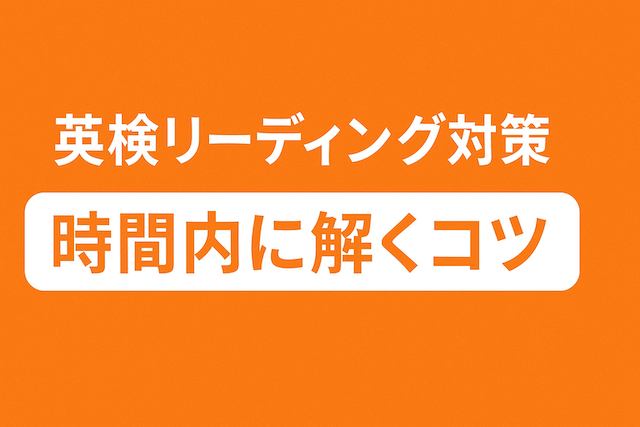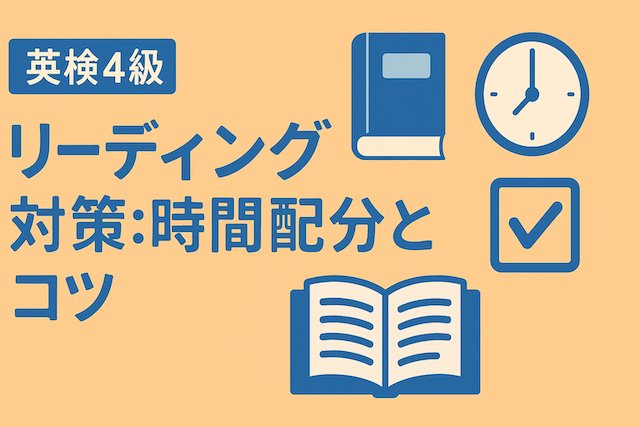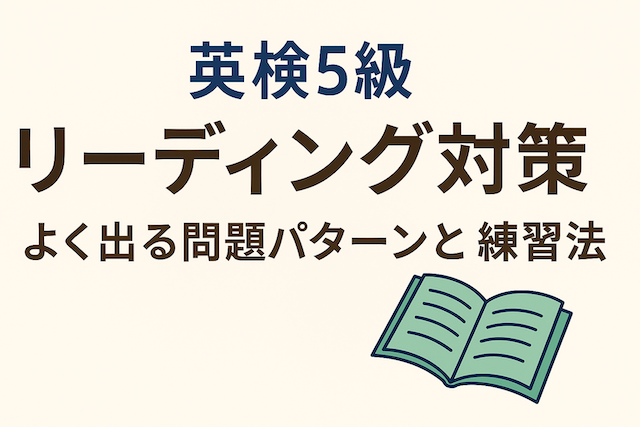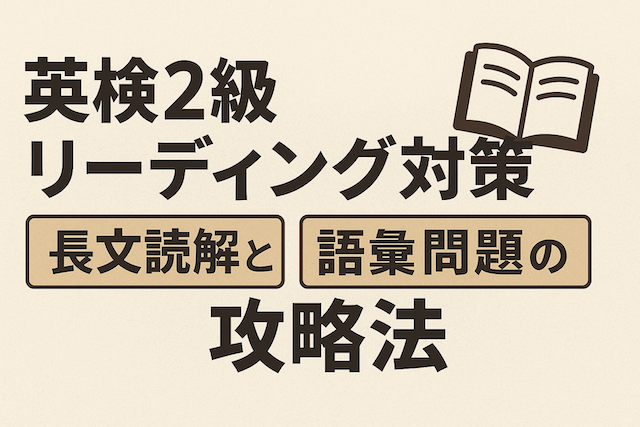目次
- 英検リーディング・長文攻略法:正確さを上げる練習法
- はじめに
- 読解で「正確さ」が求められる理由
- ステップ1:スラッシュリーディングで構造をつかむ
- ステップ2:パラグラフごとの要点をまとめる
- ステップ3:根拠の場所を明示する「証拠探し」訓練
- ステップ4:精読と速読をバランスよく
- ステップ5:設問タイプ別の読み方を意識する
- ステップ6:音読で読解精度を上げる
- ステップ7:過去問分析で弱点を把握する
- まとめ
- よくある質問(FAQ)
- 英検の長文で「正確さ」を上げるには何から始めればいい?
- 速読と精読はどちらを優先すべき?
- 「根拠探し」はどうやって練習するの?
- 段落要約はどのくらいの長さが理想?
- 内容一致問題でよくあるミスは?
- 主旨問題を安定して取るコツは?
- 語句挿入問題の判断基準は?
- 音読は本当にリーディング力に効く?
- 語彙が足りずに正確に読めないときの対策は?
- 過去問の復習はどのように行うべき?
- 時間が足りない場合の優先順位は?
- 準2級〜準1級で練習内容は変えるべき?
英検リーディング・長文攻略法:正確さを上げる練習法
はじめに
英検のリーディング問題、とくに長文読解は「時間が足りない」「内容は分かったつもりなのに間違える」と悩む受験者が非常に多いパートです。単語や文法を覚えるだけでは点数が伸びず、「どう読めば正確に理解できるのか」がカギになります。
英検では、細かい語のニュアンスや筆者の主張の方向性を正確に読み取る力が問われます。つまり、単に“速く読む”だけでなく、“正しく読む”ことが求められているのです。
この記事では、英検の長文問題で「読み違いをなくす」「根拠を持って答えられる」ようになるための具体的な練習法を紹介します。準2級から準1級まで、どのレベルの受験者にも役立つ“正確さを上げる読解練習”をステップ形式で解説していきます。
読解で「正確さ」が求められる理由
英検のリーディング問題は、表面的な理解では正答できないように作られています。選択肢の違いがわずかで、どれも一見正しそうに見えるため、「文意の取り違え」や「細部の読み落とし」が命取りになります。
たとえば、同じ「agree」という単語でも、“部分的に同意している”のか“完全に賛成している”のかで、選ぶべき選択肢が変わります。つまり、曖昧な理解のままでは正確に選べないのです。
特に準1級や1級では、筆者の主張・トーン・意図の読み取りが問われます。「全体の流れをつかむ速読」だけではなく、「根拠をもって選ぶ精読力」を鍛えることが、確実にスコアを上げる近道になります。
ステップ1:スラッシュリーディングで構造をつかむ
英文を正確に理解するための第一歩は、「文の構造を見抜くこと」です。その練習法として効果的なのがスラッシュリーディングです。文を意味のかたまりごとにスラッシュ( / )で区切り、前から順に理解していく方法です。
例:
The government / decided to increase / the budget for education.
→ 「政府は/増やすことを決定した/教育予算を」
こうして読むことで、主語(S)、動詞(V)、目的語(O)の関係が明確になり、文構造を見失うことがなくなります。
英検の長文では、複雑な構文や修飾語が多く登場します。スラッシュリーディングを日常的に練習することで、「英文を前から正確に処理する」習慣が身につき、誤訳や読み飛ばしを防ぐことができます。
ステップ2:パラグラフごとの要点をまとめる
長文読解では、「全体の構成」をつかむことが正確さにつながります。文単位の理解にとどまらず、各パラグラフの主張や役割を一文でまとめる練習をしてみましょう。
たとえば次のように整理します:
-
第1パラグラフ:筆者の主張や問題提起
-
第2パラグラフ:理由や具体例
-
第3パラグラフ:結論や提案
こうして段落ごとの要点を把握すると、全体の論理の流れが明確になります。
この練習を繰り返すことで、設問の根拠を探す際に「どの段落に答えがありそうか」を予測できるようになります。また、内容一致問題や主旨問題にも強くなり、正確さとスピードの両方を高める効果があります。
ステップ3:根拠の場所を明示する「証拠探し」訓練
リーディングの正確さを高めるために欠かせないのが、**「根拠を明確にする読み方」**です。英検の長文問題では、すべての正解に必ず本文中の根拠があります。これを意識するだけで、読みの精度が一気に上がります。
練習方法はシンプルです:
-
問題を解いたあと、選んだ選択肢の根拠となる英文に下線を引く
-
根拠が曖昧な場合は、本文をもう一度読み直す
-
他の選択肢が間違いである理由も、本文のどこに示されているか確認する
この「証拠探し」を習慣にすると、“なんとなく選ぶ”読み方から“根拠を持って答える”読み方へと変化します。結果として、理解力だけでなく、読解中の集中力も格段に向上します。
ステップ4:精読と速読をバランスよく
英検の長文読解で得点を安定させるには、精読と速読の両立が不可欠です。どちらか一方に偏ると、理解が浅くなったり、時間が足りなくなったりします。
まずは精読から始めましょう。
1文1文を丁寧に読み、文構造・文法・語彙・論理関係をしっかり確認します。わからない単語や構文は放置せず、その場で調べて理解を定着させます。
次に、速読の練習を取り入れます。過去問や模試を使い、時間を計って読むことで「制限時間内に正確に読む力」を鍛えます。精読で積み上げた基礎があれば、速読でも理解の精度が落ちません。
ポイントは、**「精読で正確さを身につけ、速読で実戦力を磨く」**という順序です。英検の高得点者は、この2つを意識的に使い分けています。
ステップ5:設問タイプ別の読み方を意識する
英検の長文読解は、設問タイプによって「求められる読み方」が異なります。問題形式ごとに意識すべきポイントを押さえることで、正答率が安定します。
内容一致問題
本文の具体的な事実や意見を正確に読み取る問題です。
-
根拠となる文を探すときは、主語・否定語・比較表現に注意
-
一見正しそうでも、「一部が違う」選択肢を見抜くことが重要
主旨問題
筆者の主張や全体の流れを問う問題です。
-
各パラグラフの要点をまとめたうえで、**一番上位の主張(main idea)**を探す
-
具体例や補足説明に引っ張られず、筆者のトーンに注目する
語句挿入問題
文と文のつながりを理解していないと正解できません。
-
however, therefore, moreover などの論理展開語を手がかりにする
-
前後の文が「対比」「因果」「補足」どの関係かを判断する
このように、設問タイプごとの読み方を意識することで、無駄な読み直しを減らし、効率的かつ正確なリーディングが可能になります。
https://3d-universal.com/eiken-study-guide