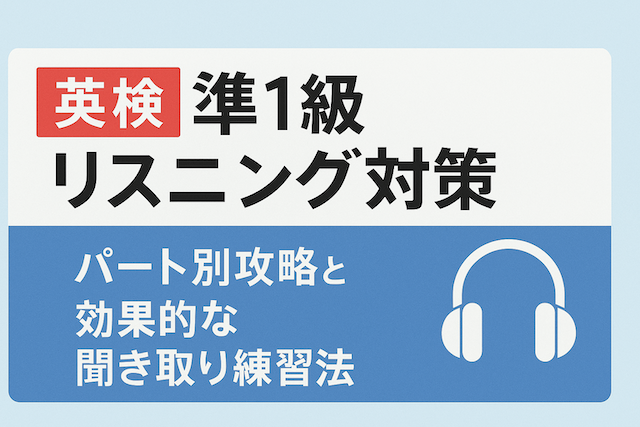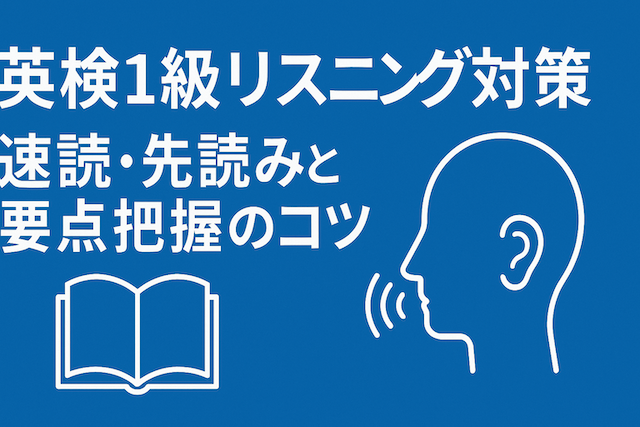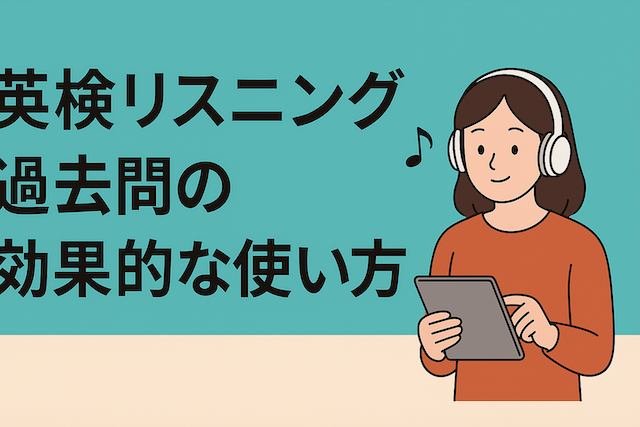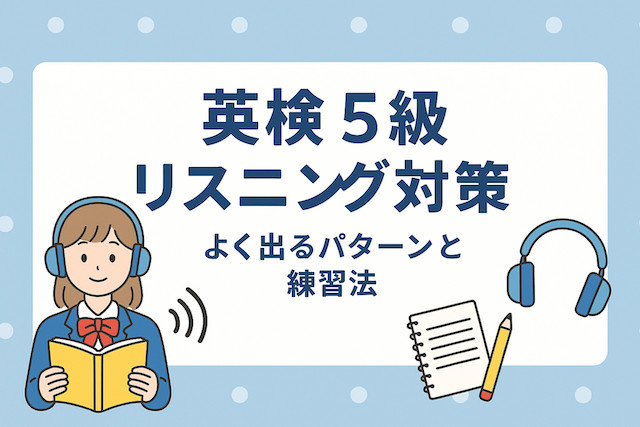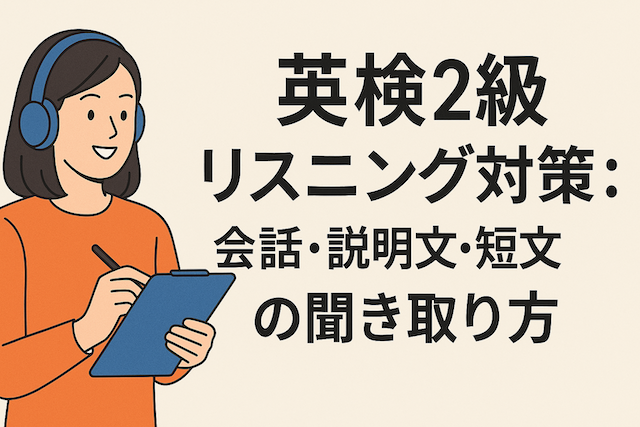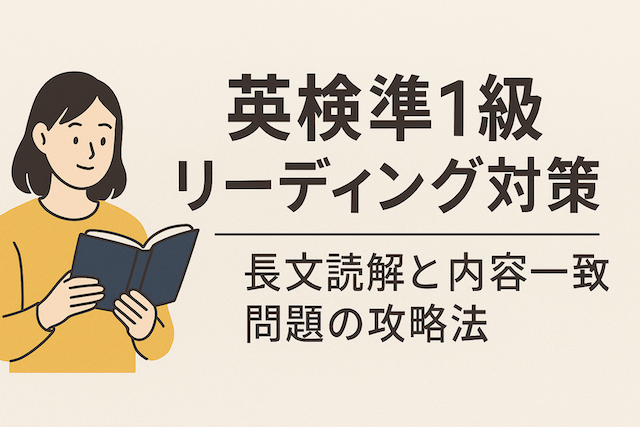目次
- 英検準1級リスニング対策:パート別攻略と効果的な聞き取り練習法
- はじめに
- 英検準1級リスニングの出題構成
- Part 1:会話問題の攻略法
- Part 2:説明文(ニュース・講義)問題の攻略法
- Part 3:インタビュー・ディスカッション問題の攻略法
- 効果的なリスニング練習法
- おすすめ教材とアプリ
- この記事のまとめ
- よくある質問(FAQs)
- 英検準1級リスニングは毎日どれくらい練習すれば効果がありますか?
- 精聴と多聴はどう使い分ければいいですか?
- ディクテーションはやったほうがいいですか?
- シャドーイングの正しいやり方は?
- Part 1(会話)はどこに注意すれば得点が上がりますか?
- Part 2(説明文)で数字や固有名詞が覚えられません
- Part 3(インタビュー・討論)で話者の立場が混乱します
- 語彙が原因で聞き取れないと感じます。対策は?
- アクセントや速さに慣れるには?
- メモは取ったほうがいいですか?
- 過去問はいつから使うのがベスト?
- おすすめの1週間サイクルを教えて
- 本番で聞き逃したときのリカバリーは?
- イヤホン・デバイスの学習面での注意点は?
- 点数が伸びない停滞期の乗り越え方は?
- 試験直前の48時間は何をすべき?
- 不正解の復習はどう記録すると効率的?
- 独学でも合格レベルまで到達できますか?
- おすすめの無料リソースは?
- 再受験の戦略は?
英検準1級リスニング対策:パート別攻略と効果的な聞き取り練習法
はじめに
英検準1級のリスニングは、多くの受験者にとって最大の難関のひとつです。語彙や文法の知識があっても、ネイティブスピードの音声を正確に理解する力が求められるため、得点が安定しにくいパートでもあります。
特に準1級では、社会問題・教育・環境・テクノロジーなど抽象的なテーマが多く、単語を聞き取るだけでは意味をつかめません。話の構成、話者の意図、論理の流れを把握する「リスニング読解力」が必要です。
この記事では、英検準1級リスニングテストのパート別攻略法と、得点力を高める効果的な聞き取り練習法を詳しく解説します。毎日の学習で少しずつ“耳”を鍛え、確実にリスニングスコアを伸ばしていきましょう。
英検準1級リスニングの出題構成
英検準1級のリスニングテストは、全体で約30分間・**全3パート構成(計23問)**となっています。
日常会話から学術的な説明、ニュース、インタビューまで幅広く出題され、総合的なリスニング力が試されます。
| パート | 内容 | 問題形式 | 問題数 |
|---|---|---|---|
| Part 1 | 会話の内容一致選択 | 2人の短い会話を聞き、内容に合う選択肢を選ぶ | 12問 |
| Part 2 | 説明文の内容一致選択 | ニュース・講義・ナレーションなどのモノローグ | 6問 |
| Part 3 | インタビュー・ディスカッション | 複数人の対話を聞き、内容や話者の意見を問う | 5問 |
各パートでは、出題傾向と求められるスキルが異なります。
Part 1では「要点の聞き取り」、Part 2では「情報整理力」、Part 3では「話者の意見理解」が鍵になります。
リスニングの全体的な難易度は英検2級より一段階上で、スピードが速く、語彙が抽象的なのが特徴です。そのため、各パートの特徴を把握して、目的に応じたトレーニングを行うことが合格への近道となります。
Part 1:会話問題の攻略法
特徴
Part 1は、2人の会話を聞いて内容に最も合う選択肢を選ぶ形式です。
話題は日常生活・職場・学校・社会的な出来事など多岐にわたり、短いながらも文脈を理解する力が問われます。
攻略ポイント
-
会話の目的をつかむ
導入のあいさつや雑談ではなく、話の中心となる「目的」や「問題点」に注目します。
例:「プレゼンの準備が間に合わない」「商品が届かない」など、何について話しているのかを素早く把握。 -
選択肢を先読みする
音声が流れる前に設問と選択肢を読み、何を問われるかを予測しておくと集中して聞けます。 -
話の方向転換に注意
“Yes, but〜”“Actually〜”“However〜”といった表現のあとに答えの核心が出ることが多いです。
話者の意見が途中で変わるパターンは頻出です。
効果的な練習法
-
過去問のPart 1を1日1セット解く習慣をつける
-
聞き取れなかった箇所をスクリプトで確認→音声を繰り返し聞く
-
シャドーイング(音声を追いかけて発音)を行い、リズムやスピードに慣れる
-
BBC Learning Englishなどの短い会話素材を使い、要約を1文でまとめる練習を行う
Part 1は一見簡単そうに見えますが、**「細部よりも全体の意図を理解できるか」**が合否を分けるポイントです。
Part 2:説明文(ニュース・講義)問題の攻略法
特徴
Part 2では、1人の話者によるナレーション形式の説明文が流れます。
テーマは環境問題、テクノロジー、教育、社会現象など幅広く、英検準1級らしいアカデミックな内容が多いのが特徴です。
音声は一度しか流れないため、集中力と論理の把握力が鍵になります。
攻略ポイント
-
全体の構成を意識して聞く
多くの説明文は「導入 → 詳細 → 例示 → 結論」という流れで構成されています。
聞きながら「今は話のどの部分か」を意識すると、内容を整理しやすくなります。 -
重要な名詞・数字・理由に注目
事実確認を問う問題が多く、固有名詞・データ・原因・結果などが正答のカギになることが多いです。 -
接続詞で流れをつかむ
“However”で逆転、“For example”で具体例、“As a result”で結論——これらのシグナルワードを聞き逃さないように。
効果的な練習法
-
TED TalksやNHK World Newsなどの3分程度の英語スピーチを活用し、内容を英語で要約する
-
英検準1級の過去問で**ディクテーション(書き取り)**を行い、理解できなかった構文や語彙を分析する
-
聞きながらキーワードを箇条書きでメモする練習を日課にする(完璧に書かなくてもOK)
Part 2は情報量が多く難易度も高いですが、「全体の流れ」と「要点キーワード」さえ押さえれば安定して得点できます。
Part 3:インタビュー・ディスカッション問題の攻略法
特徴
Part 3は、2人または複数人によるインタビュー形式・ディスカッション形式の会話が出題されます。
他のパートと異なり、登場人物の意見や立場の違い、感情のニュアンスを理解する必要があります。
英検準1級のリスニングではこのパートの比重が高く、内容の深い理解と要約力が求められます。
攻略ポイント
-
登場人物の関係を最初に把握する
冒頭の数秒で「誰が誰に話しているか」を確認しましょう。
例:「インタビュアーと専門家」「司会者と参加者」など関係を理解すると、会話の方向がつかみやすくなります。 -
意見の違いを整理する
1人が賛成、もう1人が懐疑的、というように立場の対比が頻出です。
聞きながら「A=賛成、B=反対」など簡単なメモを取ると、質問への回答が明確になります。 -
質問の意図に注意する
“What does the man imply?” や “What can be inferred from the conversation?” のような設問では、**発言の裏にある意図(imply, suggest)**を推測する力が必要です。
単なる表面理解ではなく、話の流れから結論を導く練習を意識しましょう。
効果的な練習法
-
英検公式問題集やアプリでPart 3だけを集中的に解く
-
海外ポッドキャスト(NPR、BBCなど)のインタビュー番組を聞き、登場人物の立場をメモにまとめる
-
シャドーイングの際に「どの話者がどんな意見を述べたか」を意識して再現練習する
Part 3は長く感じますが、「意見の対比」や「話者の意図」に焦点を当てることで安定した得点が可能です。
一語一句を追うより、「誰が何を主張しているのか」を常に意識して聞くのがコツです。
効果的なリスニング練習法
1. 精聴と多聴をバランスよく行う
リスニング力を高めるには、**精聴(じっくり聞く)と多聴(たくさん聞く)**の両方が必要です。
-
精聴:短い音声を繰り返し聞いて、完全に理解できるまで確認する練習。文法・語彙・発音の理解を深めます。
-
多聴:内容をすべて理解しようとせず、全体の流れや要点をつかむ練習。耳のスピード対応力を養います。
1日10〜15分でも構いません。
「英検公式音源 → TED Talks → BBCポッドキャスト」のように、難易度を徐々に上げるのがおすすめです。
2. 英語の「音の変化」に慣れる
英検準1級レベルでは、**ネイティブ特有の音の省略・連結(リエゾン)**が頻出します。
たとえば:
-
going to → gonna
-
want to → wanna
-
kind of → kinda
-
out of → outta
単語単位ではなく「フレーズ単位」で音が変化するため、スクリプト付き音源を聞きながら確認し、耳で覚えることが重要です。
3. 同じ素材を繰り返し使う
新しい音源に次々挑戦するより、同じ素材を3〜5回繰り返す方が学習効率が高いです。
-
1回目:意味をざっくり理解
-
2回目:スクリプトを見て内容を確認
-
3回目:スクリプトなしでリピート
-
4回目以降:シャドーイングで音の再現練習
「知っている音源」を使って耳を慣らすことで、理解スピードと記憶の定着が大きく向上します。
4. シャドーイングで実戦力を強化
シャドーイングとは、音声の後を0.5秒ほど遅れて追いかける練習法です。
文のリズム・イントネーション・発音が自然に身につき、リスニングとスピーキング両方に効果があります。
特に英検準1級では話の抑揚(トーン)で意見の違いを判断する問題が多いため、発音のクセを自分の口で再現できるレベルを目指しましょう。
5. ニュースやポッドキャストを日常に取り入れる
日常のスキマ時間に英語音声を流す「ながら学習」も効果的です。
おすすめは以下の音源:
-
NHK World Japan(ややゆっくり)
-
BBC Learning English(中上級者向け)
-
VOA Learning English(スクリプト付き)
通学・通勤・ランニング中などに継続することで、“英語耳”が自然に育ちます。
おすすめ教材とアプリ
リスニング力を上げるには、「レベルに合った教材」と「継続できるツール」を組み合わせるのが効果的です。ここでは、英検準1級の受験者に特に人気が高い教材・アプリを紹介します。
書籍教材
1. 『英検準1級リスニング問題120』(旺文社)
実際の試験形式に近く、パート別に段階的な練習ができる定番教材です。
音声スピードや出題傾向が本番とほぼ同じで、模試感覚で使用できます。
2. 『英検準1級 過去6回全問題集』(旺文社)
過去問で出題傾向を把握し、出題テーマ・語彙・話し方のパターンを分析するのに最適。
解説も丁寧なので、自己学習でも使いやすい一冊です。
3. 『英検準1級 リスニング完全制覇』(ジャパンタイムズ出版)
会話・講義・インタビューなど、実戦形式の問題を徹底的に練習できます。
高得点を狙う上級者にもおすすめです。
アプリ・デジタル教材
1. 英検スタディギア for EIKEN(公式)
リスニング・単語・模試を一括管理できる公式アプリ。
自動採点・解答分析機能があり、自分の弱点を可視化できます。
2. BBC Learning English
毎日更新される短いニュース・会話素材が豊富。
「6 Minute English」シリーズは、英検準1級レベルのリスニング練習に最適です。
3. TED Talks / NHK World News
ナチュラルスピードのスピーチを使って、内容要約やディクテーション練習に活用できます。
テーマが英検のPart 2・3と非常に似ているのが特徴です。
学習のコツ
-
書籍で基礎力を固める → アプリで毎日トレーニング → ニュースで実戦感覚を磨く
-
毎日10分でも耳に英語を入れる習慣を作る
-
同じ素材を3回以上使い、**「聞ける→理解できる→要約できる」**の3段階で練習する
この記事のまとめ
英検準1級のリスニングは、単なる「聞き取り力」だけでなく、論理の流れ・話者の意図・全体の要約力を問う高度なテストです。
ポイントを整理すると以下の通りです。
-
Part 1(会話):話の目的と流れを素早くつかむ。トーン変化に注意。
-
Part 2(説明文):接続詞やキーワードを手がかりに、全体構造を意識して聞く。
-
Part 3(インタビュー・ディスカッション):話者の立場・意見の違いを明確に把握する。
-
練習法:精聴と多聴の併用、シャドーイング、同じ素材の反復が効果的。
-
教材:公式過去問+BBCやTEDなどの実用音声で「耳の慣れ」を作る。
リスニングは、毎日の積み重ねで確実に伸びるスキルです。
最初は聞き取れなくても、同じ素材を繰り返すことで脳が英語のリズムを理解し始めます。
焦らず、毎日10分でも「耳を英語に慣らす習慣」を続けましょう。
努力を重ねれば、準1級のリスニングも必ず得点源に変わります。
よくある質問(FAQs)
英検準1級リスニングは毎日どれくらい練習すれば効果がありますか?
最低でも1日10〜15分の継続が効果的です。時間が取れる日は30分〜45分で「精聴→スクリプト確認→シャドーイング」の3ステップを1サイクル回しましょう。
精聴と多聴はどう使い分ければいいですか?
精聴は短い素材(30秒〜2分)を繰り返し完璧に理解する練習、多聴は長め素材(3〜10分)で要点だけをつかむ練習です。週の前半に精聴多め、後半に多聴多めなど、比率を60:40程度で調整しましょう。
ディクテーションはやったほうがいいですか?
週に2回程度がおすすめです。全文ではなく、聞き取れない箇所だけピンポイントで書き取り、原因(音の連結、語彙不足、構文理解不足)を特定しましょう。
シャドーイングの正しいやり方は?
①内容理解→②スクリプト見ながら同時追従→③スクリプトなしで追従→④録音して発音・リズムを自己評価、の順で行います。1素材につき3〜5回が目安です。
Part 1(会話)はどこに注意すれば得点が上がりますか?
“Actually, 〜”“However, 〜”“Yes, but 〜”などの方向転換シグナルに注目し、会話の目的(依頼・問題・提案)を特定しましょう。細部より意図を優先します。
Part 2(説明文)で数字や固有名詞が覚えられません
キーワードのみの略語メモに切り替えましょう(例:cost↑、2019→規制開始、Prof.Smith→反対)。全文メモは禁物です。
Part 3(インタビュー・討論)で話者の立場が混乱します
冒頭10秒で「役割メモ」を作成(例:A=司会、中立/B=研究者、肯定/C=住民、懐疑)。以後は賛否の変化にだけ印を付けて追跡します。
語彙が原因で聞き取れないと感じます。対策は?
頻出トピック別にセットで覚えます(環境・教育・テック・医療など)。同義語・反意語も併せて10語→例文→音読→聞き取りの順で運用可能にしましょう。
アクセントや速さに慣れるには?
英米だけでなく多様な話者の素材(BBC、VOA、NHK World、TED)をローテーション。再生速度は0.9→1.0→1.1の段階で慣らすと負荷が最適化されます。
メモは取ったほうがいいですか?
はい。ただしキーワードのみ(名詞・数字・因果)。記号化(⇔, →, ▲, %)で手を止めないこと。1問あたり2〜4語で十分です。
過去問はいつから使うのがベスト?
基礎を2週間固めたらすぐ導入。1回分を「通し→弱点復習→翌週リベンジ」で回し、3周目は音源をシャドーイング素材に転用します。
おすすめの1週間サイクルを教えて
- 月:Part 1精聴+シャドーイング
- 火:Part 2精聴(ディクテ)
- 水:Part 3通し演習+要約
- 木:ニュース多聴(6〜10分×2本)
- 金:過去問1セット(弱点記録)
- 土:弱点パートのみ再演習+録音チェック
- 日:軽めの多聴&総復習
本番で聞き逃したときのリカバリーは?
設問のフォーカス(人物・理由・結果)に戻り、次のシグナルワード(However, As a result, For example など)を待って再合流。迷ったら消去法で2択まで絞ります。
イヤホン・デバイスの学習面での注意点は?
学習時は同じ機器・音量・環境を固定し、試験想定の音量で練習。ホワイトノイズを避け、音質より安定性を優先します。
点数が伸びない停滞期の乗り越え方は?
素材を固定して「再現性」を測定します。同一素材で理解度80%→要約→暗唱の3指標を1週間追跡。伸びない要因(音/語彙/構文/推論)を1つに絞って対処。
試験直前の48時間は何をすべき?
新規素材は封印。過去問音源の聞き流し(1.0〜1.1倍)→頻出表現の口慣らし→弱点パートだけ軽く精聴。睡眠と当日の耳慣らし(5〜10分)を最優先。
不正解の復習はどう記録すると効率的?
「設問タイプ×原因」でタグ管理(例:詳細照合×数字、推論×トーン、主旨把握×接続詞)。同タグが3つ溜まったら専用ドリルを作成して集中的に克服。
独学でも合格レベルまで到達できますか?
可能です。過去問+ニュース+シャドーイングの三点セットを継続できれば到達可能です。客観評価用に週1回だけタイマー付き通し演習を行いましょう。
おすすめの無料リソースは?
BBC Learning English(6 Minute English)、VOA Learning English(スクリプト付き)、NHK World(語彙シンプル)。いずれも準1級の題材と親和性が高いです。
再受験の戦略は?
前回のスコアレポートでパート別の弱点を特定し、次回試験日から逆算して6週間計画(基礎2週→過去問強化2週→総合仕上げ2週)を組みます。毎週末に模試で進捗確認を。